ストレンジ・フルーツCEOの大江旅人氏は、職業アート・ディレクター。これまでジャズなど様々な分野に関わってきたが、20年前、グローブライドに招かれて『オノフ』をディレクションする立場についた。「アートな発想」が期待されてのことだった。
以来、ゴルフブランドでライフスタイルを確立すべく奮闘を重ねてきた。発売当時は白洲次郎の「Play Fast!」を広告のキャッチコピーに使ったり、「上質」「おとな」というキーワードを多用して、「飛んで曲がらない」が主流のゴルフ界に一石を投じた。一言でいえば、ダンディズムを追求するのが『オノフ』だった。
が、ゴルフによるライフスタイルの確立は「道半ば」と振り返る。「でもね、コロナが来たじゃないですか。生活様式が一変する中で、ゴルフクラブの開発も根本から見直す必要がある」
それで熟考を重ねた結果、これからのクラブ開発は「ゆらぎ」の要素を取り入れて「日常のゴルフ」を実現するところにあるという。
それだけを聞けば、ちっともわからない。どういったことか?
(聞き手・GEW片山哲郎 ハウスオノフの写真提供ストレンジ・フルーツ)
「風土とゴルフ」
 4~5年ぶりのご無沙汰ですが、今はどんな生活ですか?
4~5年ぶりのご無沙汰ですが、今はどんな生活ですか?
「実は東京と沖縄が半々なんですよ。
2年半前にオノフショップを沖縄に開きましてね。そもそもは8~9年前、シン・ヒョンジュがカヌチャリゾートで合宿をしていて、それを撮影に行って気に入って、知人に土地探しを頼んだら『いい場所が見つかりました』って(笑)
カヌチャのコースから3分ほどで、ロケーションが抜群にいい。土地は全部で600坪かな」
広いですねえ。
「借地だけどね(笑)。敷地の中にバンカーを作ったり、屋内にはバーも併設しています。初めてのオンリーショップで『オノフ』の世界観を表現しました。
商品は『オノフ』中心の品揃えで、この7月から木の圧の帆布製品も置いています。まあ、夜は星空を見上げながら一杯やったりね、今度遊びに来てください」
コロナが落ち着いたら伺います。大江さんは『オノフ』のディレクターという役割ですが、活動内容はどうなってますか?
「ヘッドの設計は専門家がやりますから、ぼくはデザインやイメージが主ですね。シェイプのイメージやデザインの雰囲気、それらをデッサンで描くこともしています。
年末には次のカタログやプロモーション用の素材も作るので、けっこう忙しくやってますよ」
『オノフ』はデビューして何年になりますか?
「今年で20年になります」
長いですねえ、飽きませんか?
「飽きませんよ(苦笑)。というか、20年経ってもやりたいことができてない。ぼくがやりたいのは『日常のゴルフ』を実現することでね、これは立ち上げからずう~っと変わらないポリシーだし、そのための世界観を『オノフ』で提案したいと思っています」
『オノフ』は業界には珍しく思想的なブランドで、性能や構造をPRするよりもライフスタイル・ブランドを目指してきた。
「そう。それをずう~っと言い続けてますが難しかったんです。ところが今回、コロナでニューノーマルという言葉が出てきたでしょ、やっと時代が来たのかなぁと。
ニューノーマルってとても心地いい、やわらかい言葉じゃないですか。GEWの記事も最近は、ニューノーマルに焦点を当てたものが多いですよね。それもあって、ぼくが提案するゴルフライフ、ゴルフスタイルが理解してもらえる時代が来た。ようやく来たという感じですね(笑)」
その話を「物作り」につなげるとどうなりますか?
「そうですねえ。『日常のゴルフ』を基点に考えれば、その対極がタイガー・ウッズ、昔はジャンボ尾崎とかの存在ですね。彼らのゴルフに憧れて、彼らを目指すクラスターが沢山いた。そこを狙う物作りです。
その一方、たとえばスコットランドの田舎町でゴルフ好きが集まる世界もありますよね。ぼくが志向するのはその世界で、リージョナリズムと言いますが、日本では欠けている部分なんです」
リージョンは「地域」ですね。地域性は「風土」にも置き換えられるかな。
「そう。地域ごとにいろんな風土がありますが、ぼくが日本でリージョナリズムを感じるのは、長崎におぢか島(小値賀)ってあるんですが、そこのゴルフなんですよ」
おぢかのゴルフって何ですか?
「自分達で造るんです」
なにを?
「ゴルフ場ですよ。元銀行員とか町役場の人間がユンボを動かして造ったんです。3年前、撮影で訪れて初めて知りましてね、これこそ俺が目指すゴルフだと、強い衝撃を受けました。
近所の図書館に行くような感覚でプレーする『日常のゴルフ』が、そこにあった。要するに『散歩するゴルフ』って感じなんですよ。日常の連続にゴルフがふわっとある感じで」
若者よ、田舎に帰れ!

「話が飛ぶようで飛ばないんだけど、新宿のホストの感染ね、なんで彼らに税金使って休業補償しなきゃいけないんだと」
飛びますねえ(笑)
「まあ、聞いてください。で、夜の街がクラスターになった一因に、この国の一次産業は極端に少なくて、三次産業の比率が異常に高いことがある」
第一次産業は名目GDPで4%ほど、二次が25%で三次が70%の割合ですね。
「そう、バランスがあまりにも悪いじゃないですか。コロナみたいにマッシブ(重大)な問題は自動車のサプライチェーンどころの話じゃなくて、国家としての制度疲労、構造的な欠陥が浮き彫りになったわけですよ。
それでホストの話ですが、彼らの大半は田舎から出てきたわけです」
花の都に憧れて。
「それでホストやキャバクラで働いてる。声を大にして言いたいですよ、『帰りなさいッ』て。爺さん婆さんの土地に帰りなさいよ。そこは限界集落になってるぜ。帰って田畑を耕せよ、魚釣れよ、林業やれよと。彼らが都会に出てくる理由は、」
憧れでしょ。それと「稼げる」という幻想もある。
「その憧れと現実のギャップがとんでもなく大きいじゃないですか。ぼくは経済学者じゃないからわからんけど、直感的には3割ずつ、これが第一次から第三次産業までのバランスかもしれないし、少なくとも御節料理の食材の99%がインポートってあり得ないですよ」
都会暮らしは古今東西、若者共通の願望じゃないですか。それを強制的に「帰れ」とは言えないでしょう。
「だから第一次産業で働くことはカッコイイという風潮をつくるべきなんです。国の要請ということじゃなく、自発的に帰りたいと思わせる。それで『モンベル』みたいなブランドがカッコいい野良着を作ればいいんです。
古民家をリノベーションして、傍にゴルフ場もあるじゃないか、クラブ数本持って担ぎでやろうと。
話が遠回りしたけれど、ぼくが描く『日常のゴルフ』はそれなんですね。単に若者達にゴルフを、じゃなく、リージョナリズムを土台にして日常生活にゴルフを溶け込ませる。
これはひとつの切り口なんですが、それぐらいの発想をしないと日本のゴルフ産業はなくなりますよ」
「本気の9本セット」
 つまり、ゴルフ産業の再興を思想的に考えるわけですね。
つまり、ゴルフ産業の再興を思想的に考えるわけですね。
「思想というより、哲学に近い感じでしょうねぇ。ゴルフの在り方の問題や、自分の生活とゴルフとの距離の問題かな。
つまり施設面のハードを含めて、ゴルフという概念なりコンセプトをどうやって再デザインしていくのかという問題です。過去の継続や継承ではなく、新しいゴルフの哲学をどうやってつくるのか」
なるほどね。その話にハマりそうなのが、クラブハウスの耐用年数です。ゴルフ場はバブル前の70~80年代に大量に造成されましたが、当時開業したゴルフ場は軒並みクラブハウスの建て替えや補修を迫られている。
「そうなるよね」
その際、高い会員権を売るために建てた豪華なハウスがお荷物になる。建て替えには3億~5億円は掛かるし、補修で大きな空間容積を維持すればクリーニングコストや人件費が負担になる。
「なるほど、なるほど」
ゴルフの大衆化を目指すなら、スタート小屋だけで十分だと。その判断に、経営者の思想なり哲学が求められる。
「だとすれば、ぼくの話にハマるじゃないですか(笑)。仮にそのゴルフ場が地域のカントリークラブを目指すなら、それは地域の共有財産であり、自分達のゴルフ場だという意識をまずはつくる。
つまりね、『おらが村のカントリークラブ』にするための意識の再設計をどうするのか、という話ですよ。
ゴルフは楽しいし、一人でもまわれるじゃないですか。クラブ2~3本持って朝の散歩みたいにプレーできれば気持ちいいし、なんていうかなあ、爽快だと感じることが生きる糧になる。その力は非常に大きいですよ」
それが「ゴルフの日常化」につながるわけですね。個人的な話をすれば、最近は6本でプレーしてるんですよ。
「オッ、いいですねえ~」
ドライバーに鉄は5、7、9番と52度。軽量バッグに入れて電車で行く、車中は読書。
「まさに図書館じゃないですか、さすがです(笑)。というのも、ゴルフの日常化には物理的な課題として持ち運びの手軽さがある。そこでね、9本でやる『ナインクラブス』っていうのを以前から構想してるんですよ。
コースをティーグラウンドとフェアウェイ、グリーン周りに3分割して、それぞれ3本という発想です。今のクラブはロフト3度ピッチでフローしますが、ぼくの考えでやると6~7度になる。
でも、長く持ったり短く持ったりで飛距離は変わるし、同じ9本でも距離が欲しいひと用の9本と、シュアなゴルフ用の9本とか、ニーズによって分ければいいでしょ。
片山さんの6本もステキですが、ぼくの9本は本気の9本でね、理想はPGAの一流プロ、たとえばライアン・ムーアみたいな選手が9本を自分で担いで堂々と戦い、優勝したらカッコいい」
「カッコいい」は大事な要件ですね。ひとの関心を集めるし、それで『日常のゴルフ』が市民権を得るかもしれない。
「おっしゃるとおりです。これまでのハーフセットみたいな感覚じゃなくて、本気も本気、トーナメントで勝てる9本ですよ。
製造や設計技術が進化して、それだけの性能を9本に持たせることができるようになった。プロは9本でいろんな球を打ち分けますが、一般向けはそれより許容性があって、アベレージプレーヤーでも距離を打ち分けられる性能を用意してあげる。
まあ、そんなことを考えて楽しんでいます(笑)」
クラブ開発の本当の限界
毎年新しいクラブが出るけれど、開発面では閉塞感が否めませんね。そこの本当の問題は、開発者自身が楽しみながら発想できなくなっていて、1ヤードでも余計に飛ばそうと研究室で頭を抱えている。昔はBSの『オールターゲット11』やPRGRの『タラコ』とか、遊び心が詰まっていたのに。
「今はクラブが進化して、慣性モーメントの大型化とか、確実にやさしくなってるじゃないですか。なので、ぼくが一切使ったことがない言葉で『飛んで曲がらない』ってありますが、この面では進化しているわけですよ。
ただし、それだけでいいのかという想いは、以前から強く持ち続けています」
そこは今日、一番聞きたかったことなんです。ニューノーマルな開発を考える上で「飛んで曲がらない」のフレーズは打破しなきゃいけない、新しい発想が必要だろうと。
「まったく同感です」
1982年にマルマンがメタルの『ダンガン』を出して、理論武装に火がついて以来、この言葉の呪縛から逃れられない。
「まったくだよねえ」
開発者は1ヤードでも伸ばせとプレッシャーを掛けられて消耗するから、どうしても近視眼的になる。
「メーカーが悪いのか、ゴルファーのせいなのか。ぼくはね、日本のゴルファーの偏差値が圧倒的に低いと思っていて、もっとも低いのはプロですよ」
偏差値とは?
「簡単に言うと想像力とデリカシーです。そしてこの言葉は、ニューノーマルの世界において圧倒的に必要なことだと思う。これから新しい世界がやってきて、いろんな選択肢がある中で、自分はどの道に進むのかを想像できるかってことですよ。
プロゴルファーを見ていて思うのは、みんないいヤツなんですよ、本当に。だけど教養面では疑問符がつく。コメントでも『ん~』とか『え~』とか言ってるじゃない(苦笑)
一方で欧米のプロは、スピーチや立ち居振舞が洗練されていますよね。それを含めての想像力とデリカシーで、ゴルフの世界に限った話ではなく、ニューノーマルを生き抜く必須条件です」
想像力はわかりますが、デリカシーって何ですか?
「ひとを想う心ですね」
「利他」の精神?
「そこまで美しくはないのかな。単純に言えば気を遣えってことですよ。ゴルフの場合はグリーンキーパーに気を遣えよと。周囲のひとに、あるいはそのゴルフ場の経営者に気を遣えよと。そうすれば必要な事と不要な事が見えてくる。
それでさっきの話、『飛んで曲がらない』の呪縛ですが、それしかないって思い込んでいるゴルファーが悪いんです。自分にとって必要なのか、不要なのかではなく、その言葉にしか反応しない」
『オノフ』は説教臭い?
 十数年前、大沢商会の常務だった伊谷さんが面白い話をしてくれました。「日本は敗戦国だ。街頭テレビで力道山が外人レスラーをやっつけると狂喜した。つまり体力劣等民族だから、悲しいほど飛距離を欲しがるのだ」と。
十数年前、大沢商会の常務だった伊谷さんが面白い話をしてくれました。「日本は敗戦国だ。街頭テレビで力道山が外人レスラーをやっつけると狂喜した。つまり体力劣等民族だから、悲しいほど飛距離を欲しがるのだ」と。
「面白いねえ(笑)。それはひとつの考察としてとても面白い話だけど、日本のメーカーは『飛んで曲がらない』以外にゴルファーを振り向かせる言葉がないわけでしょ。その意味ではメーカーの発想力も問題ですね。
これに代わる言葉を探す中で、『オノフ』は20年前に『おとなの』とか『上質な』という言葉を使いましたが、それで若干、何かを言おうとしてるんだろうな、という雰囲気は感じてもらえたと思うんです」
「飛んで曲がらない」のアンチテーゼですね。別の言葉ではポスト・マテリアル、つまり「脱・物質主義」というか「脱・機能偏重主義」みたいなことになる。
「さらに別の言葉でいうと、サイコグラフィックになるわけです。つまり数値で全部表せる、置き換えられるモノではなく、もっと感覚的で気分や感性に依拠する世界ですね。
『飛んで曲がらない』は数値で表せる。そうではない価値観をずう~っと考えてきた中で『日常のゴルフ』はどうだろうと」
それは平易でいい言葉ですが、「飛んで曲がらない」と戦うにはパンチが弱いのかな。
「んー」
初代の『ゼクシオ』は広告で「美しく飛ばそう」というフレーズを使った。その後「空へ」とやりましたが、同時にテレビCMで「ゼクシオ・サウンド」を響かせた。
「ですよねえ。文字と音の両方で『飛び』の爽快感をイメージさせた。あの手法はとても素晴らしかったと思います。
あれから十数年経ってクラスターの細分化はあったけど、現実的には『飛び』にしか反応しない属性がマスですよね。
個人的には『飛び』に反応しない属性は3つぐらいあると思っていて、一番マイナーなのが自分でクラブを作って自分のゴルフの世界を楽しむタイプだと思う」
マニアックで、唯我独尊のタイプですね。あとのふたつは?
「わからない。ちょっと整理すると出てくると思うんだけど、たとえば片山さんみたいな6本のゴルフもそうかもしれない。極めてマイナーですけどね」
マーケッターが市場を分析するとき、マインドの切り分けでクラスター分類をするのが定番だけど、極めてマイナーな層はクラスターとして表出してこない。
「そうなんですが、そこに光を当てるのが大事というか」
そもそも『オノフ』はそこに光を当てるブランドとして20年前に登場した。初期の広告表現に白洲次郎の「Play Fast!」を使ったり、やたら高踏的で、高踏的にやると説教臭くなる。
「いやいやいやッ。仮に説教臭く聞こえたなら、それはぼくらの能力のなさなんでね(苦笑)」
早くまわれ、穴を埋めろ、ゴルフ場に来たときよりもキレイにして帰れとか。風紀委員みたいだった。
「あはははッ。そうですか」
ただまあ、思想的にやろうとすると、そうなりますね。同時に写真の表現にも力を入れて、スコットランドの荒涼たる大地をビジュアルに使った広告は良かったですね。
「ありがとうございます。スコットランドは二度撮影に行きましたが、あの土地は『オノフ』の聖地というか、ぼく自身、スコットランドのゴルフが大好きなんですよ。
その理由は日常に近いこともあるけれど、何よりも風景としてね、ゴルフコースが自然に寄り添っている。自然をねじ伏せたコースじゃなくて。そこが本当にいいんですよ」
大江さんはナチュラリストですか?
「そんなカッコいいもんじゃありませんが、単純にあの過酷な条件の中でやるのが面白いんです。ただね、大半のひとはその経験がないわけだから、それに近いことをリージョナリズムでやりたいと。
先ほどの話に戻りますが、軽いゴルフクラブのセットがある、出張に9本持って行って、時間を見つけてその土地のコースをふらりと訪ねる。それを『ナインクラブス』でやりたいんだと」
「出張ゴルフ」はイメージがわきますね。楽しいだろうなあ。
「それと、取ってつけた言い方ですが、14本が9本になればエコにもなるじゃないですか」
取ってつけたエコ話は大江さんらしくないというか、つまらないですね。エコはもっと、大真面目に語ってもらわないと。
「それはそうです(苦笑)」
荒井由実の声は「f分の1ゆらぎ」
 一連の話を聞いていると、武蔵野美大の学長の話を思い出します。「f分の1ゆらぎ」についての考察で、去年、GEWで書きました。
一連の話を聞いていると、武蔵野美大の学長の話を思い出します。「f分の1ゆらぎ」についての考察で、去年、GEWで書きました。
「あの記事、読みましたよ」
長澤学長いわく「数値化できる分野はAIがやってくれる。これから人間がやるのはそこじゃなくて『ゆらぎ』です」と。要するにf分の1の世界ですね。
「そう、まさにそこなんだッ」
川のせせらぎや、初夏のゴルフで微風に吹かれる涼感とか。
「そうそう、まさにそうですよ。先ほどサイコグラフィックの話をしましたが、『f分の1ゆらぎ』は数値化できない、人間の感性に訴え掛けるモノとして大きな研究課題なんですよ。
たとえばモンゴルの原住民がヒトに伝える音の出し方があるんですね。歌でもなく、口笛でもなく、『ホエ~~』という感じの音ですが、ある領域の周波数を発するとサウンドの大きさではなく遠くまで届くんです。
でね、それに近い声が荒井由実だと言われています。なぜ彼女の声がこれだけ長い間支持されるのか、それは声の質によるんだという説があるんですよ。
f分の1はそれと非常に近くて、川のせせらぎや風のそよぎ、扇風機もそれと似たようなことをやってますが、自然の風とはどうしても違うわけで」
違いますね。断続的に強弱をつけたりするけれど、自然の風みたいに不定型というか、不揃いにならない。
「それをフラクタルと言うんですが、いわゆる蝶々が飛ぶ軌跡のことなんです。面白いのは、これをニューノーマルの概念に取り入れると『生活のゆらぎ』になるんですよ。
さらにこれをリージョナリズムや『日常のゴルフ』につなげると、なんかこう、ふわっとしたゆとりになる。同じゴルフでも帰りの渋滞を気にしながらと、生活のゆらぎとして溶け込んでいるゴルフではまったく違うじゃないですか。
その空気感をね、どのような言葉で表せばいいんだろう。一緒に考えてくださいよ」
昔、広告表現で「ファジー」(曖昧)という言葉が流行ったけど「ゆらぎ」はそれとも違いますね。この感覚を言語化するのは難しいというか、言語は語釈、つまり本質的に意味づけされるわけで、意味じゃなく感じるのがゆらぎだから。
「言えるよねぇ。リンゴの味を正確に言葉に置き換えるのが難しいのと同じで(苦笑)」
歯応えや音、風味も味になりますから。まあ、言語は機能的だから、そう考えると「ゴルフの魅力」も言語化された空疎感がありますよね。
「ん、どういうこと?」
ゴルフは自然と向き合うスポーツだと言われると、山登りがあると思ってしまうし、健康にいいと言われると、歩けばいいと。そもそもゴルフを「目的化」して「価値化」することに違和感があって、大体の目的はほかの行為で代替えできる。
「なるほどねえ(笑)。そこを整理したいけど、難しいよねえ。そよ風のゆらぎの気持ち良さとか、大きな自然の中で小さな小さな人間が感じることって沢山あるじゃないですか。
感じるというのは、生きてきた時間の中に記憶があって、それに反応してるわけですよね。この流れで『ゴルフの魅力』を改めて考えると、さっきの『飛んで曲がらない』を打倒しなければいけませんが、実はこの言葉、意外と凄いのかもしれません。
だって小さな白球に思いを込めて、ボールが自分に成り代わって飛翔するわけだから、その記憶の反応は強く残るじゃないですか」
その反面、思いを込めた1打が逃げ惑うヘビのように情けなく草むらを走るとか。
「あるよねえ(笑)。そう考えると『飛んで曲がらない』は強烈なフレーズなんだろうなぁ。ただね、そこを越えないと新しい価値観を提示できないような気がしていて『リージョン』はどう?」
んー。地域主義?
「主義って言葉は使いたくないですね。もっとふわっとした『おらが村の』みたいな感じで」
んー。宿題にしてください。
「いずれにせよ、今回のコロナで改めて思うのは、結局のところこれからは過去の知見や流儀は通用しないし、度胸を据えてやるしかないんですよ。
ぼくね、ゴルフのニューノーマル本気で考えてますよ。限界集落や休耕地、そこに魅力的なコミュニティをつくって都会のホストを呼び戻す。9本のクラブで『日常のゴルフ』を溶け込ませる。
それを地域ぐるみで、ってことを本気でやりたいと思ってます」
[surfing_other_article id=55654]
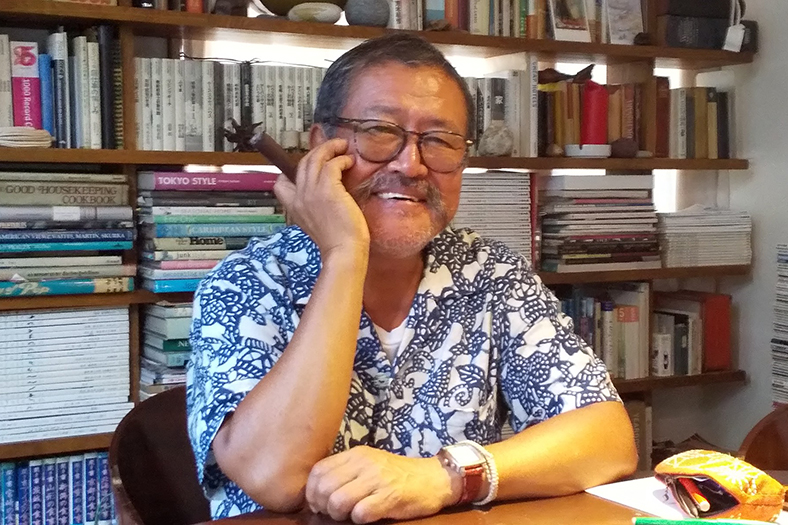
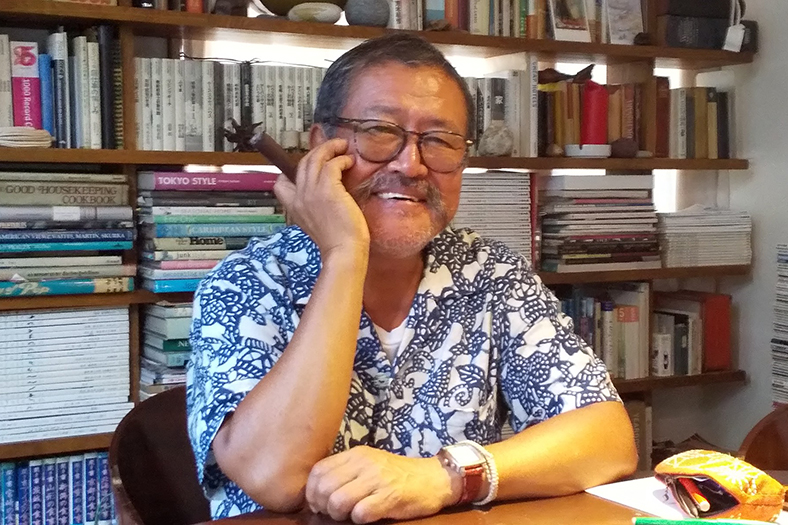
 4~5年ぶりのご無沙汰ですが、今はどんな生活ですか?
「実は東京と沖縄が半々なんですよ。
2年半前にオノフショップを沖縄に開きましてね。そもそもは8~9年前、シン・ヒョンジュがカヌチャリゾートで合宿をしていて、それを撮影に行って気に入って、知人に土地探しを頼んだら『いい場所が見つかりました』って(笑)
カヌチャのコースから3分ほどで、ロケーションが抜群にいい。土地は全部で600坪かな」
広いですねえ。
「借地だけどね(笑)。敷地の中にバンカーを作ったり、屋内にはバーも併設しています。初めてのオンリーショップで『オノフ』の世界観を表現しました。
商品は『オノフ』中心の品揃えで、この7月から木の圧の帆布製品も置いています。まあ、夜は星空を見上げながら一杯やったりね、今度遊びに来てください」
コロナが落ち着いたら伺います。大江さんは『オノフ』のディレクターという役割ですが、活動内容はどうなってますか?
「ヘッドの設計は専門家がやりますから、ぼくはデザインやイメージが主ですね。シェイプのイメージやデザインの雰囲気、それらをデッサンで描くこともしています。
年末には次のカタログやプロモーション用の素材も作るので、けっこう忙しくやってますよ」
『オノフ』はデビューして何年になりますか?
「今年で20年になります」
長いですねえ、飽きませんか?
「飽きませんよ(苦笑)。というか、20年経ってもやりたいことができてない。ぼくがやりたいのは『日常のゴルフ』を実現することでね、これは立ち上げからずう~っと変わらないポリシーだし、そのための世界観を『オノフ』で提案したいと思っています」
『オノフ』は業界には珍しく思想的なブランドで、性能や構造をPRするよりもライフスタイル・ブランドを目指してきた。
「そう。それをずう~っと言い続けてますが難しかったんです。ところが今回、コロナでニューノーマルという言葉が出てきたでしょ、やっと時代が来たのかなぁと。
ニューノーマルってとても心地いい、やわらかい言葉じゃないですか。GEWの記事も最近は、ニューノーマルに焦点を当てたものが多いですよね。それもあって、ぼくが提案するゴルフライフ、ゴルフスタイルが理解してもらえる時代が来た。ようやく来たという感じですね(笑)」
その話を「物作り」につなげるとどうなりますか?
「そうですねえ。『日常のゴルフ』を基点に考えれば、その対極がタイガー・ウッズ、昔はジャンボ尾崎とかの存在ですね。彼らのゴルフに憧れて、彼らを目指すクラスターが沢山いた。そこを狙う物作りです。
その一方、たとえばスコットランドの田舎町でゴルフ好きが集まる世界もありますよね。ぼくが志向するのはその世界で、リージョナリズムと言いますが、日本では欠けている部分なんです」
リージョンは「地域」ですね。地域性は「風土」にも置き換えられるかな。
「そう。地域ごとにいろんな風土がありますが、ぼくが日本でリージョナリズムを感じるのは、長崎におぢか島(小値賀)ってあるんですが、そこのゴルフなんですよ」
おぢかのゴルフって何ですか?
「自分達で造るんです」
なにを?
「ゴルフ場ですよ。元銀行員とか町役場の人間がユンボを動かして造ったんです。3年前、撮影で訪れて初めて知りましてね、これこそ俺が目指すゴルフだと、強い衝撃を受けました。
近所の図書館に行くような感覚でプレーする『日常のゴルフ』が、そこにあった。要するに『散歩するゴルフ』って感じなんですよ。日常の連続にゴルフがふわっとある感じで」
4~5年ぶりのご無沙汰ですが、今はどんな生活ですか?
「実は東京と沖縄が半々なんですよ。
2年半前にオノフショップを沖縄に開きましてね。そもそもは8~9年前、シン・ヒョンジュがカヌチャリゾートで合宿をしていて、それを撮影に行って気に入って、知人に土地探しを頼んだら『いい場所が見つかりました』って(笑)
カヌチャのコースから3分ほどで、ロケーションが抜群にいい。土地は全部で600坪かな」
広いですねえ。
「借地だけどね(笑)。敷地の中にバンカーを作ったり、屋内にはバーも併設しています。初めてのオンリーショップで『オノフ』の世界観を表現しました。
商品は『オノフ』中心の品揃えで、この7月から木の圧の帆布製品も置いています。まあ、夜は星空を見上げながら一杯やったりね、今度遊びに来てください」
コロナが落ち着いたら伺います。大江さんは『オノフ』のディレクターという役割ですが、活動内容はどうなってますか?
「ヘッドの設計は専門家がやりますから、ぼくはデザインやイメージが主ですね。シェイプのイメージやデザインの雰囲気、それらをデッサンで描くこともしています。
年末には次のカタログやプロモーション用の素材も作るので、けっこう忙しくやってますよ」
『オノフ』はデビューして何年になりますか?
「今年で20年になります」
長いですねえ、飽きませんか?
「飽きませんよ(苦笑)。というか、20年経ってもやりたいことができてない。ぼくがやりたいのは『日常のゴルフ』を実現することでね、これは立ち上げからずう~っと変わらないポリシーだし、そのための世界観を『オノフ』で提案したいと思っています」
『オノフ』は業界には珍しく思想的なブランドで、性能や構造をPRするよりもライフスタイル・ブランドを目指してきた。
「そう。それをずう~っと言い続けてますが難しかったんです。ところが今回、コロナでニューノーマルという言葉が出てきたでしょ、やっと時代が来たのかなぁと。
ニューノーマルってとても心地いい、やわらかい言葉じゃないですか。GEWの記事も最近は、ニューノーマルに焦点を当てたものが多いですよね。それもあって、ぼくが提案するゴルフライフ、ゴルフスタイルが理解してもらえる時代が来た。ようやく来たという感じですね(笑)」
その話を「物作り」につなげるとどうなりますか?
「そうですねえ。『日常のゴルフ』を基点に考えれば、その対極がタイガー・ウッズ、昔はジャンボ尾崎とかの存在ですね。彼らのゴルフに憧れて、彼らを目指すクラスターが沢山いた。そこを狙う物作りです。
その一方、たとえばスコットランドの田舎町でゴルフ好きが集まる世界もありますよね。ぼくが志向するのはその世界で、リージョナリズムと言いますが、日本では欠けている部分なんです」
リージョンは「地域」ですね。地域性は「風土」にも置き換えられるかな。
「そう。地域ごとにいろんな風土がありますが、ぼくが日本でリージョナリズムを感じるのは、長崎におぢか島(小値賀)ってあるんですが、そこのゴルフなんですよ」
おぢかのゴルフって何ですか?
「自分達で造るんです」
なにを?
「ゴルフ場ですよ。元銀行員とか町役場の人間がユンボを動かして造ったんです。3年前、撮影で訪れて初めて知りましてね、これこそ俺が目指すゴルフだと、強い衝撃を受けました。
近所の図書館に行くような感覚でプレーする『日常のゴルフ』が、そこにあった。要するに『散歩するゴルフ』って感じなんですよ。日常の連続にゴルフがふわっとある感じで」
 「話が飛ぶようで飛ばないんだけど、新宿のホストの感染ね、なんで彼らに税金使って休業補償しなきゃいけないんだと」
飛びますねえ(笑)
「まあ、聞いてください。で、夜の街がクラスターになった一因に、この国の一次産業は極端に少なくて、三次産業の比率が異常に高いことがある」
第一次産業は名目GDPで4%ほど、二次が25%で三次が70%の割合ですね。
「そう、バランスがあまりにも悪いじゃないですか。コロナみたいにマッシブ(重大)な問題は自動車のサプライチェーンどころの話じゃなくて、国家としての制度疲労、構造的な欠陥が浮き彫りになったわけですよ。
それでホストの話ですが、彼らの大半は田舎から出てきたわけです」
花の都に憧れて。
「それでホストやキャバクラで働いてる。声を大にして言いたいですよ、『帰りなさいッ』て。爺さん婆さんの土地に帰りなさいよ。そこは限界集落になってるぜ。帰って田畑を耕せよ、魚釣れよ、林業やれよと。彼らが都会に出てくる理由は、」
憧れでしょ。それと「稼げる」という幻想もある。
「その憧れと現実のギャップがとんでもなく大きいじゃないですか。ぼくは経済学者じゃないからわからんけど、直感的には3割ずつ、これが第一次から第三次産業までのバランスかもしれないし、少なくとも御節料理の食材の99%がインポートってあり得ないですよ」
都会暮らしは古今東西、若者共通の願望じゃないですか。それを強制的に「帰れ」とは言えないでしょう。
「だから第一次産業で働くことはカッコイイという風潮をつくるべきなんです。国の要請ということじゃなく、自発的に帰りたいと思わせる。それで『モンベル』みたいなブランドがカッコいい野良着を作ればいいんです。
古民家をリノベーションして、傍にゴルフ場もあるじゃないか、クラブ数本持って担ぎでやろうと。
話が遠回りしたけれど、ぼくが描く『日常のゴルフ』はそれなんですね。単に若者達にゴルフを、じゃなく、リージョナリズムを土台にして日常生活にゴルフを溶け込ませる。
これはひとつの切り口なんですが、それぐらいの発想をしないと日本のゴルフ産業はなくなりますよ」
「話が飛ぶようで飛ばないんだけど、新宿のホストの感染ね、なんで彼らに税金使って休業補償しなきゃいけないんだと」
飛びますねえ(笑)
「まあ、聞いてください。で、夜の街がクラスターになった一因に、この国の一次産業は極端に少なくて、三次産業の比率が異常に高いことがある」
第一次産業は名目GDPで4%ほど、二次が25%で三次が70%の割合ですね。
「そう、バランスがあまりにも悪いじゃないですか。コロナみたいにマッシブ(重大)な問題は自動車のサプライチェーンどころの話じゃなくて、国家としての制度疲労、構造的な欠陥が浮き彫りになったわけですよ。
それでホストの話ですが、彼らの大半は田舎から出てきたわけです」
花の都に憧れて。
「それでホストやキャバクラで働いてる。声を大にして言いたいですよ、『帰りなさいッ』て。爺さん婆さんの土地に帰りなさいよ。そこは限界集落になってるぜ。帰って田畑を耕せよ、魚釣れよ、林業やれよと。彼らが都会に出てくる理由は、」
憧れでしょ。それと「稼げる」という幻想もある。
「その憧れと現実のギャップがとんでもなく大きいじゃないですか。ぼくは経済学者じゃないからわからんけど、直感的には3割ずつ、これが第一次から第三次産業までのバランスかもしれないし、少なくとも御節料理の食材の99%がインポートってあり得ないですよ」
都会暮らしは古今東西、若者共通の願望じゃないですか。それを強制的に「帰れ」とは言えないでしょう。
「だから第一次産業で働くことはカッコイイという風潮をつくるべきなんです。国の要請ということじゃなく、自発的に帰りたいと思わせる。それで『モンベル』みたいなブランドがカッコいい野良着を作ればいいんです。
古民家をリノベーションして、傍にゴルフ場もあるじゃないか、クラブ数本持って担ぎでやろうと。
話が遠回りしたけれど、ぼくが描く『日常のゴルフ』はそれなんですね。単に若者達にゴルフを、じゃなく、リージョナリズムを土台にして日常生活にゴルフを溶け込ませる。
これはひとつの切り口なんですが、それぐらいの発想をしないと日本のゴルフ産業はなくなりますよ」
 つまり、ゴルフ産業の再興を思想的に考えるわけですね。
「思想というより、哲学に近い感じでしょうねぇ。ゴルフの在り方の問題や、自分の生活とゴルフとの距離の問題かな。
つまり施設面のハードを含めて、ゴルフという概念なりコンセプトをどうやって再デザインしていくのかという問題です。過去の継続や継承ではなく、新しいゴルフの哲学をどうやってつくるのか」
なるほどね。その話にハマりそうなのが、クラブハウスの耐用年数です。ゴルフ場はバブル前の70~80年代に大量に造成されましたが、当時開業したゴルフ場は軒並みクラブハウスの建て替えや補修を迫られている。
「そうなるよね」
その際、高い会員権を売るために建てた豪華なハウスがお荷物になる。建て替えには3億~5億円は掛かるし、補修で大きな空間容積を維持すればクリーニングコストや人件費が負担になる。
「なるほど、なるほど」
ゴルフの大衆化を目指すなら、スタート小屋だけで十分だと。その判断に、経営者の思想なり哲学が求められる。
「だとすれば、ぼくの話にハマるじゃないですか(笑)。仮にそのゴルフ場が地域のカントリークラブを目指すなら、それは地域の共有財産であり、自分達のゴルフ場だという意識をまずはつくる。
つまりね、『おらが村のカントリークラブ』にするための意識の再設計をどうするのか、という話ですよ。
ゴルフは楽しいし、一人でもまわれるじゃないですか。クラブ2~3本持って朝の散歩みたいにプレーできれば気持ちいいし、なんていうかなあ、爽快だと感じることが生きる糧になる。その力は非常に大きいですよ」
それが「ゴルフの日常化」につながるわけですね。個人的な話をすれば、最近は6本でプレーしてるんですよ。
「オッ、いいですねえ~」
ドライバーに鉄は5、7、9番と52度。軽量バッグに入れて電車で行く、車中は読書。
「まさに図書館じゃないですか、さすがです(笑)。というのも、ゴルフの日常化には物理的な課題として持ち運びの手軽さがある。そこでね、9本でやる『ナインクラブス』っていうのを以前から構想してるんですよ。
コースをティーグラウンドとフェアウェイ、グリーン周りに3分割して、それぞれ3本という発想です。今のクラブはロフト3度ピッチでフローしますが、ぼくの考えでやると6~7度になる。
でも、長く持ったり短く持ったりで飛距離は変わるし、同じ9本でも距離が欲しいひと用の9本と、シュアなゴルフ用の9本とか、ニーズによって分ければいいでしょ。
片山さんの6本もステキですが、ぼくの9本は本気の9本でね、理想はPGAの一流プロ、たとえばライアン・ムーアみたいな選手が9本を自分で担いで堂々と戦い、優勝したらカッコいい」
「カッコいい」は大事な要件ですね。ひとの関心を集めるし、それで『日常のゴルフ』が市民権を得るかもしれない。
「おっしゃるとおりです。これまでのハーフセットみたいな感覚じゃなくて、本気も本気、トーナメントで勝てる9本ですよ。
製造や設計技術が進化して、それだけの性能を9本に持たせることができるようになった。プロは9本でいろんな球を打ち分けますが、一般向けはそれより許容性があって、アベレージプレーヤーでも距離を打ち分けられる性能を用意してあげる。
まあ、そんなことを考えて楽しんでいます(笑)」
つまり、ゴルフ産業の再興を思想的に考えるわけですね。
「思想というより、哲学に近い感じでしょうねぇ。ゴルフの在り方の問題や、自分の生活とゴルフとの距離の問題かな。
つまり施設面のハードを含めて、ゴルフという概念なりコンセプトをどうやって再デザインしていくのかという問題です。過去の継続や継承ではなく、新しいゴルフの哲学をどうやってつくるのか」
なるほどね。その話にハマりそうなのが、クラブハウスの耐用年数です。ゴルフ場はバブル前の70~80年代に大量に造成されましたが、当時開業したゴルフ場は軒並みクラブハウスの建て替えや補修を迫られている。
「そうなるよね」
その際、高い会員権を売るために建てた豪華なハウスがお荷物になる。建て替えには3億~5億円は掛かるし、補修で大きな空間容積を維持すればクリーニングコストや人件費が負担になる。
「なるほど、なるほど」
ゴルフの大衆化を目指すなら、スタート小屋だけで十分だと。その判断に、経営者の思想なり哲学が求められる。
「だとすれば、ぼくの話にハマるじゃないですか(笑)。仮にそのゴルフ場が地域のカントリークラブを目指すなら、それは地域の共有財産であり、自分達のゴルフ場だという意識をまずはつくる。
つまりね、『おらが村のカントリークラブ』にするための意識の再設計をどうするのか、という話ですよ。
ゴルフは楽しいし、一人でもまわれるじゃないですか。クラブ2~3本持って朝の散歩みたいにプレーできれば気持ちいいし、なんていうかなあ、爽快だと感じることが生きる糧になる。その力は非常に大きいですよ」
それが「ゴルフの日常化」につながるわけですね。個人的な話をすれば、最近は6本でプレーしてるんですよ。
「オッ、いいですねえ~」
ドライバーに鉄は5、7、9番と52度。軽量バッグに入れて電車で行く、車中は読書。
「まさに図書館じゃないですか、さすがです(笑)。というのも、ゴルフの日常化には物理的な課題として持ち運びの手軽さがある。そこでね、9本でやる『ナインクラブス』っていうのを以前から構想してるんですよ。
コースをティーグラウンドとフェアウェイ、グリーン周りに3分割して、それぞれ3本という発想です。今のクラブはロフト3度ピッチでフローしますが、ぼくの考えでやると6~7度になる。
でも、長く持ったり短く持ったりで飛距離は変わるし、同じ9本でも距離が欲しいひと用の9本と、シュアなゴルフ用の9本とか、ニーズによって分ければいいでしょ。
片山さんの6本もステキですが、ぼくの9本は本気の9本でね、理想はPGAの一流プロ、たとえばライアン・ムーアみたいな選手が9本を自分で担いで堂々と戦い、優勝したらカッコいい」
「カッコいい」は大事な要件ですね。ひとの関心を集めるし、それで『日常のゴルフ』が市民権を得るかもしれない。
「おっしゃるとおりです。これまでのハーフセットみたいな感覚じゃなくて、本気も本気、トーナメントで勝てる9本ですよ。
製造や設計技術が進化して、それだけの性能を9本に持たせることができるようになった。プロは9本でいろんな球を打ち分けますが、一般向けはそれより許容性があって、アベレージプレーヤーでも距離を打ち分けられる性能を用意してあげる。
まあ、そんなことを考えて楽しんでいます(笑)」
 十数年前、大沢商会の常務だった伊谷さんが面白い話をしてくれました。「日本は敗戦国だ。街頭テレビで力道山が外人レスラーをやっつけると狂喜した。つまり体力劣等民族だから、悲しいほど飛距離を欲しがるのだ」と。
「面白いねえ(笑)。それはひとつの考察としてとても面白い話だけど、日本のメーカーは『飛んで曲がらない』以外にゴルファーを振り向かせる言葉がないわけでしょ。その意味ではメーカーの発想力も問題ですね。
これに代わる言葉を探す中で、『オノフ』は20年前に『おとなの』とか『上質な』という言葉を使いましたが、それで若干、何かを言おうとしてるんだろうな、という雰囲気は感じてもらえたと思うんです」
「飛んで曲がらない」のアンチテーゼですね。別の言葉ではポスト・マテリアル、つまり「脱・物質主義」というか「脱・機能偏重主義」みたいなことになる。
「さらに別の言葉でいうと、サイコグラフィックになるわけです。つまり数値で全部表せる、置き換えられるモノではなく、もっと感覚的で気分や感性に依拠する世界ですね。
『飛んで曲がらない』は数値で表せる。そうではない価値観をずう~っと考えてきた中で『日常のゴルフ』はどうだろうと」
それは平易でいい言葉ですが、「飛んで曲がらない」と戦うにはパンチが弱いのかな。
「んー」
初代の『ゼクシオ』は広告で「美しく飛ばそう」というフレーズを使った。その後「空へ」とやりましたが、同時にテレビCMで「ゼクシオ・サウンド」を響かせた。
「ですよねえ。文字と音の両方で『飛び』の爽快感をイメージさせた。あの手法はとても素晴らしかったと思います。
あれから十数年経ってクラスターの細分化はあったけど、現実的には『飛び』にしか反応しない属性がマスですよね。
個人的には『飛び』に反応しない属性は3つぐらいあると思っていて、一番マイナーなのが自分でクラブを作って自分のゴルフの世界を楽しむタイプだと思う」
マニアックで、唯我独尊のタイプですね。あとのふたつは?
「わからない。ちょっと整理すると出てくると思うんだけど、たとえば片山さんみたいな6本のゴルフもそうかもしれない。極めてマイナーですけどね」
マーケッターが市場を分析するとき、マインドの切り分けでクラスター分類をするのが定番だけど、極めてマイナーな層はクラスターとして表出してこない。
「そうなんですが、そこに光を当てるのが大事というか」
そもそも『オノフ』はそこに光を当てるブランドとして20年前に登場した。初期の広告表現に白洲次郎の「Play Fast!」を使ったり、やたら高踏的で、高踏的にやると説教臭くなる。
「いやいやいやッ。仮に説教臭く聞こえたなら、それはぼくらの能力のなさなんでね(苦笑)」
早くまわれ、穴を埋めろ、ゴルフ場に来たときよりもキレイにして帰れとか。風紀委員みたいだった。
「あはははッ。そうですか」
ただまあ、思想的にやろうとすると、そうなりますね。同時に写真の表現にも力を入れて、スコットランドの荒涼たる大地をビジュアルに使った広告は良かったですね。
「ありがとうございます。スコットランドは二度撮影に行きましたが、あの土地は『オノフ』の聖地というか、ぼく自身、スコットランドのゴルフが大好きなんですよ。
その理由は日常に近いこともあるけれど、何よりも風景としてね、ゴルフコースが自然に寄り添っている。自然をねじ伏せたコースじゃなくて。そこが本当にいいんですよ」
大江さんはナチュラリストですか?
「そんなカッコいいもんじゃありませんが、単純にあの過酷な条件の中でやるのが面白いんです。ただね、大半のひとはその経験がないわけだから、それに近いことをリージョナリズムでやりたいと。
先ほどの話に戻りますが、軽いゴルフクラブのセットがある、出張に9本持って行って、時間を見つけてその土地のコースをふらりと訪ねる。それを『ナインクラブス』でやりたいんだと」
「出張ゴルフ」はイメージがわきますね。楽しいだろうなあ。
「それと、取ってつけた言い方ですが、14本が9本になればエコにもなるじゃないですか」
取ってつけたエコ話は大江さんらしくないというか、つまらないですね。エコはもっと、大真面目に語ってもらわないと。
「それはそうです(苦笑)」
十数年前、大沢商会の常務だった伊谷さんが面白い話をしてくれました。「日本は敗戦国だ。街頭テレビで力道山が外人レスラーをやっつけると狂喜した。つまり体力劣等民族だから、悲しいほど飛距離を欲しがるのだ」と。
「面白いねえ(笑)。それはひとつの考察としてとても面白い話だけど、日本のメーカーは『飛んで曲がらない』以外にゴルファーを振り向かせる言葉がないわけでしょ。その意味ではメーカーの発想力も問題ですね。
これに代わる言葉を探す中で、『オノフ』は20年前に『おとなの』とか『上質な』という言葉を使いましたが、それで若干、何かを言おうとしてるんだろうな、という雰囲気は感じてもらえたと思うんです」
「飛んで曲がらない」のアンチテーゼですね。別の言葉ではポスト・マテリアル、つまり「脱・物質主義」というか「脱・機能偏重主義」みたいなことになる。
「さらに別の言葉でいうと、サイコグラフィックになるわけです。つまり数値で全部表せる、置き換えられるモノではなく、もっと感覚的で気分や感性に依拠する世界ですね。
『飛んで曲がらない』は数値で表せる。そうではない価値観をずう~っと考えてきた中で『日常のゴルフ』はどうだろうと」
それは平易でいい言葉ですが、「飛んで曲がらない」と戦うにはパンチが弱いのかな。
「んー」
初代の『ゼクシオ』は広告で「美しく飛ばそう」というフレーズを使った。その後「空へ」とやりましたが、同時にテレビCMで「ゼクシオ・サウンド」を響かせた。
「ですよねえ。文字と音の両方で『飛び』の爽快感をイメージさせた。あの手法はとても素晴らしかったと思います。
あれから十数年経ってクラスターの細分化はあったけど、現実的には『飛び』にしか反応しない属性がマスですよね。
個人的には『飛び』に反応しない属性は3つぐらいあると思っていて、一番マイナーなのが自分でクラブを作って自分のゴルフの世界を楽しむタイプだと思う」
マニアックで、唯我独尊のタイプですね。あとのふたつは?
「わからない。ちょっと整理すると出てくると思うんだけど、たとえば片山さんみたいな6本のゴルフもそうかもしれない。極めてマイナーですけどね」
マーケッターが市場を分析するとき、マインドの切り分けでクラスター分類をするのが定番だけど、極めてマイナーな層はクラスターとして表出してこない。
「そうなんですが、そこに光を当てるのが大事というか」
そもそも『オノフ』はそこに光を当てるブランドとして20年前に登場した。初期の広告表現に白洲次郎の「Play Fast!」を使ったり、やたら高踏的で、高踏的にやると説教臭くなる。
「いやいやいやッ。仮に説教臭く聞こえたなら、それはぼくらの能力のなさなんでね(苦笑)」
早くまわれ、穴を埋めろ、ゴルフ場に来たときよりもキレイにして帰れとか。風紀委員みたいだった。
「あはははッ。そうですか」
ただまあ、思想的にやろうとすると、そうなりますね。同時に写真の表現にも力を入れて、スコットランドの荒涼たる大地をビジュアルに使った広告は良かったですね。
「ありがとうございます。スコットランドは二度撮影に行きましたが、あの土地は『オノフ』の聖地というか、ぼく自身、スコットランドのゴルフが大好きなんですよ。
その理由は日常に近いこともあるけれど、何よりも風景としてね、ゴルフコースが自然に寄り添っている。自然をねじ伏せたコースじゃなくて。そこが本当にいいんですよ」
大江さんはナチュラリストですか?
「そんなカッコいいもんじゃありませんが、単純にあの過酷な条件の中でやるのが面白いんです。ただね、大半のひとはその経験がないわけだから、それに近いことをリージョナリズムでやりたいと。
先ほどの話に戻りますが、軽いゴルフクラブのセットがある、出張に9本持って行って、時間を見つけてその土地のコースをふらりと訪ねる。それを『ナインクラブス』でやりたいんだと」
「出張ゴルフ」はイメージがわきますね。楽しいだろうなあ。
「それと、取ってつけた言い方ですが、14本が9本になればエコにもなるじゃないですか」
取ってつけたエコ話は大江さんらしくないというか、つまらないですね。エコはもっと、大真面目に語ってもらわないと。
「それはそうです(苦笑)」
 一連の話を聞いていると、武蔵野美大の学長の話を思い出します。「f分の1ゆらぎ」についての考察で、去年、GEWで書きました。
「あの記事、読みましたよ」
長澤学長いわく「数値化できる分野はAIがやってくれる。これから人間がやるのはそこじゃなくて『ゆらぎ』です」と。要するにf分の1の世界ですね。
「そう、まさにそこなんだッ」
川のせせらぎや、初夏のゴルフで微風に吹かれる涼感とか。
「そうそう、まさにそうですよ。先ほどサイコグラフィックの話をしましたが、『f分の1ゆらぎ』は数値化できない、人間の感性に訴え掛けるモノとして大きな研究課題なんですよ。
たとえばモンゴルの原住民がヒトに伝える音の出し方があるんですね。歌でもなく、口笛でもなく、『ホエ~~』という感じの音ですが、ある領域の周波数を発するとサウンドの大きさではなく遠くまで届くんです。
でね、それに近い声が荒井由実だと言われています。なぜ彼女の声がこれだけ長い間支持されるのか、それは声の質によるんだという説があるんですよ。
f分の1はそれと非常に近くて、川のせせらぎや風のそよぎ、扇風機もそれと似たようなことをやってますが、自然の風とはどうしても違うわけで」
違いますね。断続的に強弱をつけたりするけれど、自然の風みたいに不定型というか、不揃いにならない。
「それをフラクタルと言うんですが、いわゆる蝶々が飛ぶ軌跡のことなんです。面白いのは、これをニューノーマルの概念に取り入れると『生活のゆらぎ』になるんですよ。
さらにこれをリージョナリズムや『日常のゴルフ』につなげると、なんかこう、ふわっとしたゆとりになる。同じゴルフでも帰りの渋滞を気にしながらと、生活のゆらぎとして溶け込んでいるゴルフではまったく違うじゃないですか。
その空気感をね、どのような言葉で表せばいいんだろう。一緒に考えてくださいよ」
昔、広告表現で「ファジー」(曖昧)という言葉が流行ったけど「ゆらぎ」はそれとも違いますね。この感覚を言語化するのは難しいというか、言語は語釈、つまり本質的に意味づけされるわけで、意味じゃなく感じるのがゆらぎだから。
「言えるよねぇ。リンゴの味を正確に言葉に置き換えるのが難しいのと同じで(苦笑)」
歯応えや音、風味も味になりますから。まあ、言語は機能的だから、そう考えると「ゴルフの魅力」も言語化された空疎感がありますよね。
「ん、どういうこと?」
ゴルフは自然と向き合うスポーツだと言われると、山登りがあると思ってしまうし、健康にいいと言われると、歩けばいいと。そもそもゴルフを「目的化」して「価値化」することに違和感があって、大体の目的はほかの行為で代替えできる。
「なるほどねえ(笑)。そこを整理したいけど、難しいよねえ。そよ風のゆらぎの気持ち良さとか、大きな自然の中で小さな小さな人間が感じることって沢山あるじゃないですか。
感じるというのは、生きてきた時間の中に記憶があって、それに反応してるわけですよね。この流れで『ゴルフの魅力』を改めて考えると、さっきの『飛んで曲がらない』を打倒しなければいけませんが、実はこの言葉、意外と凄いのかもしれません。
だって小さな白球に思いを込めて、ボールが自分に成り代わって飛翔するわけだから、その記憶の反応は強く残るじゃないですか」
その反面、思いを込めた1打が逃げ惑うヘビのように情けなく草むらを走るとか。
「あるよねえ(笑)。そう考えると『飛んで曲がらない』は強烈なフレーズなんだろうなぁ。ただね、そこを越えないと新しい価値観を提示できないような気がしていて『リージョン』はどう?」
んー。地域主義?
「主義って言葉は使いたくないですね。もっとふわっとした『おらが村の』みたいな感じで」
んー。宿題にしてください。
「いずれにせよ、今回のコロナで改めて思うのは、結局のところこれからは過去の知見や流儀は通用しないし、度胸を据えてやるしかないんですよ。
ぼくね、ゴルフのニューノーマル本気で考えてますよ。限界集落や休耕地、そこに魅力的なコミュニティをつくって都会のホストを呼び戻す。9本のクラブで『日常のゴルフ』を溶け込ませる。
それを地域ぐるみで、ってことを本気でやりたいと思ってます」
[surfing_other_article id=55654]
一連の話を聞いていると、武蔵野美大の学長の話を思い出します。「f分の1ゆらぎ」についての考察で、去年、GEWで書きました。
「あの記事、読みましたよ」
長澤学長いわく「数値化できる分野はAIがやってくれる。これから人間がやるのはそこじゃなくて『ゆらぎ』です」と。要するにf分の1の世界ですね。
「そう、まさにそこなんだッ」
川のせせらぎや、初夏のゴルフで微風に吹かれる涼感とか。
「そうそう、まさにそうですよ。先ほどサイコグラフィックの話をしましたが、『f分の1ゆらぎ』は数値化できない、人間の感性に訴え掛けるモノとして大きな研究課題なんですよ。
たとえばモンゴルの原住民がヒトに伝える音の出し方があるんですね。歌でもなく、口笛でもなく、『ホエ~~』という感じの音ですが、ある領域の周波数を発するとサウンドの大きさではなく遠くまで届くんです。
でね、それに近い声が荒井由実だと言われています。なぜ彼女の声がこれだけ長い間支持されるのか、それは声の質によるんだという説があるんですよ。
f分の1はそれと非常に近くて、川のせせらぎや風のそよぎ、扇風機もそれと似たようなことをやってますが、自然の風とはどうしても違うわけで」
違いますね。断続的に強弱をつけたりするけれど、自然の風みたいに不定型というか、不揃いにならない。
「それをフラクタルと言うんですが、いわゆる蝶々が飛ぶ軌跡のことなんです。面白いのは、これをニューノーマルの概念に取り入れると『生活のゆらぎ』になるんですよ。
さらにこれをリージョナリズムや『日常のゴルフ』につなげると、なんかこう、ふわっとしたゆとりになる。同じゴルフでも帰りの渋滞を気にしながらと、生活のゆらぎとして溶け込んでいるゴルフではまったく違うじゃないですか。
その空気感をね、どのような言葉で表せばいいんだろう。一緒に考えてくださいよ」
昔、広告表現で「ファジー」(曖昧)という言葉が流行ったけど「ゆらぎ」はそれとも違いますね。この感覚を言語化するのは難しいというか、言語は語釈、つまり本質的に意味づけされるわけで、意味じゃなく感じるのがゆらぎだから。
「言えるよねぇ。リンゴの味を正確に言葉に置き換えるのが難しいのと同じで(苦笑)」
歯応えや音、風味も味になりますから。まあ、言語は機能的だから、そう考えると「ゴルフの魅力」も言語化された空疎感がありますよね。
「ん、どういうこと?」
ゴルフは自然と向き合うスポーツだと言われると、山登りがあると思ってしまうし、健康にいいと言われると、歩けばいいと。そもそもゴルフを「目的化」して「価値化」することに違和感があって、大体の目的はほかの行為で代替えできる。
「なるほどねえ(笑)。そこを整理したいけど、難しいよねえ。そよ風のゆらぎの気持ち良さとか、大きな自然の中で小さな小さな人間が感じることって沢山あるじゃないですか。
感じるというのは、生きてきた時間の中に記憶があって、それに反応してるわけですよね。この流れで『ゴルフの魅力』を改めて考えると、さっきの『飛んで曲がらない』を打倒しなければいけませんが、実はこの言葉、意外と凄いのかもしれません。
だって小さな白球に思いを込めて、ボールが自分に成り代わって飛翔するわけだから、その記憶の反応は強く残るじゃないですか」
その反面、思いを込めた1打が逃げ惑うヘビのように情けなく草むらを走るとか。
「あるよねえ(笑)。そう考えると『飛んで曲がらない』は強烈なフレーズなんだろうなぁ。ただね、そこを越えないと新しい価値観を提示できないような気がしていて『リージョン』はどう?」
んー。地域主義?
「主義って言葉は使いたくないですね。もっとふわっとした『おらが村の』みたいな感じで」
んー。宿題にしてください。
「いずれにせよ、今回のコロナで改めて思うのは、結局のところこれからは過去の知見や流儀は通用しないし、度胸を据えてやるしかないんですよ。
ぼくね、ゴルフのニューノーマル本気で考えてますよ。限界集落や休耕地、そこに魅力的なコミュニティをつくって都会のホストを呼び戻す。9本のクラブで『日常のゴルフ』を溶け込ませる。
それを地域ぐるみで、ってことを本気でやりたいと思ってます」
[surfing_other_article id=55654]