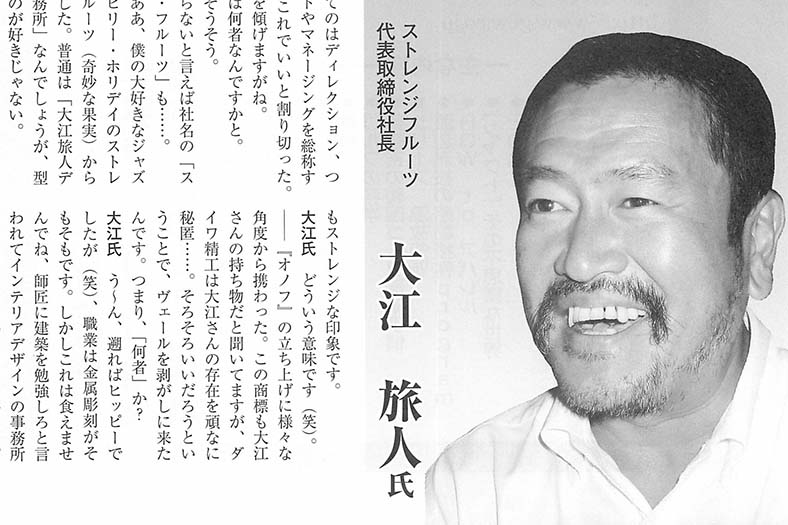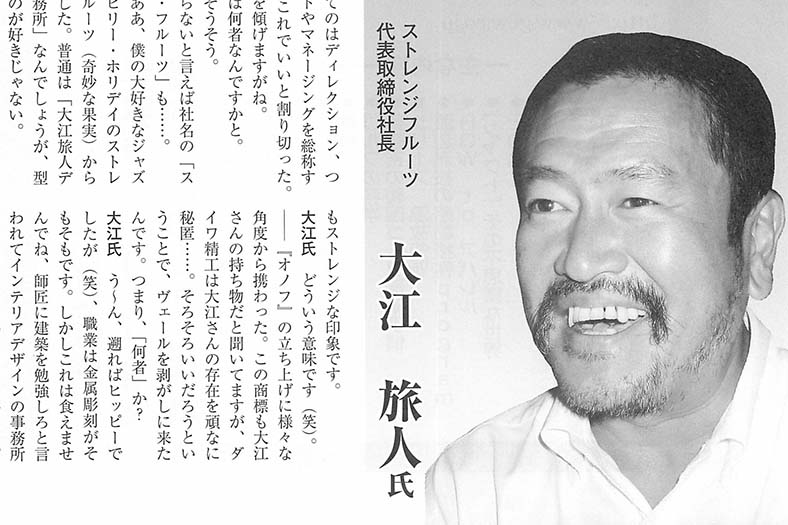「GEW」2003年12月号を振り返る オノフが主張した「上質な大人」向けのクラブはなぜ売れた?
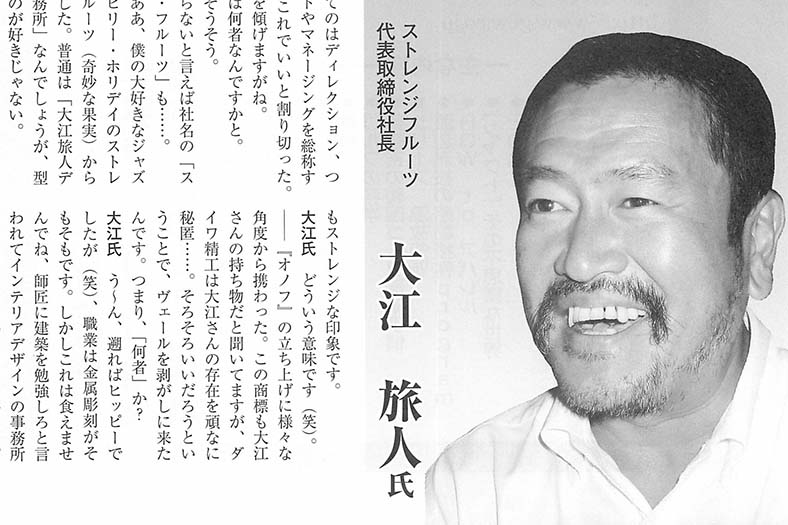
[archives key="蔵出しインタビュー" order="99" previousWpId="" nextWpId="" body="今も昔も、ゴルフクラブの売り文句は「飛んで曲がらない」である。
それじゃつまらない、ということで、クラブのブランディングに「思想」を持ち込んだのが『オノフ』だった。そしてそれは、大いなる危機感の産物でもあった。
釣り具大手のダイワ精工(現グローブライド)は1992年の最盛期、ゴルフクラブだけで150億円を販売した。それが『オノフ』を投入する直前の2001年には25億円。6分の1の惨状である。
当時の小島忠雄社長はGEWの取材に対して「オノフに成果が見えなかったら、ゴルフ事業の撤退もありました」と述懐している。バブル景気の崩壊は、容赦なく同社に襲いかかった。
そのゴルフ事業の建て直しを、外部の人材に依頼した。ストレンジ・フルーツ代表の大江旅人氏である。
クラブ市場に新風を吹き込み、窮状を脱した実績から、大江氏に注目が集まった。「メディアには出たくない」という同氏に「ブランドと思想」を多角的に尋ねた。なお、文中の数字、社名、役職その他は取材当時のままであることを留意願いたい。"][/archives]
[back_number key="200312"][/back_number]
どういう意味ですか!
大江さんのこの名刺、非常にシンプルですよね。表が「大江旅人」。これだけで、社名も役職も住所もない。裏に英語で「ディレクター」とありますが、社長ですよね?
「社長です(苦笑)」
これじゃ何だかわからない。
「まあ、そうでしょうねえ。ぼくなりにこだわった表現でしてね、名刺に『代表取締役』とか刷り込むと字ヅラが美しくありませんし、ニュアンスも好きじゃないんですよ。
『ディレクター』ってのはディレクション、つまりアートやマネージングを総称するから、これでいいと割り切りました。銀行は首をかしげますがね」
オタクは何者なんですかと。
「そうそう(笑)」
わからないと言えば社名の『ストレンジ・フルーツ』も……。
「ああ、ぼくの大好きなジャズでしてね、ビリー・ホリデイのストレンジ・フルーツ(奇妙な果実)から拝借したんですよ。ふつうは『大江旅人デザイン事務所』なんでしょうが、型にハメるのが好きじゃないし」
余計なことを言えば、大江さんもストレンジな印象ですよね。
「どういう意味です(笑)」
『オノフ』の立ち上げに様々な角度から携わっている。まあ、ダイワ精工は大江さんを表に出したくないんでしょうが、そろそろいいだろうということで、ヴェールを剥がしに来たんです。つまり、「何者」か?
「ぼくね、さかのぼればヒッピーだったんですが(笑)、職業は金属彫刻がそもそもです。
だけどこれは食えませんでね、師匠に建築を勉強しろと言われてインテリアデザインの事務所に入ったんです。昭和50年だったかなあ。
ちょうどその頃ある出版社が、アメリカのライフスタイルを紹介するカタログを作ろうとなりまして、インテリアディレクターとして参画したわけですが、それがグラフィックデザンとの出会いです。
昭和51年にストレンジ・フルーツを設立して、いろんなプロデュースをやりましたよ。
たとえば12年ほど前、『すかいら-く』の事業開発に『オ-プンセサミ』というのがありましてね、何かといえばデリカやテイクウトヘの進出です。
将来は外食から内食(家庭)になる、これを先取りしようという試みで、」
どうでした?
「早すぎた(笑)。最近はホテルのレストランが宅配に力を入れてますが、あれの走りだったわけですよ。
面白いのはカリスマ主婦をプロデュースして、食器やエプロン、本なんかを総合企画したこともあります。出版物は30万部、百貨店のイベントでは長蛇の列ができました」
そういえば、インサイダー取り引きで起訴されたアメリカの主婦もいましたね。
「そう、マーサ・スチュワートね。彼女はカリスマ主婦で大成功して、実業家になっちゃった。ぼくがやったのは、あれの日本版なんですよ」
ヒッピーとヤッピー
まあ、いろいろなさってるわけですが、大江さんの職域を定義するとどうなりますか。デザイナー、あるいはプロデューサー?
「ぼく自身は、広義ではマーケッターだと考えてます。デザインやプロデュースはマーケティングの上に立たないとディレクションが取りにくい。これを掘り下げると思想や哲学も必要で、こういった素養を持ちながら消費者のライフスタイルにアプローチする。という定義でしょうな」
なるほど。そういった思想の原風景はどこですか。たとえば昭和50年にアメリカのライフスタイル・カタログに関わったという話ですが、70年代のアメリカはいろんな意味で強烈ですよね。
「言えますねえ。あの頃のアメリカにはかなり影響を受けましたし、一方でアメリカのカルチャーやライフスタイルがどこまで日本に理解されているのか、疑問に思うことも多かったんです。
まずね、情報源が少ないんですよ。JALの機内誌やそれに類する旅行誌が、ラスベガスやヨセミテ公園をステレオタイプ(紋切り型)に取り上げる程度で……。
ベトナム反戦に代表されるヒッピーのカウンターカルチャーも台頭したけれど、一般的にはアメリカのライフスタイルを紹介するまでには至らなかった。そんな時代です」
アメリカの思想が多元的だと思うのは、ヒッピーの対立形態としてヤッピーも現れた。これ、ベビーブーマーで都市型高収入の若者集団ですが、価値観がゴロリと変わってしまう。
「いやあ片山さん、ヤッピーを対立に置くのはちょっと違うでしょう。たしかに表現は対極なんだけど、両者に共通するのは反体制の気概でね、それがビジネス手法にも表われている。ぼくはそう思うんです。
代表的なのがビル・ゲイツだし、ファッションの世界ではヒッピーのボスが『エスプリ』をつくった。ぼくが尊敬する『ベネトン』のクリエイティブ・ディレクターにトスカニという男がいるんだけど、彼らに一致しているのは『新境地を拓く』という強烈な信念なんですよ。
だからブランドには思想が必要だし、思想なきブランドは、」
無意味だと。
「そこまで言うつもりはないんだが、存在として非常に軽いわけですよ。ヤッピーはそこを追求したし、ぼくのコンセプトも同じです」
ぼくの思想はスローフードの流儀
大江さんの思想は何ですか?
「そうねえ、端的に言えば『スローフード』。これは明快な思想です。
そもそもはイタリアの片田舎(ブラ)で村興しというか、地元産品を訴求する活動にはじまったもので、スローフード協会の代表が言い出した言葉なんですね。
チーズや葡萄、ハムとかを伝統に基づいてきちんと作る。アンチ・ファストフードの急先鋒として台頭した」
パルマのハムが有名ですね。熟成具合を調べるのに馬の骨を削った針を刺して、職人がその匂いで判断する。
「そうそう。だから職人には経験と技術が必要で、資格への評価もしっかりしている。
背景には伝統に対する尊厳と、これを敷桁していく思想……、つまりオートメーションへのアンチテーゼが込められているんですね。
科学の進歩がヒューマニズムの領域を侵す例は枚挙に暇がないんだけど、遺伝子組み替え食品への対立として、あるいは生き方としてもスローライフということで、この活動を始めた人はかなりな思想家のはずですし、根底に哲学を感じるよね」
そういった思想を集約するのがブランドですか。
「ですね。ブランドをぼくなりに定義すれば、『消費者とメーカーを結ぶ精神的な絆』となる。敢えて苦言を呈すれば、日本のマーケティングはクラスター(葡萄の房、消費者群)の組み合わせが大半で、精神性が存在しない。まずいというか、豊かではありませんよね」
ブランドの語源は「焼印」ですね。西部劇の牧場で牛の尻にジュッとやる。そもそも精神性とは無縁だった。
「おっしゃるとおりです。だから最初は『識別記号』でしかなかったし、牛泥棒から財産を守る『所有権』の意味合いが強いため、マーチャンダイジングではあり得なかった。
だけど二人の牛飼いがいる。Aさんの牛は放牧で健康的に飼育するが、Bさんのは狭い牛舎に詰め込んで、やたら不健康なわけですよ。同じ牛だけど全然ちがう。
今、語られるブランドは、このレベルでの選択肢ですよ。しかし本来力のあるブランドはね、ここに精神性を持ち込んで、サプライヤーの思いを強烈に主張する作業じゃないですか」
やわな精神じゃ伝わらない
すると「受け手」が問題になりますね。そういった思想に共鳴するインテリジェンス、要するに教養がないと思想家がいくら頑張っても虚しいだけだし。だいたい、固有の思想がライフスタイルに馴染むんですか?
「そのテーマで『スローフード』を拡大解釈するならば、マーケティングの磁場になり得ると思うんです。このベクトルに来るライフスタイルはかつてのヒッピーやベトナム反戦を歌ったフラワーチルドレンと同じだろうと」
はあ……? 全然わからない。
「つまりね、反体制を通すには流されない自我が前提で、そういった価値観への認識です。ここにメーカーと消費者の関係を乗せると、『売れる物作り』の発想ではなく、『自信ある物作り』のほうが結局は強い。
ブランドが『精神的な絆』というのはまさにこの意味で、もちろん業種によっては違うんだけど、ぼくがやってるゴルフ、時計、ジャズってのはまさしくこの領域に入っている。サプライヤーがね、やわな精神じゃ伝わりませんよッ」
メーカーが特定の層を狙った場合、「迎合」ではなく「牽引」だと。リードする力が思想なんだと……。
ただ、一方で『ユニクロ』の存在がありますね。あれは無思想ゆえの大衆迎合、つまりSPAを駆使したマスマーケティングの定番じゃないんですか?
「とんでもないッ。『ユニクロ』の存在を単にシステムで語る人が多いんだけど、実はあれこそ反体制の真髄ですよ。と、ぼくは思う。
先ほどヤッピー流の起業はチャレンジングな変革で、それは反体制思想に基づくと言いましたが、『ユニクロ』も全く同じなんですね。つまりカジュアルファッションの世界をあれだけダイナミックに変革した実績は、まさに精神性の発揮だし、少なくともぼくの中では存在感がもの凄くある」
どんな存在感?
「ライフスタイルを創った。この一点に尽きるかなあ。
要するに、ぼくなりに将来の魅力的なライフスタイルを想像するとね、それは『ユニクロ』と『エルメス』を上手く着こなす光景なんですよ」
『エルメス』のジャケットに『ユニクロ』のパンツを自在に着る。
「そうそう」
全身高級ブランドってのはブランド依存だし、精神性の貧困に見える。ブランドで自分の承認欲求を満たすというか。
「だから『ユニクロ」の功績は、一方の選択肢を生活者にハメ込んだ。これが凄いんだな。
以前『エルメス』の本店に行きましたら、日本人がずら~っと並んでて、店もそれ用の商品をワゴンに積んで待ち構えてる。まあ、それからみっともない光景が始まるわけ(苦笑)。
これまでのぼくはそれを見て、実に美しくない振る舞いだと、ちょっとした嫌悪を覚えていたんですよ。だけど最近はちょっと違うんです。
ああいった日本人の光景は、ライフスタイルが成熟する前の過渡期において必然なんじゃないだろうか。自我が確立してないから、無闇にブランドをありがたがる。
だけどブランドに精神的な紐帯を求める消費行動は、いずれポピュラーになるはずだし、それを動かすのが我々の仕事でもあるんです」
なるほど。知恵熱みたいなもんで、一度かからないと次のステップに移れない。
「そうそう、だと思いますね」
ゴルフ記者が気づいてくれない
先日『ニューオノフ』の記者発表を都内のホテルでやりました。いろんなこだわりが仕組まれていて、まず、クッキーがやたら美味かった。
「あれはね、ホテルの厨房で当日の朝焼いたんですよ。美味かったでしょ?(笑)」
飲み物はペットボトルの水でしたが、あれ、ハイランド地方の水をわざわざ取り寄せたそうですね。
「そう、ハイランド。ゴルフ発祥の地というね、とても由緒ある水でした」
もの凄~くこだわった。
「なんですが、悲しいのは、クッキーに手をつけなかった人が大半で、記者発表が終わったあと無造作に残されていたんです。
ハイランドの水にしたってですよ、あれ見てニヤリとした記者がいなかった………」
一方通行で終わってしまった。
「うん」
まあ、あの日の陰の主役はクッキーと水で、もの凄く思想を込めたわけですが、結果的にすべったわけですね。つまり、観念主義ってのは理解させるのに骨が折れる。
「折れますねえ(苦笑)。そもそも『オノフ』というブランドは『高速道路を路肩走行しない人』が対象で、極めて強い観念主義に始まっているんですよ。
『オノフ』はゴルフの魂を発信する。ゴルフの魂は『明るく楽しい』に尽きますが、自律心や公正の理念を含んでいます。だから『オノフ』は美しい振る舞いということが、BI(ブランド・アイデンティティ)の根底にあるわけですよ。
おっしゃるように観念と経済の両立は容易じゃない。だけどブランドは思想抜きには語れないんだと頑張って前提を立てて、押し通すしかないんです。
ほかのナショナルブランドが入れない領域で、ワンブランド50億……。これぐらいの売り上げで健康的な利益をつくるのが『オノフ』の使命だと考えますし、シェアを狙うブランドでもありません。やるんなら別に『カローラ』を作ればいいんですよ」
カエルを振り回した
だから去年のデビューはやけに高踏的だった。「白洲次郎」の書物からコピーを抜いたり「プレイ・ファースト」や「目土袋」をアピールしたり。見方によっては説教くさい。
「あのね、基本的にはクラスマーケティングなんですよ。日本の場合、特にスポーツ業界がクラスターマーケティングをやろうとすると『可処分所得』や『年齢軸』で括ったり、」
ゴルフクラブの場合は「飛んで曲がらない」を連呼して、可処分所得、ヘッドスピード、ゴルフ歴と、平面的に切り分けていく。
「そんな類型になるんですが、『思想』でクラスマーケをやる場合は、最初にガッチリしたほうがいいんです。多少説教くさかったとしても、理解されるプロセスでやり方を変えればいいですから」
ダイワ精工はそれを受け入れました?
「はい。新ブランドが失敗すれば、ゴルフ事業撤退という空気もありましたしね。
ダイワさんが準備したネーミングは『レッドゾーン』とかでしたが、」
如何にも飛んで曲がらない系の名前ですね。
「そう。これじゃブランドはつくれない、思想が入らないわけですよ。ですからその点は強く主張しましたね。
ただ、技術系の会社らしい潔さというか、硬派な印象を持ちました。一度決めたら迷わない、とことん行こうってな割り切りで」
そのへんの純朴さは、理系の学生的ですね。黒縁眼鏡かけて、真面目で、納得すると一途に惚れこんじゃう。
「かもしれない(笑)。だからこっちも責任感じちゃって、コケたらどうしよう。まあ、技術のダイワに狂いはないから、機能でそこそこ行けるだろうと、それが救いの面もありましたよね、正直に言えば……」
文系がコケたら理系が助ける。そのあたりは信頼感として、いいバランスですね。
「だと思います」
一連の広告ビジュアルで好きなのは、アイアンヘッドに蛙が乗ってるやつです。ぬらっとした柔らかさと金属の冷たい光沢が対照的で、なんかこう、命の儚さを感じさせる。蛙がおとなしく乗ってますが、あれは接着剤でつけたんですか?
「アハハハ、違います。取り敢えずゴルフ場に行ったら雨蛙がいた。捕まえてぐるぐる回したら酔っ払いみたいになりましてね、それをちょこんと置いたんです。
素材はロケ地で探すんですよ。カメラマンはドキュメントの専門家で、蟻はどうだ、ミミズじゃきついとか、いろいろやって……(笑)。
スローライフは本物志向、ヘンに妥協しない信念です。だから表現も自然との融合を大事にしたい、そこから連想するものを大切にしたいと思ってます」
[surfing_other_article id=63729][/surfing_other_article]
[surfing_other_article id=55654][/surfing_other_article]