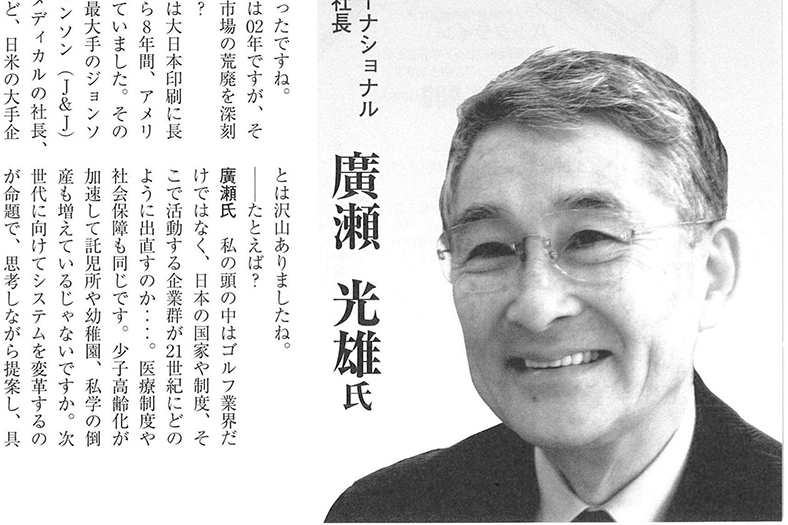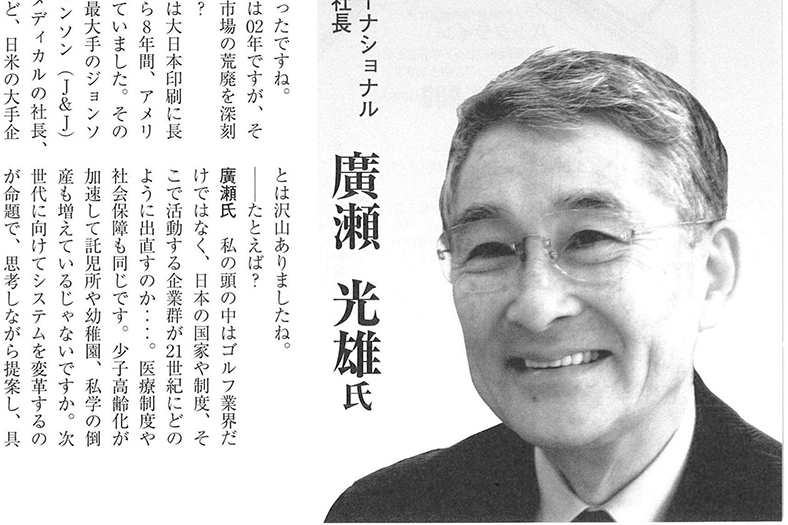「GEW」2006年6月号を振り返る PGM初代トップ廣瀬会長「浪花節じゃ経営はできない」
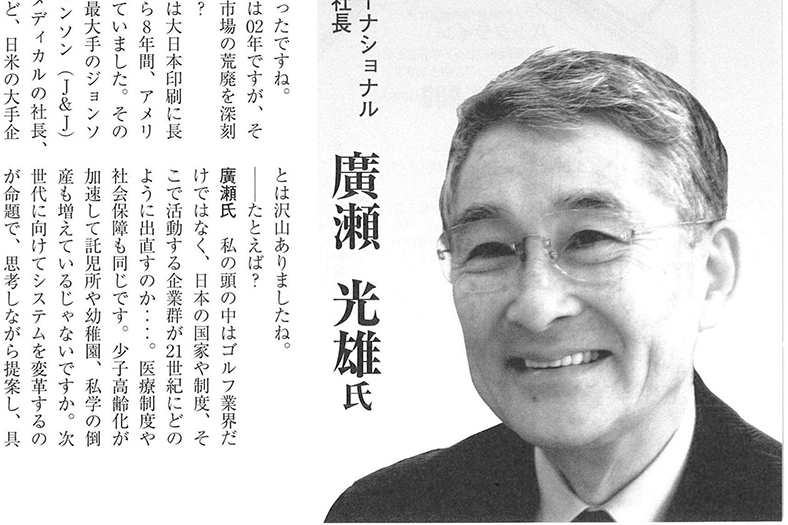
[archives key="蔵出しインタビュー" order="128" previousWpId="" nextWpId="" body="パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングスという、やたら長い社名だった。現パシフィックゴルフマネージメント(PGM)のことである。
初代の代表取締役会長兼社長が廣瀬光雄氏だった。
アコーディア・ゴルフがゴールドマン・サックス、PGMがローンスターと、共に外資系ファンドを創業時の母体とした。バブル崩壊で経営難に陥ったゴルフ場を買収して、再建、上場の流れで利益をあげるビジネスモデル。ゴルフ場を安く買って再生し、莫大な「売却益」を得ることから「ハゲタカ・ファンド」と揶揄された。
PGMはホテル・ゴルフ場経営の「地産」が最初の買収案件となり、以後、アコーディアと張り合う形で系列コースを増やしていった。
当時、廣瀬会長への取材テーマは、白旗をあげたワンマン社長たちの負の遺産を、どのように整理し、付加価値をつけていくのか?そのあたりを尋ねている。
取材時期はリーマンショックの2年前、ハニカミ王子が登場する前年の2006年だった。なお、文中の数字、役職、企業名その他は当時のままであることを留意願いたい。"][/archives]
[back_number key="200606"][/back_number]
ゴルフ界の問題は日本の問題と同じ
御社は創業わずか5年で上場しました。当初からそこを狙っていたわけでしょうが、そもそもPGMとはどんな会社なのか? そのあたりからお願いします。
「わかりました。まず、当社の創業時はゴルフ場の倒産ラッシュがありましてね、この傾向は会社が立ち上がる前から顕著でしたし、わたし自身、7つの会員権を持っていましたが、そのうち4つが倒産ですよ(苦笑)。
一人のゴルファーとしても何とかならないかと……。そんなことを思っていた矢先、PGMから『経営をやってもらえないか』と打診を受けたのです」
会長への就任は2002年ですが、それ以前からゴルフ市場の荒廃を深刻に受け止めていたわけですか?
「そうですね。わたしの経歴を簡単に話しますと、大日本印刷に長らく勤めまして、1979年から8年間、アメリカ法人の社長をしていました。その後ヘルスケア業界最大手のジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)に移って、J&Jメディカルの社長や日本法人の社長など、日米の大手企業で様々な経験を積んだわけです。
PGMからの誘いはJ&Jを辞めてコンサルティング業をしていた頃ですが、そういった観点から思うことは沢山あったんですよ」
たとえば?
「わたしの頭の中はゴルフ業界だけではなく、日本の国家や制度、そこで活動する企業群が21世紀にどのように出直すのか……。そんなことを常に考えているんですね。
医療制度や社会保障も同じです。少子高齢化が加速して、託児所や幼稚園、私学の倒産も増えているじゃないですか。次世代に向けてシステムを変革するのがこの国の大命題になってくる。思考しながら提案し、具体的な手段を講じていく。一連のことを手掛けるには、マーケティングの発想が不可欠です」
なるほど。それらはゴルフ業界の課題とも通底しているわけですね。
「そうです。日本では93%のゴルフ場が赤字でした。ゴルフというスポーツのポテンシャルは変わらないのに、周辺環境が変化したからです。
社用ゴルフの激減が卑近な例ですが、プレーに対するウィシュ(願望)は同じなのに、それを妨げる障壁がある。つまりゴルフ業界が抱える問題は、学校や病院の問題と同じなんですよ。ゴルフ界が抱える問題は、ゴルフ界に限ったものではありません」
浪花節の経営じゃダメですよ
つまり「変革」が急務だと。変革をする際に、変革の軸を刺すことが大事ですね。その軸を市場のどこに刺すんですか?
「そうですねえ。日米の大手企業に勤めて、さらにコンサルティング会社を経営した経験で思うのは、『文化の違い』に尽きるでしょうね。
要するに、変革は文化の溝を認識して、ブリッジング(架橋)をすることです。谷を埋める作業ではなく、橋を架けるコンセプトで、互いの強みを活かしていく。これによって新しい方向性を創造することが『軸』になると考えています。
で、そのことを深く考えられる人が日本に少ないのは、日米で大手企業の経営を体験した人が少ないからなんですよ。
自分をPRするわけじゃありませんが(笑)、わたしはコンサルティングでもトヨタ、日産、味の素など、グローバル企業を手掛けてきました。そういった目線で考えたとき、PGMもわたしが描くストーリーに乗っていると判断したし、上手く舵をとれば今のゴルフ市場の在り方を変えられる。まあ、そんなふうに考えたわけです」
観念論としてはわかりますが、具体的にはピンときません。経営破綻に陥ったゴルフ場を、今のストーリーでどのように再建するわけですか?
「わたしはね、学者でも評論家でもメディアでもなく、経営者なんですよ。その視点で日本の現状を見た場合、ふたつのグループに大別できると思うんですね。
ひとつは『今のままでもなんとかなるだろう』と考える既存勢力、もうひとつは『ダメだからイチからやり直そう』と考える勢力です。わたしはまず、後者の立場をとりますが、なぜならファンダメンタルのシフトが要求される現代では、一度ゼロにリセットしたほうが合理的で、そのことはダイエーとマイカルの再建にも顕著に表れています」
ボロ家を増改築するよりも、一度更地にして建て直した方が効率的。
「という話です。両社とも流通グループの雄として成長してきたわけですが、市場の変化に対応できず、結局は苦戦しましたね。問題はここからです。
マイカルのスポンサーとなったジャスコ(現イオングループ)の場合、支援はするけど『その前に法的整理をすべきだ』と主張して、一度潰しているんですよ。
ところがダイエーは潰さない方向でスキームを組んで、銀行もその流れで協力したじゃないですか。ゼロにしたほうが早いのに、日本的な情緒を優先して、未だに試行錯誤を続けています。実はね、それがコンフォタブル(心地良い)なわけですよ」
つまり、再建過程の努力自体が浪花節というか、悲運に酔える?
「そうそう、まったくそのとおりです(笑)。ビジネスはね、浪花節的な感情を含めて、気持ち良さを求めるものではありませんよ。
そりゃ、潰れればいろんなバッシングを受けますが、純粋な意味での経営は日本の社会性やシキタリと切り離して考えるべきであって、先ほど申し上げた『文化の違い』はそのことを指しているんです」
非情ですねえ。
「日本人が言うと『非情』なんだけど、ピーター・ドラッガー(米経営学者)は『再生の早道を考えるのが大切だ、再建が成功すれば雇用も生まれるじゃないか』と主張しています。これが文化の違いなんですよ」
「ハゲタカ」には異論あり
そのような思考がPGMの経営に反映されているわけですか? 瀕死のゴルフ場を虎視眈々と狙っていることから「ハゲタカ」とも呼ばれてますが。
「あのね、ぼくは『ハゲタカ』と呼ばれることには異論があるんですよ。なぜなら、うちはアメリカ流のバッサリではなく、日米の中間手法をとっているからです。
ただし、コース買収のストラテジー(戦略)は例外なく倒産企業に絞り込む。法的整理をされてないゴルフ場は絶対に買わないし、その点はイオンと同じスタイルかな。
なかには整理前に『買ってくれ』というコースもありましたが、引き受けませんでした。
まずは一度、きちんと潰れることです。倒産は裁判所が決めるから、その過程でうちは一切絡みません。裁判所はゴルフ場を持っていても仕方ないから、入札になる。入札はガラス張りだから談合もない。非常にスッキリしてるじゃないですか」
そうですね、買収に至る諸々の雑事が一切ないから非常にスッキリしています。で、再建側の人間として、破綻コースに共通する問題点は見えますか?
「見えますねぇ。裁判所は民事再生会社のスポンサーを募り、新たな引き受け先が事業化管財人を出しますが、わたし自身、エスティティ開発や地産では管財人を務めました。
そのような経緯から思うのは、破綻コースの最大の穴は前経営者の責任ですよ。会員から集めた預託金を、勝手に株や土地に投資したじゃないですか。
本来、預託金は預かり金だからきちんと経理処理をすべきだし、そこになければいけない資産なのに、多くの経営者は勝手に流用したわけですよ。
これ、商法違反じゃないですか。アメリカの経営者なら間違いなく逮捕されますが、日本はそれをやりません。地産のときも前経営者は脱税容疑だったでしょ。つまり日本そのものが間違っているんですよ。
にもかかわらず『ハゲタカ』という言葉を我々に向ける。むしろどちらが『ハゲタカ』なの……? わたしはそう問いたいですよ。
それと、破綻コースに総じて言えるのは集中力の欠如もありますね。地産の場合は29のホテルがあって、いずれも赤字に苦しんでいました。同じことは西武にも言えますが、ゴルフ以外の事業にも投資していたのでゴルフ事業が散漫になったわけです」
要するに片手間だった?
「そう。これじゃきちんとした経営は期待できませんよ」
この仕事は「不良債権買取再生業」
経営で大事なのは集中力だと。すると、PGMの集中力はどの方向に向けて発揮するんですか?
「うちは現在18ホール換算で118コースを運営しておりますが、これをもっと増やしたいと考えていて、すなわち集中力は『数』ですよ。集中力は当面、チェーンメリットの追求に発揮する方針です。
我々の仕事は経営的に『不良債権買取再生業』だと思うんですね。だって、買収コースの100%が倒産企業じゃないですか。買収額は表面的に10億〜20億円なんですが、個々に抱える不良資産は少なくとも50億円、多いところでは200億円に達するものもあるんですよ」
とはいえ、負債をすべて継承するわけじゃないですよね。
「そうですが、だとしても入札は一発勝負で、再生に失敗したら不良資産だけが残るじゃないですか。
再生に成功を収めるためには『ゴルフコース・マネジメント・ビジネス』に特化する必要があって、ゴルフ場をマネジメントしながら健全化の源泉である利益を出す。これによってメンバー、株主、従業員の満足度を高めていく。そんな道筋になるわけです」
それで今、キャッシュフロー・ベースでどれくらい改善したわけですか?
「買収コースの8割以上が黒字になりました」
すごいですねぇ。で、どのように?
「私どものビジネスコンセプトは『チェーンオペレーションの徹底』で、10コース程度のチェーンではゴルフ場経営の採算が合いません、合わないから倒産してしまう、という視点に立っています。
数を持たないとコストは下がらない。だから数が大事なんで、このコンセプトはアメリカで50年以上も前のビジネスモデルなんですよ。
会社の近所にとんかつ屋があって、カツ丼が870円です。コンビニのカツ丼は半額以下で、双方成立してますが、400円のコンビニはこれを可能にするシステムがあるわけで、決してマジックではありません。ゴルフ場も同じですよ」
PGMは2010年までに、運営受託を含めて200コース(現在100コース)を目指してますが、社内的なチェーンオペレーションによるコストの優位性とは別の視点で、他社対抗的な意味合いのシェアもありますね。
仮に200コースを取ってもシェア1割に届きませんが、限界シェアについてはどんな判断ですか?
「それについては今のところ、未知数ですね。国内2430コースのうち、当社とアコーディアさんを併せても現段階では7%程度じゃないですか。我々の力が及ぶ範囲はどれくらいなのか……。
まあ、2010年で200コースは発表している数字なので、間違いなく目指しますが、それ以降は未知数なんですよ」
買収環境は厳しくなってくる
先ほどコンビニのカツ丼の話が出ましたが、コンビニ業界の激越なシェア合戦が派生する形で「99円ショップ」を生み出して、社会で価格破壊が進んでいます。御社はつまり、それをゴルフ業界に持ち込むわけですね。
「いやいや、そこを目指して経営してるわけじゃありませんよ(苦笑)。採算の中で大事なことは適正利益を出すことで、そこは重視していきます。とはいえ、競争はいつの時代も同じことで、永遠に続くテーマです」
御社の競争相手はアコーデイアですが、今後ふたつの局面で競合が激しくなってきます。ひとつはコースの買収競争、もうひとつは顧客の獲得競争ですが、その際、PGMとアコーディアの違いは何でしょう。
「そうですねえ。まず、アコーディアさんはマクドナルド・スタイルで、すべてのコースに統一感を持たせています。色や看板、スコアカードも共通化するなど、経営はやりやすいと思います。
これは想像ですが、1コース当たりの入場者数は向こうが多いでしょうし、単価も安いはずだと思います。ところがウチはそれと反対で、PGMのカラーを出しません。そこが一番の違いでしょうね」
その理由は?
「まあ、一言でいえば哲学の違いだと思います」
わかりません。哲学って何ですか?
「うん、ゴルフコースは地域のニーズによって成立します。だからメンバーの心象に配慮する必要もある。経営破綻で買収されて、『進駐軍』が我が物顔で居座ったらどうなりますか?」
もの凄く居心地悪いというか、腹が立ちますね。だって、そもそも自分が払った会員権で造ったコースなのに、他人が我が物顔で振る舞うわけだから。
「ですよね。メンバーさんの気持ちを考えれば、進駐軍的な振る舞いをしたり、何から何まで新しいやり方に変えるべきではありませんよ。
だから我々は買収後もコース名を変えないし、PGMのコーポレートカラーも押し付けません。それで傍目にはPGMとわかりにくいわけですが、それでいいと思ってます。
破綻コースは今後も沢山でると思いますが『買収されるならPGMの方がいい』と、そんな希望を口にするところは多いんですよ」
アコーディアは現在87コースですが、あそこはチェーンの着地点を「取り敢えず100コース」と考えています。
「うん……」
PGMの目標はその倍だから、買収は当面続きますね。
「そうですね」
その一方で、第三勢力、つまり国内の様々な企業がゴルフ場買収のビジネスに参戦してきています。当然、買収状況は厳しくなるし、そんな事情を考えれば「進駐軍的な手法」は得策じゃない。「配慮」というのはその意味ですね。
「おっしゃるとおりです」
目標の200を達成したら、一転、マクドナルド・スタイルに転じるかもしれない。その方が合理的ですから。
「まあ、良し悪しの判断をするのは時期尚早だと思いますが、将来においてその必要性が生じれば、そうなるかもしれませんね」
運営コースの利益ターゲットはどれくらいですか?
「まあ、今はコメントを控えましょう(笑)」
ゴルフ場って図体が大きいから、売上も大きいと思われがちですが、実のところ中小企業なんですよね。経営状況が「中の上クラス」でもキャッシュフローで年商5億円。年間来場者5万人で客単価1万円。これに年会費と名変料が付く程度で。
「あのね、ゴルフ場をアバウトな数字で考えたら駄目ですよ。コース経営はディテールビジネスですからね、これまでの大雑把な手法は通用しません。
たとえばリゾートコースといった場合、北海道のリゾートや東京近郊の『リゾート的』なコースでも、実態はまったく違うじゃないですか。そこをきちんと把握しないと」
その違いを御社の場合、何分類してるんですか?
「そうねえ、マーケティング的には12分類ですが、これにリージョン(地域)の気候やGDP、絶対人口とゴルフ人口の兼ね合い、消費特性などを吟味する必要があります。
リージョンは県単位がベースになって、先ほど申し上げた要素をマトリクスで判断するわけですが、これ以上は企業秘密です(笑)。それでもね、かなり話した方ですよ。ちょっと話しすぎたかなぁ」
ありがとうございます。それでは最後にビジネスビジョンを伺います。これ、凄く大事なことだと思うので。
「大事ですね。我々のキャッチフレーズは『Love Life Love Golf』で、ビジョンはこの言葉に集約されているんですね。
博報堂は以前、コカ・コーラを普及させるときに『スカッと爽やかコカ・コーラ』とやって成功しましたが、会社の名前を打ち出すよりも、商品を想起させる言葉の方が遥かに浸透しやすいわけですよ。
従来のゴルフはビジネスマンの世界に偏りすぎて、女性や子供が入れないというイメージがありました。当社はそれを壊すために、逸早く業界のリーダーになることを掲げたし、そのために創業から5年で上場しました。
その上で、ゴルフビジネスの最大のリスクは何だと思いますか?」
それはもう、天候要因、天変地異を含めてこれでしょうね。
「そうなんです。だからそれをヘッジするためにも、全国チェーンを追求しているわけですよ。
先頃『P-CAP』制度を導入して、会員は系列コースで安くプレーできるようになりました。それで『価格競争勃発か?』と書かれるのは筋違いで、重ねて申し上げますが、うちは安ければいいという考えは持っておりません。
正当な価値を提供し、質の高い利益を得るのがビジネスビジョンだと心得ています」
[surfing_other_article id=71617][/surfing_other_article]
[surfing_other_article id=63292][/surfing_other_article]
[surfing_other_article id=58048][/surfing_other_article]
[surfing_other_article id=50195][/surfing_other_article]
[surfing_other_article id=57486][/surfing_other_article]