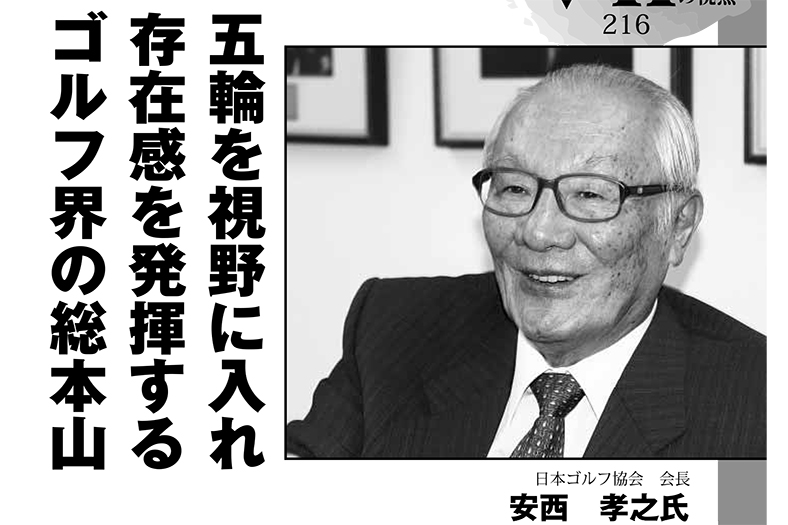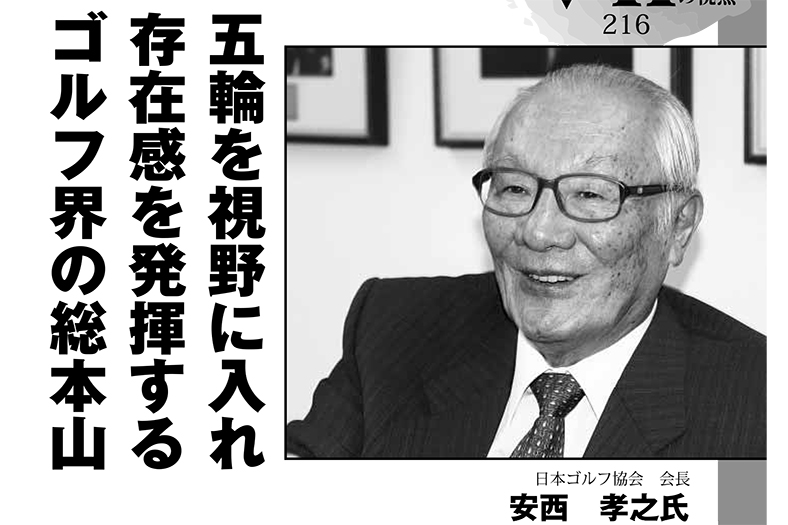「GEW」2013年11月号を振り返る JGA安西会長が描くゴルフ界発展の姿
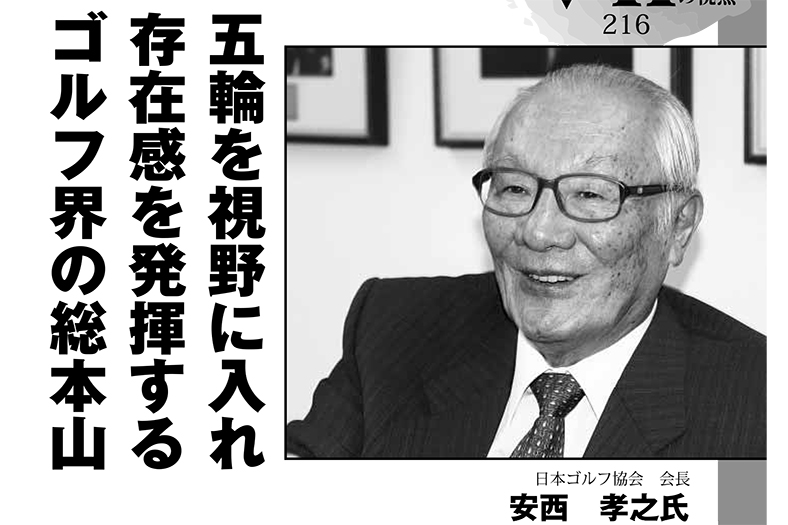
[archives key="蔵出しインタビュー" order="216" previousWpId="" nextWpId="" body="JGA(日本ゴルフ協会)元会長の安西孝之氏に取材したのは2013年10月だった。その前年4月、JGAは「公益財団法人」に移行して、活動目的を新たにしている。
JGAは「競技団体」と呼ばれる。国内ゴルフ場の6割ほどが加盟して、全国でアマ競技を行うほか、日本の三大オープン(男子、女子、シニア)を主催。また、ゴルフのナショナル・フェデレーションとして五輪選手の強化・派遣も専権事項だ。
ところが「公益財団」になると、競技ばかりに力を入れるわけにいかない。ゴルフ全体の普及を行う立場として「競技」以外の活動も大事になる。
折しも2016年のリオ五輪からゴルフが正式競技となり、東京大会の招致も決定。これを機に、スポーツ課税として評判の悪い「ゴルフ場利用税」の撤廃も現実味を帯びはじめた。というタイミングで、この取材を行った。
その後、利用税は東京五輪でも廃止されず、今に至る。撤廃運動は下火になり、業界には諦めムードが漂う印象もある。改めて、10年前の動きを振り返ってみよう。なお、文中の役職、組織、数字等は当時のままであることを留意願いたい。"][/archives]
[back_number key="201311"][/back_number]
「スロープシステム」の導入
JGAは日本のゴルフ界の総本山という位置づけなので、ちょっと敷居が高いんですが、
「いえいえ、そんなことはありませんよ(苦笑)」
どういった組織なのか、改めてその点から教えてください。
「わかりました。JGAの発祥は1924年でございまして、7倶楽部(神戸、根岸、鳴尾、東京、舞子、保土ヶ谷、甲南)の代表が、ゴルフの統括団体を作る目的で始まったわけです。
戦前の加盟倶楽部は50〜60だったと思いますが、ピークは約1600、今は1540ほどに少し減っておりますが、会員制のゴルフ倶楽部が加盟対象になっています」
いきなりお金の話を聞きます。
「はい」
当期の収支予算はゴルフ場からの「会費収入」が4億6000万円ほどです。前期比で2000万円ほど減ってますが、これについての印象は如何ですか?
「まあ、コース経営が苦しくなったから漸減しているのであって、(JGAが)必要ないから減っているわけじゃないと思いますよ(笑)。
我々の成立過程を鑑みれば、会費で運営してきた経緯がありましてね、年会費は18ホールで26万円、27ホールで34万円、36ホールで40万円です。
ただし、加盟するメリットを打ち出すことはとても大切だと考えていまして、そのひとつが不退転の決意で来年1月1日からの導入を決めた、USGAのハンディキャップシステム(スロープシステム)です。
これは61か国・地域で導入されてましてね、最大の特徴はハンディの互換性なんですよ」
互換性とは?
「従来のハンディキャップはね、その人の所属倶楽部で10ならば、難易度の違うコースでもハンディ10でプレーしていました。ところが新システムは、コースのレーティングに応じて『その日のハンディ』が調整できるんです。
これによってボギープレーヤーも競技への参加意欲が高まるでしょうし、たとえば8月1日に全国のゴルフ場で一斉に大会を開いたとして、『その日の日本一』を決めることもできるわけです。
JGAは昨年、公益財団法人に移行しましたので、ゴルフの普及・振興を目的に、全ゴルファーへ門戸を開放しなければなりません。新しいシステムは、そのあたりの効果も強く意識しております」
そのシステムが、ゴルフ場がJGAに加盟するメリットになるわけですか?
「それはなるでしょう。加盟倶楽部は『スロープシステム』を無料で利用できますし、従来は400円頂戴していたJGAハンディも無償化します。JGAに未加盟の倶楽部からはお金を頂くので、加盟して無料になることはメリットでしょう。
それとJGAの個人会員は2万8000人ですが、ゴルフ人口800万人に対して如何にも少ないじゃないですか。一連の活動を通じましてね、個人会員はひと桁上の28万人を目指したいと思っているんですよ」
賞金を高くして世界の一流を呼ぶ
JGAの事業活動は「競技」「普及」「育成」「国際交流」「マーチャンダイジング」の5本柱です。「競技」は全国でアマ競技を行うと同時に、「日本」と名がつく三大オープン(男子、女子、シニア)を主催していて、その事業費は計12億円を超えています。つまり、イベント運営団体という体質も強いわけですか?
「まあ、オープン競技については別に考えたほうがいいと思いますがね。3オープンはゴルフの普及・振興に関わる大切な事業で、とにかく日本最高の競技にする、世界最高峰の『USオープン』や『ブリティッシュオープン』に一歩でも近づくために、損益と分離して進めている気持ちが強いんですよ。
今おっしゃった数字は、いつの収支予算ですか?」
当期のです。
「なるほど。7〜8年前はその半分ほどで、2006年に賞金をゴソッと上げました。
男子の優勝賞金は2400万円から4000万円に上げて総額2億円、女子は1400万円を2800万円にして1億4000万円。シニアも増額しましてね、スケールアップを図ったのです。
まず、先に賞金を上げることを決めたので、担当者は大変だったと思いますが、いつまでも同額ではね、つまり同じ収入に見合った支出(賞金額)では世界に追いつけませんから。
賞金を高くして、世界の一流選手が出てくれば望ましいですよね。大会は『舞台』と演じる『役者』、盛り上げる『観客』と『運営』の4者がしっかりして、初めて成功するわけです。
実はね、去年の『日本女子オープン』は世界ランク10位までが8人ほど出ています。同様に男子の『日本オープン』も、世界の一流選手が出たいと思える大会にしたいですね」
ただ、日本のトーナメントは入場料収益が極端に少ないですね。一般的には冠スポンサーの出費で賄いますから。
「そう、日本のトーナメントはチケット販売に力を入れてきませんでした。一般的にはクライアントがパッケージで保障して、チケットはタダで配っても構わないということです。
とはいえ我々の大会は、倶楽部に販売権を差し上げて、自治体なりと連携して、地域で販売して頂くわけです。有料入場者の数は大会の価値を推し量る大切なバロメーターですからね。それもあって8年前、ギアをローからトップに切り替えたんですよ(笑)」
五輪の強化選手はJGAが選ぶ
優れた舞台という意味で「2グリーン」の問題はどうですか。ゴルフは1グリーンが世界の統一思想ですが、「日本女子オープン」(相模原GC)は2グリーンでした。それを非難するムキもありますが。
「まあそれはね、日本の芝は夏に弱かった、それで2グリーンになった経緯もありますが、日本独自のゴルフ文化として2グリーンが評価される面もあるわけですよ。同じコースでふたつのグリーンを楽しめるとか……。
しかしながら世界の潮流は1グリーンですね。ゴルフ文化は欧米から来たものですが、日本が独自に培ってきた文化を肯定しながら、どうやってグローバルへ移行するか。
いずれにせよ、物事には矛盾があるわけですよ。
アメリカはパブリックのゴルフ場がほとんどですが、日本は会員制が大半ですな。公益法人であるJGAは、閉鎖性を是とする会員制倶楽部で成り立っているところにも矛盾がありますし、会員制のゴルフ場はメンバーの収益だけでは成り立たない。これも矛盾です。
2グリーンも同じことで、今すぐに解決することは難しいけど、徐々にその方向(1グリーン)が望ましいとは思います」
まぁ、人生そのものが矛盾に満ちてますし、矛盾はいずれ解決すればいい、と。
「そうそう(笑)」
五輪について伺います。リオと東京でゴルフ競技のメダルが期待されますが、そのためには競技団体であるJGAの真価が問われます。基本認識として、JGAはどのような立場なんですか。
「五輪に関しましてはね、まずJOC(日本オリンピック委員会)が28競技から成る五輪選手団を一括して形成します。そのJOCにゴルフ選手を送り出す唯一のナショナル・フェデレーションがJGAで、これはJGTO(日本ゴルフツアー機構)でもLPGA(日本女子プロゴルフ協会)でもありません。
ただし我々が勝手にやるのではなく、関連団体と連携した『オリンピック対策本部』を立ち上げましたので、JGAはコーディネーターの役割りを担うことになるでしょう」
なるほど。それで強化選手を選ぶ道筋はどうなりますか?
「ゴルフの場合、五輪選手は大会直前の世界ランクで決まりますが、それ以前の強化段階では、JGAが強化指定選手を選んで文科省とJOCに推薦します。
3年後のリオデジャネイロと7年後の東京では意味合いがまったく違いましてね、基本的に東京は、今の13歳、14歳の選手をどうやって育てていくか。一方のリオデジャネイロは、プロで志のある選手をどうやって選んで強化するのか……。
JGAはこれまで、アマチュアのナショナルチームが中心だったじゃないですか。プロになったら関知しませんよ、という姿勢だったわけですが、今後はプロとアマも一気通貫でやる必要があると思いますねぇ。
国立のスポーツ科学センターとトレーニングセンターがありましてね、選手の様々なデータが科学センターへ送られて、選抜・強化するわけですが、ゴルフにはトレーニングセンターがありませんので、早急に決めなければなりません」
特に「東京大会」に向けては、より広範な人材発掘と育成が必要ですね。
「そうです。ジュニアの『発掘』『育成』『強化』事業は、これまでも力を入れてきましたし、その優等生といえるのが『日本女子オープン』を制した宮里美香さんです。
14歳で『日本女子アマ』に勝った彼女はジュニア時代、多分、もっとも多く海外に派遣した選手ですが、特に女子についてはね、我々のジュニア育成が効果を発揮していると思えます。
とはいえ、強化資金は十分ではありません。ジュニアの合宿は設備が整っているグアムで行うんですが、韓国の場合、ナショナルチームの年間予算は5億円ですよ。我々とは桁がひとつ違うんですね。
それと、JGAには8地区の連盟があって、それぞれが地区の特徴を生かして選手の発掘活動をしていますが、困ったことに数年前まで『うちの子は運動神経がにぶいからゴルフでもやらせよう』というご両親がいたりしてね(苦笑)」
たしかにゴルフは、足が遅くても俊敏じゃなくてもできますし、野球やサッカーに比べてレベルが下に見られます。そのあたりの認識は、人材発掘に対する大きな壁ですね。
「そうなんですよ。たしかに運動神経が抜群に良くなくてもいいかもしれんが(笑)、問題は体力ですよ。食事や睡眠のとりかた、集中も体力がないとできないので、そういったゴルフの特性を広く知らしめる、教える必要もありますなぁ」
ゴルフ「文化と産業」は両立できる
ところで、JGAは「ゴルフ文化の本陣」という位置づけですが、
「うん」
そのような体質は時として、ゴルフ産業との対峙関係を招きます。「文化」と「産業」は対立する、という観点です。たとえば、ヘッドの反発性能でボールを飛ばすクラブを禁じる「高反発規制」の問題ですが、
「そうかなぁ……。ぼくは別に、対峙してるとは思わないですよ。
だって無制限に飛ぶクラブやボールを作っていいわけはないでしょう。そんなことしたら、ゴルフというスポーツが成立しなくなってしまうじゃないですか。
道具の技術進歩に対する様々な声は常にあるし、根本的には飛ばないボールを作ればいいという意見もあります。ただ、野球じゃないけど、そこに捕らわれすぎてもいけないし、さりとて、ゴルフ場を長くすることも難しいし……。このあたりは簡単に答えが出る問題じゃありませんなぁ」
JGAは「ゴルフ産業」の発展に前向きなんですか?
「もちろん積極的ですよ。我々はアマチュア競技に力を入れておりますが、一方においては生涯スポーツとしてゴルフをたしなむ人口は競技者よりも遥かに多い。従って、趣味として楽しむゴルファーを如何に増やすかが一番重要です。
要するにね、文化も産業もそうですが、双方とも普及・振興の結果において発展するわけです。
あなたはゴルフ雑誌を出して、用具メーカーのことが頭にあるから『技術進歩を止める規制はどうなんだ』と言いますけどね、ゴルフ場はサービス産業で、物作りとは違います。
つまりJGAの立場はどちらがどうということではなくて、ゴルフそのものに力を入れているということですよ」
大本ですね。ゴルフという大本の幹を育てれば、ゴルフ場や練習場、用品の枝ぶりも豊かになる、と。
「そうそう(笑)。それがJGAの役割ですよ」
「利用税」の撤廃に向けて
その際、関連17団体が加盟する日本ゴルフサミット会議がありますが、その在り方はどうでしょう。議長はJGAの会長、つまり安西さんが務めますが、ゴルフ振興に向けて業界の各種団体が集まったものの、具体的な活動は遅々として進みません。
「そうねぇ……。まず、参加団体が多すぎて、議論の焦点が合わないという問題がひとつ。17団体が年に1〜2回顔を合わせるだけのサミット会議で、何かを作り出すのは難しいと思うんですね。
それよりも新年会をして、『やあやあ』と交歓することに意味があるんじゃないですか、と思いますけどね」
JGAはリーダーシップを発揮する立場だと思います。日本のゴルフの総本山ですから。
「まあ、それは申し訳なく思いますし、JGAが本気になればまとまるとは思うんだけど、やることが沢山あってねぇ(苦笑)。ゴルフの中核団体としてリーダーシップを発揮する必要はあるけれど、多様な意見をまとめる活動には、正直、手が回っておりません」
ゴルフ界の団結という意味では、過去にゴルフ場利用税の「一部撤廃」や震災復興のチャリティ活動がありました。今はゴルフが五輪種目に採用されて、東京五輪も決定した。ゴルフ界が飛躍する絶好のチャンスだと思うんですね。
「むろん、そうです。日本のゴルフ史を振り返ると、第一次ゴルフブームが起きたのはカナダカップからですよ。その後、AONという大型のプロフェッショナルゴルファーが登場して、二度目のブームが起きたわけですな。
ツアーが活性化して、企業広告の媒体価値が高まった。観戦スポーツとしての地歩も固めたわけです。
ところが、バブル経済の影響でゴルフ場が沢山できて、会員権やプレー料金が上がってしまい、ゴルフの素直な成長を阻害しちゃった。金持ちの道楽と揶揄されたり、社用族、あるいは投機に利用されたりと、マイナス面が沢山出たわけですよ。
その後バブルが弾けて、ようやくスポーツとして認められるようになったのが現時点。今後は五輪をどうやって活用して、健全に発展させるかです」
最大の課題は、ゴルフ場利用税の「完全撤廃」ですね。だいたい、スポーツに課税することが間違ってる。徴税側は、ゴルファーは金持ちだから担税力がある、という理屈にならない主張をしてますけど。
「それはそうです。スポーツに税金が掛かるというのは、世界に例をみない悪法ですよ。しかも、二重課税(正しくは併課)という問題もありますね。
ゴルフ場経営の側面では、昼食付のパック料金が3000円という破格値で、このなかに800円前後の利用税が含まれるわけだから大変だし、スポーツに課税するという状況を放置すれば、日本は世界の笑いものになりますよ」
政治家の認識はどうですか。
「政治家の皆さんも『不平等税制』の認識をもっています。これまでは、利用税を廃止したらそれに代わる財源がないという理由で止まってましたが、五輪の東京招致が決まったことで、放っておけないという認識を大半の政治家がもっています。
ここまでは来た。ただね、利用税は一方において総務省管轄の地方税ですから、市町村がですね、環境整備や道路などで大きなモノを得ているし、ゴルフ場も市町村との兼ね合いで圧力を受ける場合もあるんですよ」
つまり、目処が立たないと。
「いやいや、そんなことはありませんよ。政治家も選挙で選ばれるわけだから、そのあたりの人間関係を利用してやるしかないですね。
いつまでとは約束できませんが、少なくとも東京五輪までには完全撤廃を目指したいですね。こんなこというと、リオまではいいのかって、政治家に安心されても困るんだけど(笑)」
利用税の廃止、期待してます。長時間ありがとうございました。え~、次に動画撮影をお願いします。
「なに?撮影もやるの……。随分と長丁場だねえ……」