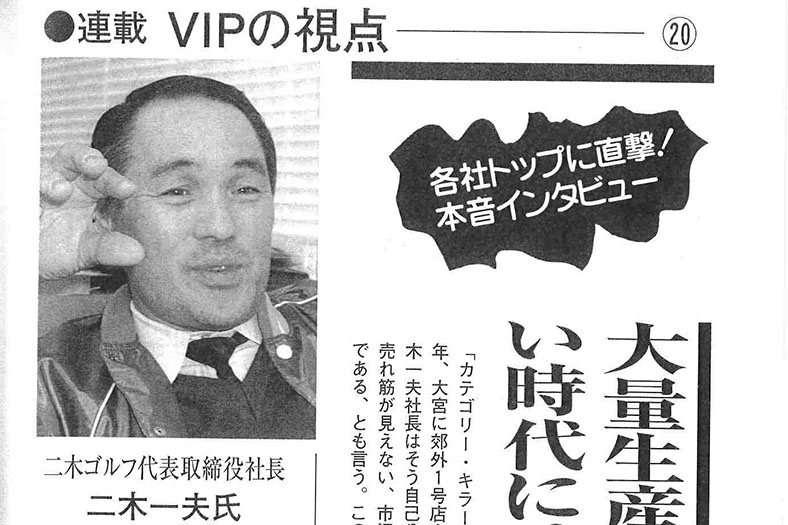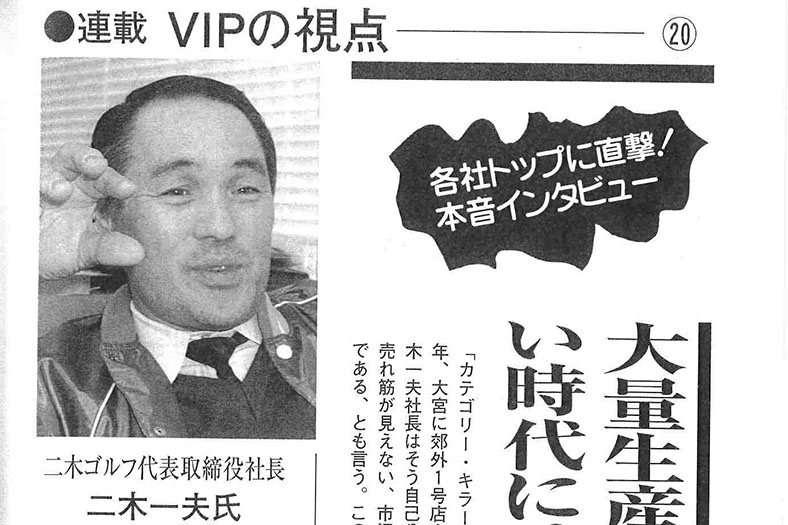[archives key="蔵出しインタビュー" order="20" previousWpId="" nextWpId="" body="東京・御徒町に菓子現金問屋として創業した「二木」は、二代目社長の二木一夫氏が枝分かれする形で二木ゴルフを創業。これが大当たりした。その意味で同氏は中興の祖であり、ゴルフ事業では創業者だった。
野太い声、学生時代にアメフトで鍛えた体躯は迫力満点。1979年、他社に先駆けて埼玉・大宮に大型郊外店を出店し、ゴルフ専門チェーンの草分けとなった。
取材当時の1996年は55店舗を構えて隆盛を誇っていたが、惜しまれたのは50代での早世であった。長男・一成氏が社業を継いで、創業50年を迎えている。
ゴルフ用品市場では2000年を境にECの台頭がはじまる。この取材はその4年前、同氏はネットの台頭で「小売りが不要になるかもしれない。経営的にはシビレるよね」と楽しそうに笑っていた。
小売業を「変化対応業」と位置づける同氏にすれば、環境の変化は「望むところ」だったのだろう。豪胆な一面が伺える。
今、往時の「二木語録」を振り返ることで、サラリーマン化した業界に刺激を与えることができるだろうか。なお、記事中の数字、メーカー名等は取材当時のものであることを了承願いたい。。"][/archives]
[back_number key="199601"][/back_number]
小売りは市場をつくれるのか?
最近、売れるクラブのセオリーがまったくわかりません。ヒット商品は何が決め手になって売れるんですか?
「それは、共通項の話だよね……。ハッキリ言って、売れるクラブの共通項なんかないでしょう。基本的には上位10ブランドで売上げの8割を占めるんだけど、ここにどんな共通項があるんだろう……。
実は、この取材の前に現場からきたデータを見てましてね、ドライバーは飛ぶという要素がありますがアイアンがまったく見えてこない。そんなことを考えてたわけ(笑)。
たとえばミズノの『ツアービッグ』ですが、正直言って僕はこんなに売れるとは思わなかった。で、売れる理由を考えると、あそこの宣伝力というか……なんて言うのかなぁ、パワーでウワッと持ってくでしょ。
もちろん口コミも含めての宣伝力なんですが、強引に広げるあのパワーはよそがどんなに頑張っても真似できない、ミズノならではのマーケティングですよ。商品力というよりも、企業力だったように思うんですね」
メーカーは「いい商品作れば売れる」というけど、そうじゃない?
「いい商品であることは大事だけど、それだけじゃないってことだよね」
市場に物が少ない時代はメーカーが有利な「メーカー主導」、物があふれると自由に選べる「ユーザー主導」になると言われます。となると今はユーザー主導になりますが、売れているのはミズノなど大手メーカーばかりです。そう考えるとメーカーのパワーは相変わらず強い?
「ですね。メーカー主導と言われた80年代、それが90年代前半にはディーラー主導と言われたし、今はユーザー主導とか言われますが、実のところ曖昧でね、本当のことはわからない。
もちろんメーカーは『ユーザー主導です』と言ってますよ。『我々メーカーはユーザーの声に耳を傾けて、あなた好みの商品を提供します』と。でもね、よーく考えると自分ちが支持されるのが前提でしょ。
じゃあ支持されるにはどうするか。ミズノみたいに沢山のモデルをずらっと並べて『さあ、この中から選んでください』と、ゴルファーをがっちり囲い込む。あるいはブリヂストンね、『ツーピースで14連勝しました、時代はツーピースですよ』とやる。
そうなると『プロや上級者は糸巻だ』と言ってきたダンロップも黙ってられないから、あっちこっちでガンガンはじまっちゃう。そのやり合いがトレンドを作って、ユーザーを巻き込んでいくわけですよ」
メーカーが語る「ユーザー主導」は、リップサービスなんですかね。個々の消費者に丁寧に寄り添っている、という一種のポーズ?
「まぁねえ。たしかに30年前、アイアンはスポルディング、ウッドはマグレガーと言われた時代に比べれば、今は格段に選択肢が広がっている。でもね、選択肢が増えたというレベルでのユーザー主導であって、基本的にメーカー主導は変わりませんよ。本当のユーザー主導になるとメーカーも困っちゃうだろうし」
「困る」というのは、そうなった場合の対応ですか。
「そう。これはウチの問題でもあるんだけど、素材が変わったときの怖さを常々感じているんですよ。ウッドはパーシモンからメタル、メタルからチタンに変わった。アイアンの場合はマッスルバックからキャビティバックにドカッと変わった。
すると前の商品が一気に不良在庫になっちゃうでしょ。
店としては、売れる物を在庫するのが大前提なんですが、素材が変わって構造が変わると一気にマーケットが変わってしまう。今はもう、マッスルバックなんか売れませんよ。
だけどウチにはマッスルの在庫が沢山残っているんだから。つまりメーカーの技術革新が、市場で圧倒的な影響力をもってるわけでね。
僕はこの商売はじめた時から『小売り主導でマーケットをつくれるのか』ということをテーマにやってきました。小売りがどうやって市場をつくるのか、という挑戦です。だけど現実には難しいよね。そんなふうに思います」
小売りは「中間搾取業」
市場はメーカーが牛耳っているんだと。だとすれば、小売りの独自性はどこで発揮すればいいんでしょう。
「本音を言えば、いい条件もらったメーカーの商品を売りたいよね。だけどウチの小売りとしてのスタンスはデモクラシー、つまり『ゴルフ民主主義』っていうのかな、より多くの趣味嗜好を汲み取ってユーザーの選択肢を広げていく。その中から支持してもらうことに尽きると思うんですよ。
小売りの独自性という意味では、ゴルフ5や有賀園、スポーツロードなんかと比べるとウチのプライスレンジは違いますし、その違いを売り場の提案て言うのかな、提案力で独自性を出していく。そういった部分が大事なんですね。
極論しちゃえば小売りって『中間搾取業』じゃないですか。だけど単に搾取するだけではないプラスαは、メーカーに対してユーザーの意識を整理して提供する、この部分のノウハウなんですよ。
メーカーって、自分ちの商品はわかってるけど、他社については意外と知らない。だけど我々は知っている、日々ゴルファーと接してるわけだから。そこを提案しながら、中間搾取だけじゃないメリットをアピールするわけです。
同時に、ゴルファーに対しては数ある商品を整理して、個々に最適なモノをきちんと販売していくこと。そこに小売りの価値があるわけです」
デフレは続きます
売るための大事な要素に「値頃感」がありますね。消費者と接する小売店は毎日の肌感覚でそれがわかる。その値頃感に、ある種の法則はあるんですか?
「それもね、けっこうバラバラで難しいんだけど、ゴルフの場合は月に何回プレーするかが大きいんじゃないですか。アメリカの製品は高いドライバーで1本200㌦から300㌦くらいしますけど、日本の市場はその人の1か月のプレー代と関係してるように思えるんですよ。
月イチゴルファーなら3万円のドライバー、4回なら12万円とか…。もちろんプレーするコースも違うからプレー料金は一概に言えませんが、感覚的にはそういった関連性があると思う。アイアンは長持ちするからウッドの4、5倍かな。だからゴルフ場が安くなれば必然的に用具も安くなっていくでしょう」
ゴルフが大衆化すれば、必然的に用具も下がる。ある種の必然性ですね。
「だと思います」
それとは別の流れとして、総じて物価は下がってます。在庫整理と円高デフレが要因でしょうが、これからゴルフ用品はどうなるんでしょう。
「物価はね、上がりませんよ。生活物価はどんどん下がる傾向ですな。
土地をみれば明らかで、日本の場合は土地が高かったからすべての物価に反映してきたわけですよね。だけど現状、土地は下がっている。このトレンドが今後も続けば派生していろんな物価が下がっていく。
だから日本もEU型の経済と同じ動きになっていて、トータルのキャパが増えないことを前提に利益の絶対額を確保しなきゃならないわけです。
ゴルフ用品も同じことで、大量生産・大量販売が通用しない時代では、拡大志向なんかナンセンスですよ。大事なのは固定客のリピート率、つまり選挙と一緒で支持率をどうやって上げるかの勝負になってくる。
二木ゴルフが好きだから二木に来る。ヤマハの『プロト』を買ったら次も新しい『プロト』を買いたくなる。買いたくなるプロモーションをどうやってやるかが大事なんで、自動車にしてもカローラを買ったら次はマークⅡ、それからクラウン、セルシオと、買い換えてもらうための智恵が試されます」
捨てる覚悟が大事です
量を求めず利益の絶対額を確保する時代。となれば、企業の経営指標だった売上げやシェアにとらわれない経営思想が必要になってきますが、その思想の根本を、メーカーはどこに置けばいいんですか。
「それは『自分ちは何屋なんだ』という、そこの認識じゃないですかね。小売りもまったく同じことで、ウチもディスカウンターやスーパーの台頭で影響は受けてますよ。ボールなんか我々の常識では2割引きなんだけど、向こうは4割、5割でもいいんだ、と。
要するに彼らにとってのゴルフ用品は、全体の一部にすぎないんですね。たしかにスーパーもディスカウンターも沢山ゴルフボールを売りますが、一方でリピーターは定着しないじゃないですか。値段で動くわけだから。
だから我々専門店は、ウチとは関係ないと思いきることが大事なんです。もちろん同じ商品なわけだから影響は受けるし、異業種間の競合は必ず起こる。起こるんだけど、敢えて『関係ない』という覚悟を貫くことが大事だと思います」
貫く覚悟の源泉はなんですか?
「それはね、その会社のコンセプトですよ。同じことはメーカーにも言えて、メーカーのコンセプトをびしっと打ち出したところが結局は受け入れられる。
自分ちのお客さんを明確に意識するべきで、全員に使ってもらおうとすると虻蜂取らずになっちゃうでしょ」
なるほど、積極的に捨てる覚悟で自らの姿勢を鮮明にする。
「そうです。マルマンは一時厳しかったけど、今は持ち直していますよね。それで『科学のマルマン』を定着させた。売る相手は初中級者に絞り込んで、ここへのアピールに徹している。
ダイワ精工にしてもミズノの小型版といった歩き方から、特徴的な商品で隙間を狙う戦略に変わっています。
さっきのボールじゃないけれど、ブリヂストンにしてみれば糸巻ではダンロップと勝負にならない。BSの『レクスター』とダンロップの『マックスフライ』じゃ、やっぱり『マックスフライ』が選ばれますよ。
それでツーピースボールをジャンボ軍団に使わせた。どっこいコレが飛ぶんだね。驚くほどブッ飛ばす。それで『ツーピースはブリヂストン』という評判を勝ち取った。
キャスコの『RR』にしろトップフライトの『スーパー・ソフト』にしろ、物はいいんですよ。いいんだけど、この領域はブリヂストンの『ニューイング』が圧倒的に強いでしょ。要するに、度胸を据えたメーカーのコンセプトがユーザーを惹きつけたわけで、自分ちのいいイメージを覚悟して、どうやって定着させるかなんです。
これを必死にやらなきゃ数あるブランドから選ばれないよね」
片手間や、必死さがないメーカーの商品は相手にされない。
「そう。ダンロップもここに来てツーピースをガンガンやってるから、かなり激しいことになるでしょうな。それが全体の活性化につながるし、ゴルファーの琴線を揺さぶるわけです」
セイコーの参入で一変した
活性化をする上で、手っ取り早いのが異業種の参入です。異業種の知恵や技術が入ることで、市場の多様性なり活性化が実現される。最近の例では服部セイコーがデカチタンの『S・YARD』で参入して、一気に市場が動きました。
「そう、あれは異業種の参入が市場を活性化させた典型的な例でしょうなあ。『S・YARD』が登場して、当初は三越で火をつけた。それでデパートも息を吹き返した。
大型チタンヘッドという意味でも先鞭をつけたし、このモデルは一種のカテゴリー・キラーと言えるかもしれないよね。
既存のメーカーにしてみれば、忸怩たる思いがあるはずですよ。ここまで市場を育ててきたのはオレ達だ、種蒔いて育てて、さあ収穫だ。と思ったら、あれっという感じでバッサリ持ってかれちゃった。
特にダンロップやブリヂストンなんかは『商品が高い』って言われながらもトーナメントに金を掛けて、宣伝して、産業としてのゴルフを育ててきたわけだから」
実った稲穂を新参のセイコーに取られちゃった。
「それは業界の話だからユーザーには関係ない、と言われればそれまでだけど、本音を言えば悔しいよね。僕にしても、先達の功績に対しては敬意を払ってます。だけど、そのことと新規参入による活性化は別の話で、振り返れば過去に同じことが沢山あったじゃないですか」
エポックは70年代の初頭ですね。ライターのマルマン、釣り具のダイワ精工、タイヤのブリヂストンと大型参入が相次ぎました。それで一気に市場が大型化した。
「そう、ちょうどジャンボ人気に火がついた頃だよね。それまでのプロスポーツは野球であり相撲でしょ。ゴルフなんか認知されていなかった。
それが一般に知られるようになってライター、釣り、タイヤの大手が異業種参入の形でゴルフ事業をやりはじめた。これによって市場が飛躍的に拡大しました。
ウチなんかもその頃スタートしましたが、最初はね、大宮の野っ原にあんなでかい店をつくって『大丈夫か?』って散々言われたもんですよ。つまり二木ゴルフもカテゴリー・キラーだったんだけど、そんなの今じゃ珍しくもなんともないじゃない。
企業30年説とはよく言ったもので、最初は新規参入だったけど、いつの間にかカテゴリーに収まっている。市場って面白いもんで、ある一線を越えた瞬間、急に拡大するんですよ。ゴルフの場合はプレー人口が1000万人を超えたあたりでドカーンと広がった。
その頃合いを見て外から入って、相乗効果で拡大する。セイコーにしてもね、あそこが入るに相応しい市場規模に育ったな、という判断が当然あったはずですよ」
カテゴリー・キラーはイノベーター
カテゴリー・キラーの有効性をどのように定義しますか?
「そうねえ。定義としてはやっぱりイノベーターだと思いますね。イノベーターというのは現状破壊を伴う革新で、ウチの郊外1号店だった大宮にしても、駅前の出店が当たり前の時代に『アホか』と言われたもんですよ(笑)。
でも5、6年もすると、ロードサイドの大型専門店がひとつのカテゴリーになってきた。
もちろん時代背景も重要で、大量生産・大量販売の入口だったからカテゴリー・キラーが成立したんだけど、同じ話は商品にも言えて、1本十数万円のチタンドライバーが主流だったら別のメーカーが8万円を出す、8万が出たら5万を出す、これも立派なカテゴリー・キラーじゃないですか。
そういったメーカーのやり合いが市場での熱気を生みだすわけで、消費者にしてみれば新鮮な魅力があるんでしょうな。市場の活気がゴルファーを惹きつける。市場が発散する熱量がね、ヒトを集めるわけですよ」
祭りと同じなんでしょうね。活気があると人が集まる。しょんぼりとした村祭りは閑散として物悲しい。
「言えるよねぇ(笑)」
二木ゴルフは、再度カテゴリー・キラーとして打って出る計画がありますか?
「まあ、今のところ具体的にはありません。とりあえず前年比10%アップで来てますし、去年3店舗閉めて2店舗オープンしたのもカテゴリーの中での工夫であって、本質的な意味での革新じゃない。
ただ、小売りっていうのは『中間搾取業』なんだけど『変化対応業』でもあるわけで、守勢にまわったらダメなんですよ。
インターネットの普及人口は5000万人になりましたが、さっきのプレー人口の話とまったく同じで、ある一線を越えたらぶわっと広がる可能性がある。それで買い物がネット社会になったとき、今の小売りは必要なくなるかもしれません。
だからショップ経営としてはかなりシビレるんだけど、常に新しいことに挑戦しなきゃダメですよ」
挑戦は楽しいですか?
「そりゃもう、めちゃくちゃ楽しいよね!(笑)」
[surfing_other_article id=76741][/surfing_other_article]
[surfing_other_article id=63823][/surfing_other_article]
[surfing_other_article id=60547][/surfing_other_article]
[surfing_other_article id=48462][/surfing_other_article]
この記事は弊誌月刊GEW 1996年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊GEWについてはこちら