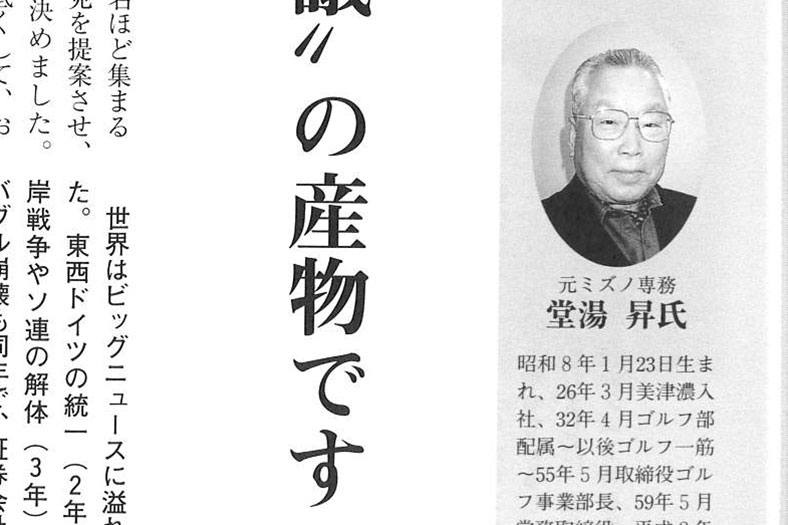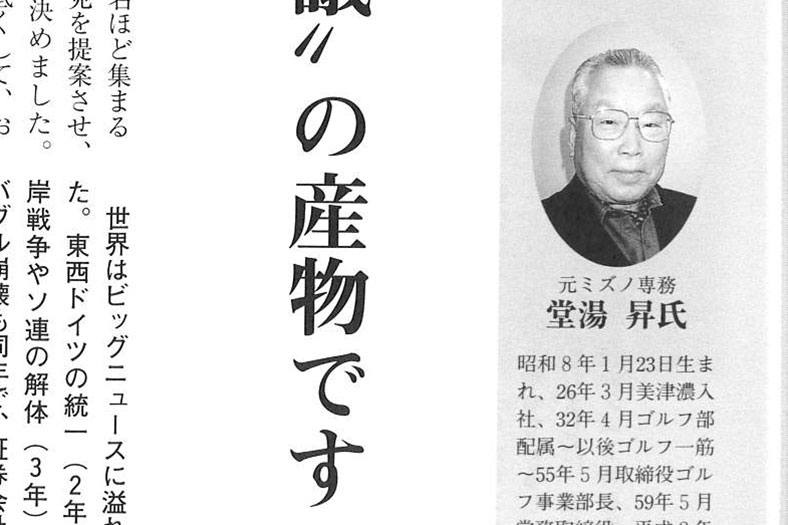「昭和」ゴルフ市場を振り返る ミズノ元副社長 堂湯昇編(5)
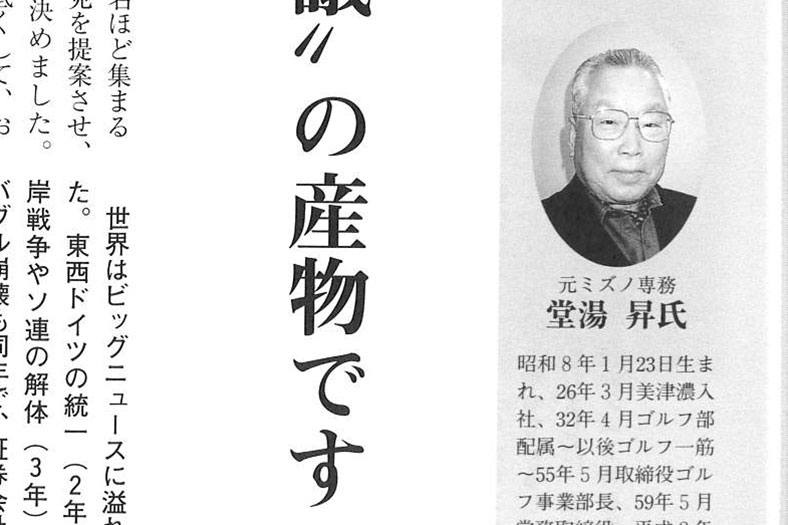
[archives key="蔵出しインタビュー" order="200" previousWpId="" nextWpId="" body="GEWの2003年6月号から同年10月号まで5回にわたり、ミズノの大番頭と呼ばれた元副社長・堂湯昇氏が昭和のゴルフ市場を語った「シリーズ温故知新」の最終回をお届けする。
バブル景気の波に乗って、同社は「5000億円企業」を目指した。2000億円をスポーツ用品の販売、3000億円をゴルフ場経営など施設産業で稼ぐ目算はしかし、バブルの終焉で崩壊した。堂湯氏は「私にも責任がありました」と、反省の弁を口にした。
往時の天国と地獄はどのようなものだったのか。その詳細を振り返ろう。なお、文中の数字、社名等は取材当時のままであることを留意願いたい。"][/archives]
[back_number key="200310"][/back_number]
1本18万円のチタンウッド
専門店と量販店を比べた時に、ある種の思惑違いと言いますか、我々が専門店を過大評価したことは否めません。
ミズノはゴルフ専門店がなかった時代に、スポーツ店と一緒になってゴルフの売り場を作ってきた。そのとき私らが強く言いつづけたのは「ゴルフはほかのスポーツとは違うんです、専門性を磨きましょう」と。そういった経緯があったので、ゴルフショップは専門性が強いんだと、我々自身が思い込んだのかもしれませんな。
前回でも述べましたが、二木ゴルフさんとの取り引きで感じたのは、量販店の力強さであり、対して専門店の脆さだったような気がします。
そのうちメーカーは大型店に翻弄されて、コントロールできなくなってしまった。新規出店が相次いで、その都度オープニングセールをやるわけですが、特価チラシを見るたびにぴりぴりしとったもんですよ。
ただ、それが時代の熱気でもありましたなぁ。小売りの競争に煽られる形でね、商品開発が活発になって、新しい商品、魅力ある物がどんどん出た。平成2年に業界初のチタンウツド(ミズノプロTi)を1本18万円で発売したのが代表的な例ですよ。
もっとも、その頃私は全社の営業を見る立場で、ゴルフ事業は片山君(彰氏、元専務)に譲っておったんです。会議には出席するけれど、ほとんど口を出さないようにしましてね。20名ほど集まるゴルフ会議で個々の意見を提案させて、「1本18万円」も全員の合議で決めました。
チタンウッドの18万円は他の商品よりも掛け率を低くして、お店に儲けてもらうんだと、そんな狙いもあったんです。ただし、当初の販売目標は少なかったはずですよ。たしか年間5000本程度かな。それが最終的には3万本に届いたわけで、勢いというのは凄いですなあ(笑)。
目指せ5000億企業
当時、ミズノは全社的に活気があった。『ミズノプロTi』を上市した平成2年は年商1768億円(単体決算)、翌年以降1922億円、2003億円と飛躍的に伸ばし、これが同社のピークとなる。
世界はビッグニュースに溢れていた。東西ドイツの統一(平成2年)、湾岸戦争やソ連の解体(同3年)。バブルの崩壊も同年で、証券会社の損失補填が社会問題になっていた。
ちょうどあの頃、ミズノは21世紀に「5000億円企業」を目指すんやと、そんな構想がありました。社内の総合企画室を中心にいろいろ立案するんですよ。政府の資料、銀行の意見とかを集約して、物販じゃどんなに頑張っても2000億が限界だろう、残り3000億を上乗せるには物販以外に何ができるか事業部別に考えろと。
いま思えば、一種の熱病だったですよ。バブルの怖さと言えばそれまでですが、経済の実態を見誤った、ミスがあったということを、とても反省しております。私にも責任あると思ってます。
で、当時なにをしたか? 最初は勉強のために西田辺の社員寮を潰しましてね、上はマンション、下はフィットネスクラブを作りました。MARV構想の一環ですよ。
施設産業を中核に据えたMARV(ミズノ・アクティブ・リゾート・ヴィレッジ)は、同社の新機軸として大いに期待された。フィットネスクラブ、テニス施設、ゴルフドームやゴルフ場経営など、施設産業を意欲的に立ち上げた。
平成4年にはミズノの新たな象徴となる南港の新本社ビル「ミズノクリスタ」が落成している。総工費300億円を投じた地上147m(地下3階、地上31階)で、1~4階に「光のオプジェ」、1、3、4階にスポーツ博物館、31階にはスポーツバーを設けている。
「スポーツ文化新世紀への再創業精神」と謳った一大事業の背景に、5000億円構想があったことは言うまでもない。
初めて「ミズノクリスタ」を見た時には、へえ〜っ、派手なもんやなあと、正直びっくりしたもんですわ。あの頃は真面目に仕事しとれば売り上げを伸ばす自信があって、全社員が自信と昂揚感に包まれていました。
ゴルフ場が大失敗
最大の失策は、ゴルフ場ビジネスに乗り出したことですよ。私の記憶では、四国でゴルフ場やりましょう、滋賀県でどうや、岡山にもいい物件ありますよと、業者の売り込みは本当に頻繁でした。当時、日本全国で3000コースはできると言われていて、事実、私もそう思ったもんです。
日本全体が浮かれとったからしょうがない、とは言えません。景気の波は必ずある、その認識を誤ったということです。
営業を続けている月山(山形県)のコースは、苦戦してるようですな。思い出すのは地元代議士だった加藤紘一さんと月山のオープニングでゴルフやりましてね、これからは地方の時代やと、そんな話をしましたかねえ。
ゴルファーが増えて、高額商品が売れる中で、市場の成長を信じて疑わなかったわけですよ。
だけど、危機感を覚えたのは早かったんです。ミズノは平成4年のピークから売り上げがガタッと落ちましてね、平成5年が1894億円、その翌年が1727億円…………。こういった過程を見るにつけ、こりゃあかん、ゴルフ場やっとる場合じゃない、と。大ケガしてからじゃ遅いので、即座に方向転換したわけです。
近年、大幅なリストラをやりましたなぁ。1回目で350人、2回目で300人だったと聞いてますが、これも早めの決断でしょう。企業はヒトやと思うにつけ、まぁ、いろんなことを考えますが、私が口にすべきことではありません。
三者協力で立ち上げた「電波塔」
ひとつ言えるのは、市場育成の大切さです。そりゃね、資本主義社会やから、個別の競争はあって然るべきです。だけどその一方で、業界が手を携えて大同団結しなきゃいかん。団結すべきは団結する、そうじゃないと市場は大きく育ちませんから。
かつては団結がありました。今は薄れている。そんな印象はありますなぁ。
ひとつの例を申し上げると、住商さんが中心になって立ち上げた「ジュピターゴルフネットワーク」(CS放送)があります。これね、「ゴルフ界初の電波メディアを持つんや」と、ダンロップの大西さん(久光氏、元住友ゴムエ業常務)が奔走されたんですよ。
それで大西さんは「ミズノさん、BSさんも株主になってくれないか」と。「そりゃええことや」と息投合したものの、BSとダンロップはボールで激しく戦うライバルでしょ。大西さんからは話し難いということで、私が山中さん(故幸博氏、元ブリヂストンスポーツ社長)を口説いたんです。
ミズノは以前から、ダンロップやBSの代理店でした。両社のボールをミズノが販売するという関係やから、早くから親しく付き合っていたんですよ。そんなわけで、山中さんとも肝胆相照らす仲というか、あちらがゴルフクラブ事業を始めたときは「お手伝いしましょうか」と申し入れたり、電話で話すことも頻繁でした。
内容は、まあ、いろいろですよ。「あそこのボール安いやないか」「まいりましたなあ」とかもあったけれど、そんな商売の話だけやなくて、業界に対する考え方、こうすべきじゃないですかと、事あるごとに意見交換をしたもんです。
ダンロップとBSの関係を見るにつけ、ミズノが接着剤をしましょうと、そこで三者協議が成立したんですな。ジュピターへの出資に山中さんは二つ返事だったです。「よし、分かった」と。それで業界の電波塔というか、ジュピターゴルフネットワークが立ち上がりました。
大西さんも山中さんも、人間の度量が大きかった。たしかに商売敵ではあるんやけど、ゴルフ界はこうあるべきだと、見ている世界が大きいんですよ。そのためには目先の競争だけじゃなく、協力すべきは協力する。度量が本当に大きかった。
要はお互いを立てる、ということですよ。エンタープライズを作ってトーナメントの隆盛を築かれた大西さんはダンロップの代表的な存在でしたが、こちらを立ててくれるんですな。他人の意見に耳を傾けて、出来る出来ないをしっかり言う。それが信頼関係につながったんです。
それにしても、山中さんは早くに亡くなられて残念でした。二木さんも山中さんも五十代の早世でしょ。仮にご健在だったなら、ゴルフ市場の風景は今とかなり違ったものになっていたでしょうなぁ。
私が業界を離れてだいぶ経つので、今、どんな状況かを詳しく知ってるわけではありません。だけどゴルフの楽しさを啓蒙するためには、一致団結が絶対に必要。これだけは強く言いたいですね。
若者の参入をどうするか、女性対策やジュニア育成についてもね、大局観が必要です。老婆心ながら、改めて業界のご多幸を願ってやみません。あなたも大いに頑張ってください(笑)。