前回まで、ゴルフ場の隆盛と凋落の推移を見てきたが、本稿では、なぜリコンセプト(Re-concept)が大事なのか、その前提となる筆者の考えを述べる。
日本最古のゴルフ場、神戸ゴルフ倶楽部(一般社団法人)が六甲山頂に開場したのは1903年。最初の4ホールが開場した1901年を日本の「ゴルフ元年」とする説もあるが、英国人貿易商アーサー・グルームが故郷を想い、山頂に開いた。
以後、多くのゴルフ場が誕生し、近年は開場百年を迎える老舗コースが現れている。そして70~80年代の開発ブームに乗ったゴルフ場群は、歴史ある名門クラブを絶えず真似て、続々と誕生した。その弊害を、筆者は強く感じている。
古い社団法人のクラブ(一部、任意団体及び株主会員制の営利目的外クラブを含む)と、日本で約90%を占める営利目的の株式会社による預託金制クラブでは、理事会や各文化委員会の在り方が同じである必要はない。なぜなら、社団法人のクラブは営利目的ではないからだ。
ちなみに、いわゆる名門と言われる代表例に「関東七倶楽部」や「九大ゴルフ倶楽部」(重複コースあり)があり、これら歴史あるクラブの目的は、持続可能な運営のもとで会員同士が楽しむクラブライフを重要視するソサエティだ。
【関東七倶楽部】(社団法人、株主会員制)
小金井カントリー倶楽部(東京)、相模カンツリー倶楽部(神奈川)、程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川)、霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉)、東京ゴルフ倶楽部(埼玉)、我孫子ゴルフ倶楽部(千葉)、鷹之台カンツリー倶楽部(千葉)
【九大ゴルフ倶楽部】(社団法人、株主会員制、任意団体)
相模カンツリー倶楽部(神奈川)、程ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川)、霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉)、東京ゴルフ倶楽部(埼玉)、軽井沢ゴルフ倶楽部(長野)、神戸ゴルフ倶楽部(兵庫)、廣野ゴルフ倶楽部(兵庫)、鳴尾ゴルフ倶楽部(兵庫)、茨木カンツリー倶楽部(大阪)
同好の士が出資して運営する倶楽部は、性格上、排他性を伴う。その一方で接待需要が普及し、会員同士でクラブライフを楽しむ目的ではなく、Guest=接待先や、ゴルフ仲間を連れて楽しむスタイルとなったのだが、にも関わらず、多くは名門と呼ばれる社団法人系のクラブ運営を真似てきた。そこに、ボタンの掛け違いがある。
たとえば後発組のゴルフ場は、自ゴルフ場の物差しを決める際に「名門の〇〇倶楽部がそうしているから」とエクスキューズできるよう、模倣的に会則・細則・利用約款などを決めてきた歴史がある。水戸黄門の葵の御紋と同じで、名門の権威に盲従する情けない姿だ。
このような歴史が根深く残る盲従体質を改善するには、リコンセプトが唯一無二の方法だと筆者は考えている。
「預託金」の負い目
「なぜこうなっているのか?」について、本来は一つひとつ意味があって然るべきだが、先達からのバトンを受け継いできたゴルフ場の社員たちは、それが自社のコンセプトに合っているか否かが判断できず、問題意識なく過ごしていることが多い。日々の業務に追われる中で思考停止状態に陥っている。
筆者がゴルフ場をコンサルする際、現場からは「前任者がこのやり方だったから」「メンバーさんから言われたから」というフレーズをよく耳にする。逆に「当クラブのポリシーはこうだから、こうしたい!」との主張を聞くことは少ない。
なぜか? 多くのゴルフ場は預託金返還請求に困窮し、再生手続きなどを経て預託金債権を棒引きにしてもらった負い目があるから、と筆者は見る。バブル絶頂期の強気が一転、弱腰になり、主体性を失った印象が否めないのだ。
具体的な例をあげよう。
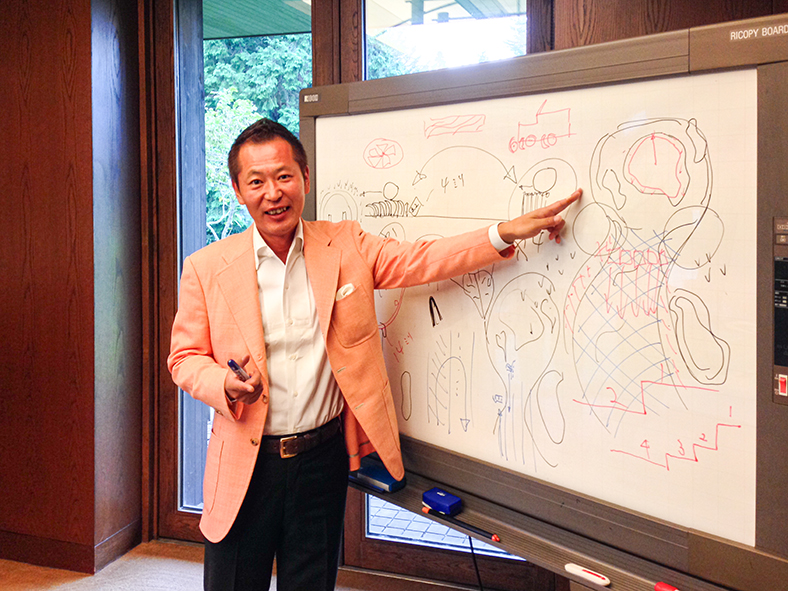
ゴルフ場の玄関先に、不似合いな装飾の置き物等をよく目にする。これらはステークホルダーなどからの寄贈品が多く、忖度して目立つところに置いている。ゴルフ場に支払う料金の中には「居心地の良い空間の利用料」も含まれる、と考えれば、その空間に不似合いな物は来場者に違和感を与える。サービスを提供するエリア用か、バックヤードに設置すべき物なのかの判断基準が歪んでおり、忖度優先の一例と言える。
また、ラウンジの雰囲気をぶち壊しにする「SALE」の張り紙や、業者から持ち込まれた不揃いの什器による景観の乱れもこれに該当する。
ホールインワン植樹も例外ではない。そもそもコースと樹木は密接な関係にあり、コース築造の際にはコースレイアウトのデザインと同時に植栽計画が織り込まれているため、ティーイングエリア付近に乱雑に植えるものではない。脈略なく植栽した樹木は、根が芝生の中に入り込み、水分を吸収し、芝生の生育を妨げたり、グラウンド上の不陸(地面の凸凹)が生じたりと様々な弊害を生む。そんな光景をしばしば目にする。
記念植樹の代わりに、クラブハウスにホールインワンのプレートボードを設置して敬意を払う。あるいは達成者が記念品の寄贈を申し出たら、ゴルフ場が木製の3人掛けベンチを用意して、寄贈プレートを背面に設置する。これはスコットランドの風習で、筆者のお勧めだ。
客観的な実態把握
リコンセプトの第一歩は、実態把握を徹底的に行うことから始まる。この実態把握は、あくまで〝客観的〟に行うことが重要だが、当然、このプロセスには外部の力を借りることをお勧めする。内部でやろうとすると現体制への批判と取られかねず、忖度した結論が生まれやすいからだ。
筆者がレポートをまとめる際には、その会社の強みや弱みなどを洗い出すSWAT分析から始める。そして、そこからリコンセプトとして目指すゴルフ場(なりたいゴルフ場)=新たなコンセプトを提案する。
リコンセプトの着眼点は、己を知り、己のポテンシャルをどこまで追求できるか、が重要。「己」は、自社のゴルフ場であり、その着眼点から見える光景よりも、アップサイドの提言、すなわちやるべき事項が浮き彫りとなってくる。また、リコンセプトが網羅すべき範囲は、全てに及ぶ。全ての細部において「当ゴルフ場はこのようなクラブにするべく運営しております!」という強いメッセージを発信できれば「Re-concept」は全ての指針となるはずだ。
基準が明確になれば「これはOK」「これはNG」という判断基準が理路整然と共有され、ひとつの法則が見えてくる。
この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2025年2月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

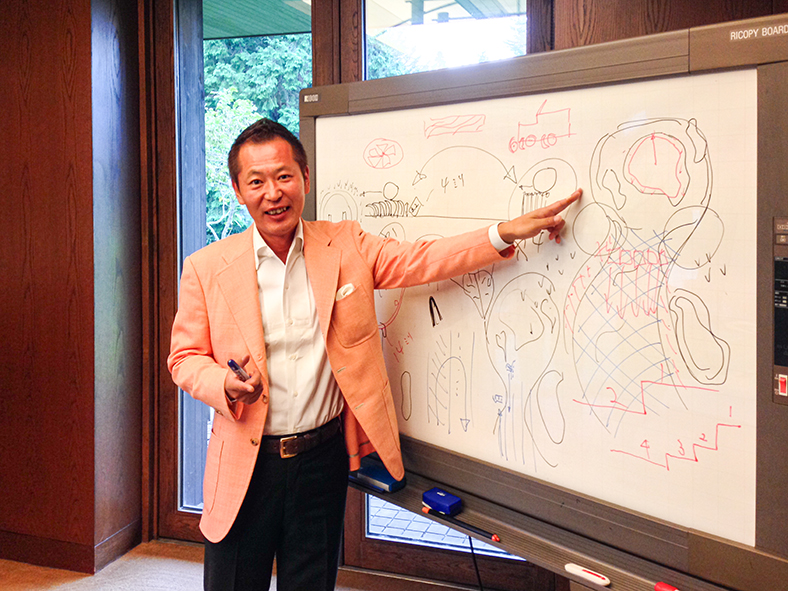 ゴルフ場の玄関先に、不似合いな装飾の置き物等をよく目にする。これらはステークホルダーなどからの寄贈品が多く、忖度して目立つところに置いている。ゴルフ場に支払う料金の中には「居心地の良い空間の利用料」も含まれる、と考えれば、その空間に不似合いな物は来場者に違和感を与える。サービスを提供するエリア用か、バックヤードに設置すべき物なのかの判断基準が歪んでおり、忖度優先の一例と言える。
また、ラウンジの雰囲気をぶち壊しにする「SALE」の張り紙や、業者から持ち込まれた不揃いの什器による景観の乱れもこれに該当する。
ホールインワン植樹も例外ではない。そもそもコースと樹木は密接な関係にあり、コース築造の際にはコースレイアウトのデザインと同時に植栽計画が織り込まれているため、ティーイングエリア付近に乱雑に植えるものではない。脈略なく植栽した樹木は、根が芝生の中に入り込み、水分を吸収し、芝生の生育を妨げたり、グラウンド上の不陸(地面の凸凹)が生じたりと様々な弊害を生む。そんな光景をしばしば目にする。
記念植樹の代わりに、クラブハウスにホールインワンのプレートボードを設置して敬意を払う。あるいは達成者が記念品の寄贈を申し出たら、ゴルフ場が木製の3人掛けベンチを用意して、寄贈プレートを背面に設置する。これはスコットランドの風習で、筆者のお勧めだ。
ゴルフ場の玄関先に、不似合いな装飾の置き物等をよく目にする。これらはステークホルダーなどからの寄贈品が多く、忖度して目立つところに置いている。ゴルフ場に支払う料金の中には「居心地の良い空間の利用料」も含まれる、と考えれば、その空間に不似合いな物は来場者に違和感を与える。サービスを提供するエリア用か、バックヤードに設置すべき物なのかの判断基準が歪んでおり、忖度優先の一例と言える。
また、ラウンジの雰囲気をぶち壊しにする「SALE」の張り紙や、業者から持ち込まれた不揃いの什器による景観の乱れもこれに該当する。
ホールインワン植樹も例外ではない。そもそもコースと樹木は密接な関係にあり、コース築造の際にはコースレイアウトのデザインと同時に植栽計画が織り込まれているため、ティーイングエリア付近に乱雑に植えるものではない。脈略なく植栽した樹木は、根が芝生の中に入り込み、水分を吸収し、芝生の生育を妨げたり、グラウンド上の不陸(地面の凸凹)が生じたりと様々な弊害を生む。そんな光景をしばしば目にする。
記念植樹の代わりに、クラブハウスにホールインワンのプレートボードを設置して敬意を払う。あるいは達成者が記念品の寄贈を申し出たら、ゴルフ場が木製の3人掛けベンチを用意して、寄贈プレートを背面に設置する。これはスコットランドの風習で、筆者のお勧めだ。