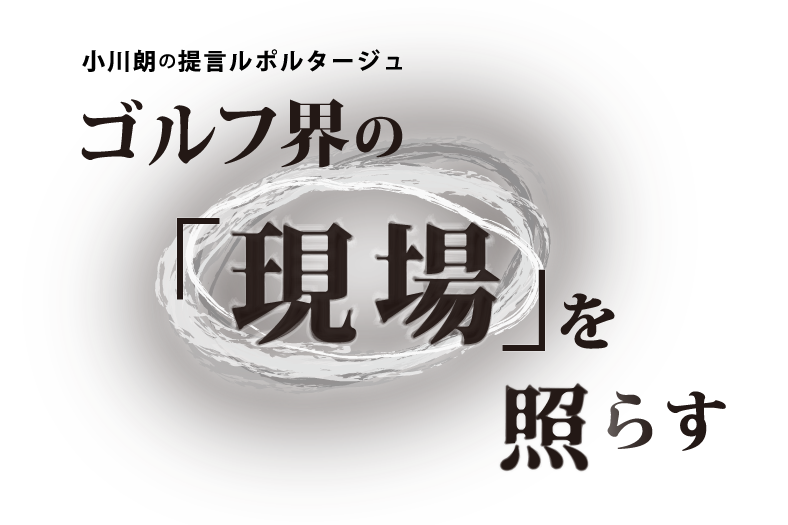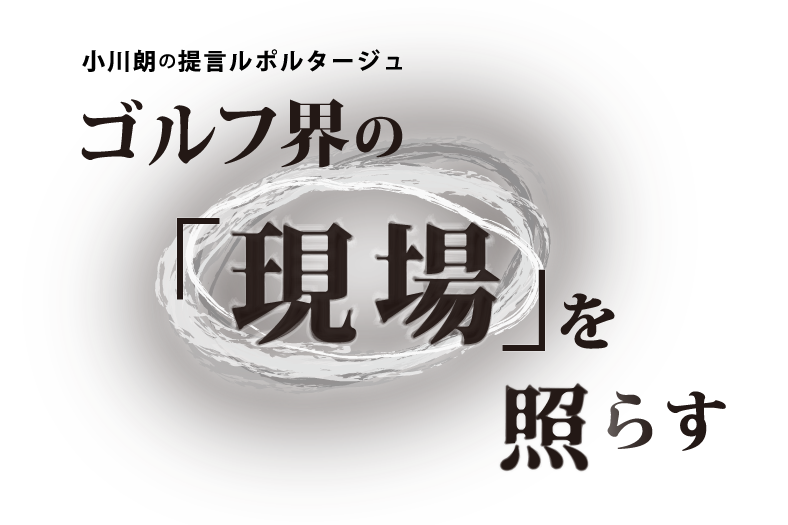ラウンド後の一般ゴルファーから20円~70円徴収、「ゴルフ振興金」の闇
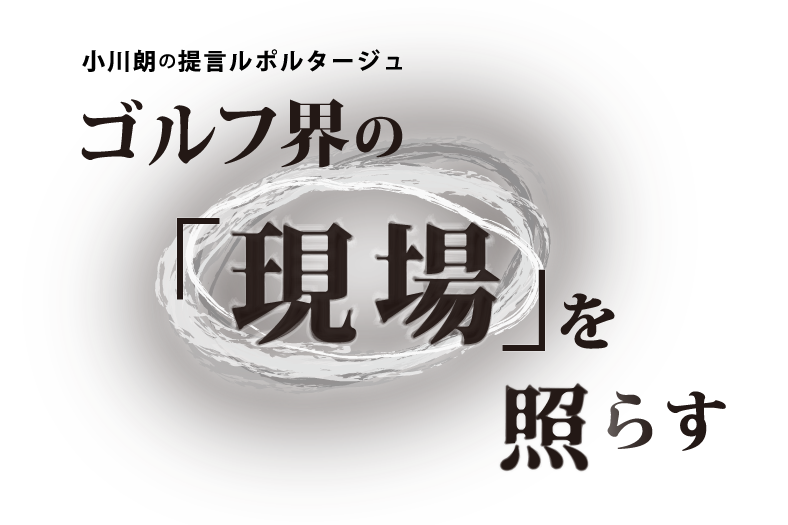
月刊ゴルフ用品界2016年7月号掲載
なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
「誰に断ってあんた、そんなことを調べてるんだ?」。あるゴルフ連盟の事務局長から、ドスの効いた声で脅された。「そんなこと」、とは巷間「ゴルフ振興金」と呼ばれているカネの流れだ。
47都道府県のうち7割を超える競技団体が、1ラウンドあたり20円から70円をプレー後のゴルファーから徴収している。少額のため、これまで問題視する声は少なかった。
しかしトータルすれば10億を超えるこの金が公開されないまま闇へと消えているとしたら――。
あなたは許せる?
6月4日、土曜日。記者は北海道から沖縄まで、各県に存在するゴルフの競技団体に電話取材していた。その過程で取材対象から暴言を浴びせられた。以下はそのやりとり。
Y県S理事事務局長(以下S):もしもし?
記者:はい、小川です。ああ、どちらの県のゴルフ連盟の方ですか?
S:どちらのって、誰に断ってあんた、そんなこと調べてんだ?
記者:ああ、メッセージで残したゴルフ振興金のことですね。えー、こちらはゴルフ用品界という月刊誌で連載している小川と申します。今、ゴルフ振興基金と呼ばれているものを取材してまして。どちらの県の方ですか?
S:Y県。こっちは留守番電話に入ってたから電話してんの。
記者:ああ、初めて見た番号だったので、お聞きしました。あの、ゴルフ振興基金についてお話をうかがいたいのですが。
S:ゴルフ振興基金? まだ去年、入ったばかりで、よく分からない。今日は休みだからさ、週明けに電話してよ。
記者:ああそうですか。では、またかけ直します。
34年の記者歴で、いきなり恫喝されたのは初めてだった。どうやら組織によっては、調べてはいけない案件であることは確かのようだ。
ここで〝振興金〟について見て行こう。47都道府県のうち、実施していないのはわずかに12団体だから、かなりの広がりと言っていい。値段は富山、広島が最高額で70円、最低額は20円と幅がある。
しかしプレー代に占める割合は非常に小さいため、これに気づくゴルファーはさほど多くない。標準税率800円、制限税率1200円のゴルフ場利用税にくらべれば微々たるもの。その利用税にすら異を唱えるゴルファーが少ない現実をみれば、「取ったもの勝ち」状態となっているのも無理ないか。
国体が隠れ蓑に
こうした振興金ができたキッカケのひとつに、国民体育大会がある。「○○国体を成功させよう」をスローガンに「国体準備協力金」という名目でスタート。国体を開催するにも、選手の育成・強化にも金がかかるから一般ゴルファーからいただこう、というワケだ。
今年(2016年)国体を開催する岩手も、ご多聞に漏れず国体協力金という名称で平成25年4月1日から30円を徴収している。
これに東北ゴルフ連盟も20円を上乗せしており、ゴルファーの負担は50円となる。ちなみに関西は30円、四国は10円、九州は25円をさらに追徴し、府県との「2階立て」の構造となっている。
こういうパターンが非常に多い。国体をうたい文句に「30円や50円ならいいだろう」と安易にスタートし、「宴の後」も制度自体が名前を変えて残る。せっかくこんなにいい集金システムが出来上がっているのに終わったからと言って今更手放すのは惜しいからだ。
開催県にとって国体は県の競技レベルを上げる絶好のチャンス。一方で好成績を挙げるための強化費をどこから捻出するかは頭の痛いところだろう。沖縄では平成8年から、ゴルフ競技支援を目的とした「スポーツ振興協賛金」(ゴルフ募金)がスタート。
しかし実際はゴルフ場で徴収した20円はいったん沖縄県体育協会に入り、その半分しかゴルフ協会に回らなかった。平成25年まで体協とゴルフ協会で5:5の形を続けたが、26年に体協3:ゴルフ協会7の割合に移行。昨年からゴルフ協会に「沖縄県ゴルフ振興協賛金」という名目で、すべてがゴルフ協会へと入るようになった。
そもそもゴルファーから集めた金が、沖縄のようにゴルフ以外のスポーツに回るのは筋違い、と感じる人もいよう。また、ビジターから集めた金が、メンバーシップのゴルフ場のために使われるケースも散見され、これも考えてみればおかしな話だ。
実際、集めた金が正しく使われているか、地区によっては定かでない。こうした問題があるにもかかわらず多くの団体がその使途を公開していない。金額が少ないせいで文句がこないのをいいことに、好き勝手している感は否めない。
中国地方のあるゴルフ協会に「使途の内容を記載した資料を閲覧は可能ですか?」と尋ねると「何で見ず知らずの人にそんな資料をみせる必要あんの? こっちまで来てくれたら見せてあげるよ(笑)」と軽くあしらわれてしまった。
取材目的でこの有様だから、一般ゴルファーが真相を知るために超えるべきハードルは相当高い。
「クリーン」が売り物の群馬
こうしたいい加減なスタンスを逆手に取り「クリーンにやって行こう」という強烈なメッセージを旗印にスタートしたのが「一般社団法人 群馬県ゴルフ振興基金」だ。
現在は県内の32コースが加盟。昨年(平成27年)の4月1日からプレー時に30円の「ゴルフ振興金」を徴収している。使途配分もホームページ上で公開。
ゴルフの普及・活性事業に33.3%、人件費や事務所使用料の振興費に17.5%、JGA(日本ゴルフ協会)への寄付など県ゴルフ振興金に17.5%、国体への派遣費用であるゴルフ振興費に11.7%、群馬県プロゴルフ界などへの強化支援団体費に10%、県ジュニア育成強化事業に5%、広告宣伝費と予備費に2.5%ずつと、使途配分も公表している。
群馬といえば中嶋常幸、恵利華兄妹や大町昭義、最近では武藤俊憲、矢野東といった有名選手を輩出しているお土地柄。2020東京オリンピックの代表育成も当然視野に入っている。
ただ、これだけクリーンをうたって立ち上げたとはいえ、群馬県内の加盟率は50%と伸び悩んでいる。なぜ同じ数のコースが加盟を見送っているのか。未加盟のコースに話を聞くと「やはりその金の使われ方に、疑問があるから」と本音を明かしてくれた。
「振興金アレルギー」の関係者も群馬には同数いる感じだ。チリも積もれば山となるではないが、少なくとも10億円から15億円と想定される金額が集められているのは確かで、それがゴルファーにハッキリ見える形になっていないのは紛れもない事実だ。
疑惑を払拭するには業界の「ガラガラポン」しかないのかもしれない。