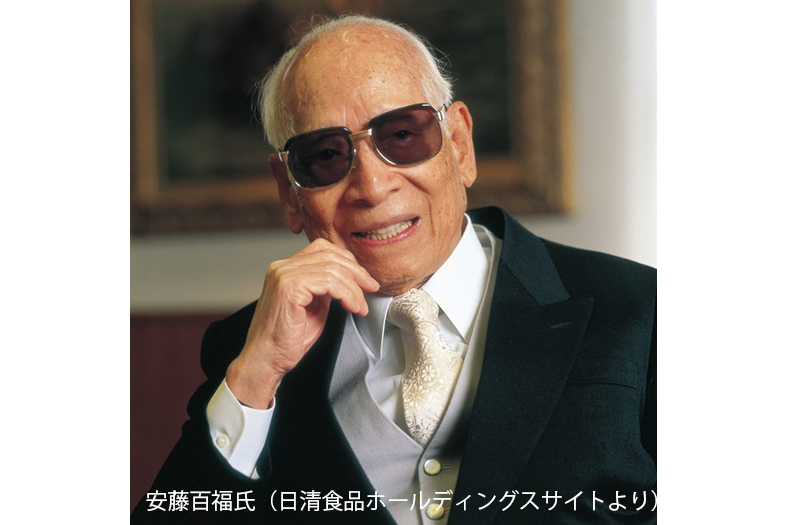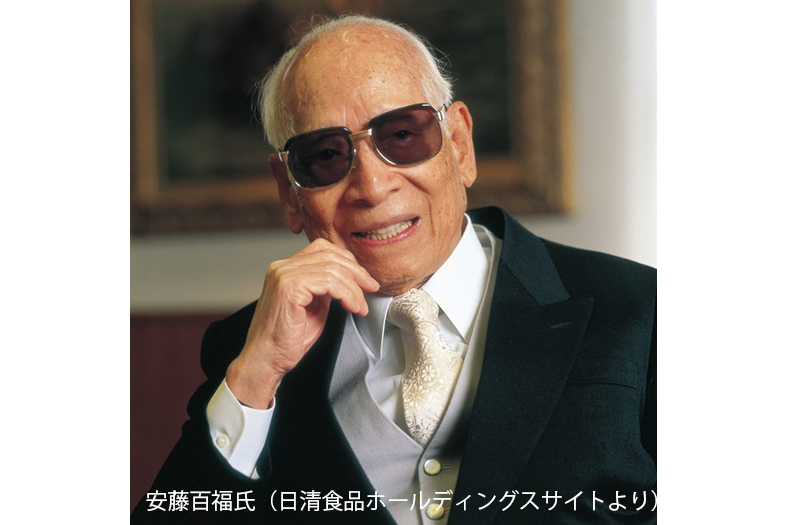戦争直後の生活
私は昭和19年1月、横浜の生まれです。戦中派ということになるのでしょうが、物心ついたころにはもう戦後の生活が始まっていました。小学校に入学したのが昭和25年で、横浜の街はどこもかしこも焼け野原でした。
ぶかぶかの半ズボンに自動車のタイヤから作られたゴム靴を履いて遊び回っていた。学校は2部授業で午前中と午後のクラスに分かれていましたので時間は有り余っていました。
焼け跡のくず鉄拾いも大事な遊びでした。何時間もかけて拾い集めたくぎや銅線をバケツ一杯集めてくず鉄商に持っていくと一円くれます。そのお金を握って駄菓子屋に行き、ベーゴマやメンコ、ビー玉などを買うのです。
それからが大事な勝負の時です。買ったベーゴマやメンコを賭けて勝負して、負けたらとられ、勝てば相手のベーゴマやメンコをもらえる。取りっこをするのです。一日の労働を賭けての勝負です。
勝ったときはいいのですが、負けると悔しくて泣きだすこともありました。子供たちはみんな腹をすかして瘦せていた。でも自由気ままに遊んでいたのでとても楽しかった思いが残っています。
クラスの半分の子の父親はまだ戦地から帰っていません。先生も足りず、校舎も足りない。そんな中での小学校生活です。今思うと、現在の途上国の貧しい家庭の子供たちのようだった。
安藤百福さん
そんなころ、関西で安藤百福さんがインスタントラーメンの可能性に気付いていたのです。百福さんは焼け跡でうどんやラーメンをすすっている人たちを見て、ラーメンの底力を感じ、「食」をテーマにその後の人生を賭けることにしたのです。誰もが家で手軽にラーメンを作れないか、と考えたそうです。
その後、紆余曲折があり、1957年に自宅の庭に小屋を建てインスタントラーメンの制作に励みます。「安くておいしいインスタントラーメンを創ればみんなが喜ぶ」その一念で研究を続け、ついに完成します。そして発展の一途をたどることになるわけです。
2000年の冬だったか、百福さんから私に連絡がありました。その年の1月2日、NHKラジオ番組で私が「子供たちの自然体験が不足している。指導者を育て日本中の子供たちに自然体験をさせたい」と話したことを、ゴルフ帰りの百福さんが聴いてらして、話を聞きたい、ということでした。
私は急いで百福さんの住む大阪の池田市に向かいました。百福さんは私の話を熱心に聞いてくださった。
一時間ほどで帰りましたが、帰り際に百福さんは「君たちは良い仕事をしている。私に何かできるか考えてください。また来るように」と、とてもやさしい声で励ましてくださったのです。
それから5年ほど、年一、二回ですが、池田に通いました。インスタントラーメンを創ったいきさつや若者支援のためにスポーツを支援した理由など、何もかもが国民を勇気付けたいという思いであったことをお話しいただきました。
ある時、君はゴルフをするのか、と聞かれ、しません、と答えたら、残念そうに「面白いから始めてごらんなさい」とおっしゃった。百福さんが無類のゴルフ好きだったことは後から気が付いたのですが、あの時ゴルフを始めていればよかったと悔やまれます。
空腹を満たす
腹が減っても食べるものがない。私たちが経験したあの悲惨な状況が世界各地では今も続いている。戦後75年を過ぎて日本では飢餓はありませんが、世界中の多くの人々は飢餓に苦しんでいます。
国連の報告によると、2019年時点で6億8780万人が飢餓状態に陥っています。これは世界人口の8・9%になります。飢餓は年々増えて2018年から19年の間に1000万人も増えています。SDGsでは「2030年までに飢餓をなくす」ことを目標にしていますが、予測では、ゼロになるどころか8億4140万人に増える見込です。
地域別にみると、最も飢餓が多いのはアジアで、3億8100万人が飢餓に苦しんでいます。でもアジアは少しずつ飢餓が減っています。それに対し、アフリカでは2億5030万人が飢餓に苦しみ、2030年には飢餓人口でアフリカがアジアを抜いてしまいそうです。
ゴルフの縁
百福さんが亡くなった後、日清食品の安藤宏基社長から連絡があり、百福さんと約束がなかったか尋ねられ、自然体験の研修センターを創りたいと話していたことを申し上げると、すぐに実行してくださった。そして私にゴルフを勧めてくれた。以来、私はゴルフの面白さにのめり込むことになるのです。
その宏基社長が現在、飢餓を救うためのWFP(国連世界食糧計画)を支援する特定NPO法人国際連合世界食糧計画WFP協会の会長をされています。親子二代にわたって世界の飢餓を救う活動をされているのは素晴らしいことだと思います。
ちなみに日清食品ではゴルフが盛んで、ゴルフを「社技」と呼んでいるそうです。
飢餓をゼロに
SDGsの二番目の目標は「飢餓をなくそう」です。具体的には①飢えをなくし、貧しい人も、幼い子どもも、だれもが一年中安全で栄養のある食料を、十分に手に入れられるようにする②小規模の食料生産者(特に女性、先住民、家族農家、牧畜や漁業をしている人々)の生産性と収入を倍にする③持続可能な食料生産の仕組みをつくり、何か起きてもすぐに回復できるような農業を行う④国際的な約束にしたがって、世界の農産物の貿易で、制限をなくしたり、かたよった取引をなくしたりする…などの目標をあげています。
この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2022年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら