30 by 30
聞き慣れない言葉ですが、「サーティー・バイ・サーティー」と読みます。2030年までに(バイ・サーティー)地球上の陸域、海域の30%(サーティー)を保全しよう、という意味です。
これは、今年の生物多様性条約会議で決定される予定の世界目標値です。2010年に名古屋で開かれた生物多様性条約第10回締約国会議(COP3)では陸域17%、海域10%の保全が目標とされ、「愛知目標」と言われています。日本はこの目標を達成していますが、世界的にみると陸域16・6%、海域7・7%の達成率で、まだまだ目標には程遠く、地球上の自然は破壊され続けています。
このため2021年のG7サミットで陸域海域とも30%を保全することが約束されました。これを受けて今年12月にカナダのモントリオールで行われる第15回締約国会議(COP15)で採決される可能性が高いのです。
そこで環境省が動き始めました。30%達成に向けて、国立公園をはじめとした保護地域の拡張に加え、民間に参加を呼びかけているのです。2023年度から全国で「自然共生サイト」を認定しようという計画です。
この動きについて環境省の奥田直久・自然環境局長にインタビューをしました。
自然共生サイトとは?
[caption id="attachment_74395" align="aligncenter" width="383"]

「ゴルフ場は大きな援軍になる」と語る奥田局長[/caption]
―自然共生サイトに指定されるための条件とは何ですか。
「今考えていますのは、境界が定まっていること、管理する人と土地があること、生き物が健全な状態で生息していることが確認できること、モニタリングなど保全のための管理ができることの4点を基準にしています。今年度中に、こうした場所のモデル的な取り組みを皆さんにいくつかお見せしたいと思っています」
―ゴルフ場が認定される可能性はありますか。
「もちろん可能性はありますよ。今はゴルフ場が里山の保全の役割を果たしているところがたくさんあります。ちょっと頑張ってくれれば、立派な自然共生サイトになるでしょう。ゴルフ場は全国に2200近くあり、その総面積は神奈川県ほどだといわれています。森林はその40%、芝で耕作されていない状況の自然が60%あると聞いていますので、全国のゴルフ場が立ち上がってくだされば、これは大きな援軍になります」
―何か参考になる取り組みがありますか。
「ゴルフ緑化促進会という団体がありますね。この団体が2013年に出版した『生きものの里山をめざすゴルフ場ガイドライン』がとても参考になります。まず、生物多様性を保全するゴルフ場宣言があります。さらに生息地の維持管理計画を作り、実施し、計画の進展具合をチェックし、計画を改善するという4ステップのPDCAが提唱されています。そのほかの内容もかなり高度ですよ。これだけのことをしていただければ合格じゃないでしょうか」
ゴルフ場に呼び掛けたい
―ゴルフ場関係者に一言あれば。
「ゴルフ場は今や里山管理の重要な役割を果たしています。その事実に自信を持ってほしいのです。生物多様性の保全に非常に重要な役割を担っているのだという自負と責任感を持っていただきたいですね。そして、もっと良くしていこうじゃないか、と前向きになっていただけると本当にありがたい。ゴルフ場関係者の皆様が、ゴルフ場は環境面でも最前線に出るんだという意識を強く持ってくだされば、有名なゴルファーも参加してくれるようになるだろうし、本当の意味で環境教育が進んでいくと思います。ぜひ、ご協力をお願いします」
―スキー場なども候補ですか。新潟県の小出スキー場はとても小さなスキー場ですが、周辺の里山を含めてカタクリなど植物のモニタリングを続けています。
「スキー場もゴルフ場もどこも条件は同じです。自然環境を保全するのに熱心なところは可能性がありますね。企業の敷地でもいいですよ」
ゴルフの楽しみを増やす
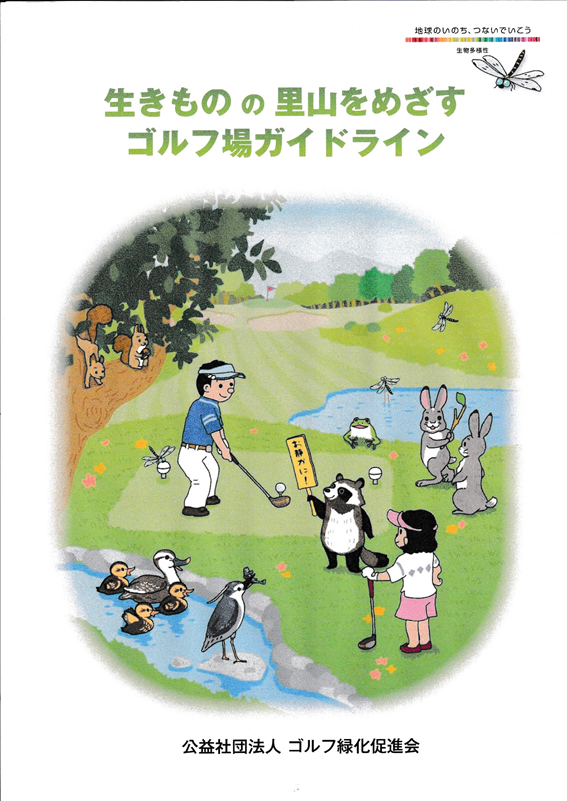
奥田局長のインタビューを終え、ゴルフ場関係者への強い期待を感じました。実際ゴルフ場が里山保全に立ちあがれば、陸域の保全に大きな役割を果たすと思います。
ゴルフ緑化促進会の「ガイドライン」は非常によくできているので、全国のゴルフ場に配布してほしいです。このような指針ができていて、いくつものゴルフ場がそれを実践していることは、あと一息で、流れができるでしょう。
多くのゴルフ場の意識が高まればすぐにでも自然共生サイトが増えそうです。こう言った動きは必ず世間から評価され、ゴルフそのものの人気や社会的ステイタスがさらに高まることと思います。
ゴルフに行って、自然を守ることに共感し、場合によっては寄付もする。自然の中でゴルフそのものを楽しみ、さらには自然を大切にする運動にも協力できる。そして、地域の特産物を買い、子供たちを巻き込んだ自然体験教育のような活動にも協力できる。ゴルフ場の経営そのものが地域の発展などに寄与できるようになれば、ゴルフ人気は高まるはずです。
生物多様性条約
多様な生きものが生きていける状況を担保するために1992年のリオ・サミットで作られた条約です。生物の多様性については①遺伝子レベル②種レベル③生態系レベルの三つのレベルでの多様性を求めている。条約には、現在196の国・地域が加盟している。人間は食料、医薬品、エネルギーなど多方面で多様な自然に依存しているが、現在、猛烈なスピードで生物が絶滅しており、今後10年間が「勝負」だという。
この記事は弊誌月刊ゴルフ・エコノミック・ワールド(GEW)2022年10月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ・エコノミック・ワールドについてはこちら

 「ゴルフ場は大きな援軍になる」と語る奥田局長[/caption]
―自然共生サイトに指定されるための条件とは何ですか。
「今考えていますのは、境界が定まっていること、管理する人と土地があること、生き物が健全な状態で生息していることが確認できること、モニタリングなど保全のための管理ができることの4点を基準にしています。今年度中に、こうした場所のモデル的な取り組みを皆さんにいくつかお見せしたいと思っています」
―ゴルフ場が認定される可能性はありますか。
「もちろん可能性はありますよ。今はゴルフ場が里山の保全の役割を果たしているところがたくさんあります。ちょっと頑張ってくれれば、立派な自然共生サイトになるでしょう。ゴルフ場は全国に2200近くあり、その総面積は神奈川県ほどだといわれています。森林はその40%、芝で耕作されていない状況の自然が60%あると聞いていますので、全国のゴルフ場が立ち上がってくだされば、これは大きな援軍になります」
―何か参考になる取り組みがありますか。
「ゴルフ緑化促進会という団体がありますね。この団体が2013年に出版した『生きものの里山をめざすゴルフ場ガイドライン』がとても参考になります。まず、生物多様性を保全するゴルフ場宣言があります。さらに生息地の維持管理計画を作り、実施し、計画の進展具合をチェックし、計画を改善するという4ステップのPDCAが提唱されています。そのほかの内容もかなり高度ですよ。これだけのことをしていただければ合格じゃないでしょうか」
「ゴルフ場は大きな援軍になる」と語る奥田局長[/caption]
―自然共生サイトに指定されるための条件とは何ですか。
「今考えていますのは、境界が定まっていること、管理する人と土地があること、生き物が健全な状態で生息していることが確認できること、モニタリングなど保全のための管理ができることの4点を基準にしています。今年度中に、こうした場所のモデル的な取り組みを皆さんにいくつかお見せしたいと思っています」
―ゴルフ場が認定される可能性はありますか。
「もちろん可能性はありますよ。今はゴルフ場が里山の保全の役割を果たしているところがたくさんあります。ちょっと頑張ってくれれば、立派な自然共生サイトになるでしょう。ゴルフ場は全国に2200近くあり、その総面積は神奈川県ほどだといわれています。森林はその40%、芝で耕作されていない状況の自然が60%あると聞いていますので、全国のゴルフ場が立ち上がってくだされば、これは大きな援軍になります」
―何か参考になる取り組みがありますか。
「ゴルフ緑化促進会という団体がありますね。この団体が2013年に出版した『生きものの里山をめざすゴルフ場ガイドライン』がとても参考になります。まず、生物多様性を保全するゴルフ場宣言があります。さらに生息地の維持管理計画を作り、実施し、計画の進展具合をチェックし、計画を改善するという4ステップのPDCAが提唱されています。そのほかの内容もかなり高度ですよ。これだけのことをしていただければ合格じゃないでしょうか」
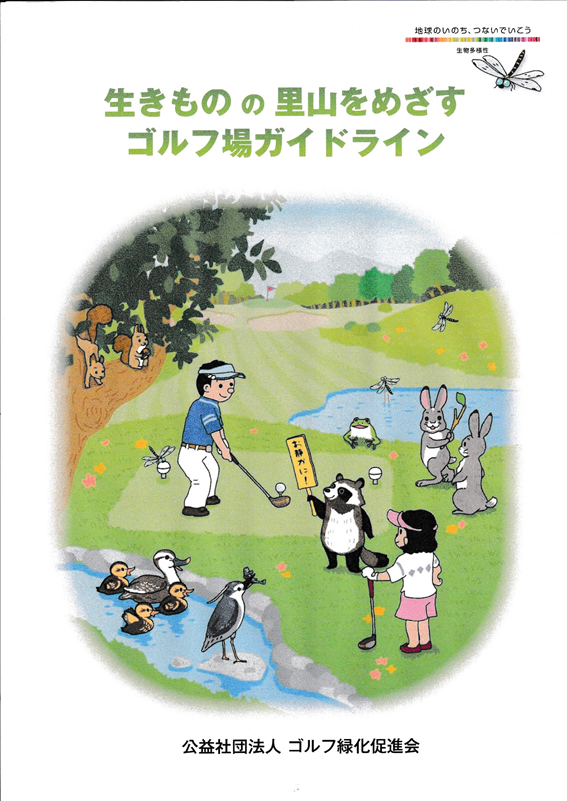 奥田局長のインタビューを終え、ゴルフ場関係者への強い期待を感じました。実際ゴルフ場が里山保全に立ちあがれば、陸域の保全に大きな役割を果たすと思います。
ゴルフ緑化促進会の「ガイドライン」は非常によくできているので、全国のゴルフ場に配布してほしいです。このような指針ができていて、いくつものゴルフ場がそれを実践していることは、あと一息で、流れができるでしょう。
多くのゴルフ場の意識が高まればすぐにでも自然共生サイトが増えそうです。こう言った動きは必ず世間から評価され、ゴルフそのものの人気や社会的ステイタスがさらに高まることと思います。
ゴルフに行って、自然を守ることに共感し、場合によっては寄付もする。自然の中でゴルフそのものを楽しみ、さらには自然を大切にする運動にも協力できる。そして、地域の特産物を買い、子供たちを巻き込んだ自然体験教育のような活動にも協力できる。ゴルフ場の経営そのものが地域の発展などに寄与できるようになれば、ゴルフ人気は高まるはずです。
奥田局長のインタビューを終え、ゴルフ場関係者への強い期待を感じました。実際ゴルフ場が里山保全に立ちあがれば、陸域の保全に大きな役割を果たすと思います。
ゴルフ緑化促進会の「ガイドライン」は非常によくできているので、全国のゴルフ場に配布してほしいです。このような指針ができていて、いくつものゴルフ場がそれを実践していることは、あと一息で、流れができるでしょう。
多くのゴルフ場の意識が高まればすぐにでも自然共生サイトが増えそうです。こう言った動きは必ず世間から評価され、ゴルフそのものの人気や社会的ステイタスがさらに高まることと思います。
ゴルフに行って、自然を守ることに共感し、場合によっては寄付もする。自然の中でゴルフそのものを楽しみ、さらには自然を大切にする運動にも協力できる。そして、地域の特産物を買い、子供たちを巻き込んだ自然体験教育のような活動にも協力できる。ゴルフ場の経営そのものが地域の発展などに寄与できるようになれば、ゴルフ人気は高まるはずです。