月刊GEW 見本誌のお申し込みはこちら
ハッシュタグ「エイジシュート21回の塩じいが語る」記事一覧

若い頃、ハワイでアメリカのレッスンプロのコーチを受けた。そのときにUSPGA発行の「メソッド オブ ティーチング」という本があることを知った。
アメリカのプロゴルフ協会が発行元ということで、なんとなく新鮮で、内容にも一本筋が通っているような気がした。どうしても欲しくなって、その場でコピーさせてもらった。そしてそのコピーは今でも大事な私の教科書だ。
当時はゴルフ記者として、プロにスウィングの技術について話を聞き、原稿を書くことが仕事の中心だった。
取材しながら、気がついたことが一つあった。それは同じスウィングのポイントを説明する場合でも、プロによって、明らかに違ったり、あるいは微妙に差がでたりすることだった。
例えばテークバックのスタートで、あるプロはまっすぐ後方へヘッドを動かすというのに対して、ほかのプロは、インサイドへ引くという類だ。
仕事とはいえ、実は自分でも少しでも上手くなりたいという気持から、プロに聞いた話は、練習場で実際にやってみることにしていたので、こうしたちぐはぐな話になると、どちらのプロの説を選択するか非常に困った。
あるとき知人から「あなたはプロからいろいろ教えてもらえるので羨ましい」と話しかけられたこともあった。だがプロの話は前に述べたように十人十色なので、かえって混乱するケースが多かったことも覚えている。そんなときに見せられたのが「メソッド オブ ティーチング」の本だったのである。
モダンとクラシックの比較
この技術書の執筆者としては、セレステ・ウルリッチ博士(ノースカロライナ大学教授=健康教育学)を始め、人気ツアープロのバート・ヤンシー、ジム・フリック、ボブ・トスキーなどが名を連ね、さらにレッスンプロとして、全米に名が知られていた、クラブプロのビル・ストラスバーグ、ドン・スミスなども加わっている。
またこの本では、近代ゴルフスウィングへの道を切り開いた名手、ハリー・バードンとボビー・ジョーンズの二人の技術を克明に分析し、さらに新しい時代(当時)のバイロン・ネルソン、ベン・ホーガン、ジャック・ニクラスらが、それぞれの時代のスウィングをどう進化させてきているかをわかりやすく比較説明している。そして、その時代の一番新しい技術を〝教科書〟として出版したのである。
この本を読んでいくうちに、前記のように多くのプロを取材し、各人各様の技術の話を聞いても、混乱することはなくなったような気がした。
取材で気になっていたそれぞれのプロの説明に差があるのは当然であり、この「メソッド オブ ティーチング」とは、違った角度から動きを捉えたもので、個人的な問題と割り切ることができたからである。
そこで参考のために、この書の中で、当時、何がモダンで、何がクラシックなのか、その一部をピックアップしてみた。
・テークバックのスタート
〈モダン〉両脚は固定したまま動かない。
〈クラシック〉ヘッドとともに下半身も動き始める。
・バックスウィングのトップ
〈モダン〉少ないヒップターン(上半身と下半身の間に捻れを生じさせる)。
〈クラシック〉からだの右サイドを後方へ回して、大きなヒップターン。
・インパクト
〈モダン〉左手首が折れずに、しっかりとアドレスの形をキープしている。
〈クラシック〉左手首が逆くの字に折れて、手首で強く打つ感じになっている。
こんな形式でアドレスからフィニッシュまで53項目に分けて対比している。
ただ、練習場で知人に「メソッド オブ ティーチング」の話をすると、「あなたはアメリカ人に比べて背も低いし、力も弱い。外国人の書いた技術書が参考になりますか」と質問された。
だが、前出の例文でもわかるように、体力やパワーを必要とする技術的チェックは、この本のどこを探しても見当たらなかった。
この本は、あくまでも万人に向けた教科書であり「ゴルフスウィングとは」という、技術の基本を客観的に明示したものであるからだ。
成功したゴルフスクールの一因
昨年の暮れに大掃除をしていたとき、古い日本のゴルフ雑誌をペラペラとめくっていたら、アメリカのゴルフ評論家トム・クィーン氏の「200年の歴史の積み重ねが(ゴルフの)基本である」という見出しに目が止まった。
トム・クィーンはその特集の中で、あるゴルフスクールの成功の一因を、
「そのスクールを開講する前に何をやったか。なん10年もレッスンをやっている有名なティーチングプロ、長期にわたって立派な成績を残しているツアープロを集めて協議を重ね、年齢、性別に関係なく、体重や背の高低を問わず、すべての人がこれだけは守らなければならない点について討議し、〝基本〟をその通り実行したからです」
と、しっかりとゴルフの基本を提示し、それに基づいて教えたのが、多くのゴルファーに認められたのではないかと説明している。
日本にもアメリカPGAが発行したような基本に基づいた教科書があれば、世の迷えるゴルファーたちにとって、大いなる助けになるのではないか。 (完)
タイトル 万感込めた「退会」の通知
セントアンドリュースの近くにスコッツクレーグ・ゴルフクラブがある。1996年夏、セントアンドリュースのプロに連れられて、仲間と一緒にこのコースでゴルフを楽しんだ。その後、ここのメンバーと我々の訪問チームで対抗戦などもやってきたりした。
ある時、仲間の数人とキャプテン室に呼ばれ「このクラブの海外メンバーに承認された」と報告を受けた。その後、スコットランドを訪れるごとに、このメンバーコースでプレーを楽しんだ。友人もできた。だが70歳を過ぎたあたりから、さすがにスコットランドへの長旅に恐れをなし、訪問の機会もなくなった。80歳を機に残念ながら退会の通知を送った。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2021年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

アメリカの専門誌に載っていたジョン・スウィルの「スタンドトール」の記事を読んでハッと気がついた。内容は「背中を丸めずに、大きく構えるアドレス」という特集だった。
本来ならアドレスの写真を見ただけで見逃すところだったが、最近ショットがよくないのは、構え方に原因があるのではないかと、うすうす感じていた矢先だったので、この特集に目が止まった。
80歳を過ぎた頃からフェアウェイウッドやアイアンショットでボールの頭を叩くミスが目立つようになった。原因は全くわからず、友人に相談したら、「目が悪くなったからだよ」とそっけなくかわされた。
確かに目も悪くなったし、足腰も弱くなった。こんな友人の言葉にも、抵抗なくそのまま受けいれられるようにもなった。
しかしスウィルの特集を読んでいくうちに、今の〝トップ病〟は、知らないうちに背中が丸くなっているアドレスの姿勢が、原因ではないかと確信するようになった。
というのも、この記事を発表したJ・スウィルが、
「構えたときに背中が丸くなっていると、スウィング中のスムーズで力強い体の回転ができなくなる。そのためにインパクトでヘッドスピードが落ちたり、ダフリやトップといったミスを招いたりする恐れがある」
と丸い背中のアドレスが、ショットに及ぼす影響について、こう教えていたからである。
スタンドトールの勧め
「高く立て」といっても、膝や腰を伸ばして、直立に近い姿勢をとるわけではない。J・スウィルは、アドレスの正しい姿勢について、次のように説明している。
「丸くなる背中を抑えるためには、上体を前傾させるときに腹からではなく、腰から折るようにする。次に両膝を軽く曲げ、お尻を後方へ突き出すことである」
実際にこの方法でやってみると、背骨がまっすぐに伸び、重心がピタッと両足の土踏まずの中心に落ちる感じだ。このために押されても引かれてもビクともしない体勢ができあがる。
同時に背骨をまっすぐに伸ばしているせいか、高い姿勢で構えているイメージも湧いてくる。
そしてこの姿勢には、何となく懐を深く感じさせる一面がある。そしてJ・スウィルもいっているように、肩が今まで以上に回りやすくなった感じもある。
最近のアメリカのゴルフ専門誌には、「アスレチック・アドレス」という言葉がよく出てくる。競技者向けの構え方とでもいったらいいのか。とにかく「構え方の見本」となるフォームであることに間違いない。J・スウィルのこの理論も、まさしくアスレチック・アドレスの考え方と同一のもののように受け取れる。
では先端を行くこのアスレティック・スタイルのアドレスを身につけるにはどんな方法があるのか。
レッスンの名手といわれた小松原三夫プロは、愛弟子たちに「地面にある重い石を両手で持ち上げるときの姿勢」と教えていた。
石を両腿の高さまで持ち上げたときの形を見ると、両膝がわずかに曲がり、お尻は後方へ突き出た形になる。そして前傾している背骨は首からお尻までまっすぐに伸びている。
またアメリカのレッスンプロV・J・トロリオがレッスンする雑誌には、基本的なアドレスの姿勢として、相撲の稽古で、兄弟子が弟弟子に「さあ来い」というように、両足を踏ん張り、胸を広げた写真が使われている。
ずっと前、先輩の相撲担当記者に連れられて、部屋巡りをしたことがある。兄弟子の胸に、両手でぶつかっていく若手力士の姿を見たが、兄弟子の体はビクともせず、仁王立ちのままだったのを思い出した。
この写真から推理しても、V・J・トロリオの示すアドレスの形が、いかに強固なものであるかがわかった。
さらに「完全なるアドレスの姿勢」と題して、同じくアメリカのレッスンプロ、カルロス・ブラウンがゴルフ雑誌に次のような方法を勧めているのも目にした。
まず、直立してバックルを中にして、両手でベルトをつかむ。そしてその両手を両腿の方へ強く押し下げるというやり方である。
こうすると両膝がわずかに曲がり、背骨はまっすぐのまま、お尻を後方へ突き出すような形になる。
以上、強くてバランスのよいアドレスの姿勢を作る3ドリルを紹介したが、この姿勢における背骨の位置は、ウッド、ミドルアイアン、ショートアイアンで、微妙に変化することも念頭に入れておく必要がある。
昔から「構えたときの顎の位置がダウンスウィングの最低点」という説がある。
それに従えばドライバーの顎の位置はスタンスの中央より右寄り、5番アイアンでスタンスの中央、そしてショートアイアンでは中央よりも左足寄りがそのポイントになる。
実戦では、前記のように基本姿勢における背骨の位置が、クラブによって順次変わることも常に頭に入れて実践していかなければならない。
一般には静止しているアドレスだけに、練習しなくても何とかなるだろうと考えがちだ。しかしアメリカから送られてくる専門誌を見ても、紙面のページ数では、アドレスの項が最も多い。
老いが進むからこそ、これからもアドレスの変化には、特に目が離せないと思っている。(第41回 完)
カヌースティ・ゴルフリンクス 好スコアに乾杯
初めてセントアンドリュースを訪れたとき、小さいが由緒あるホテルの女主人が、オールドコースを終わったばかりのわれわれを玄関先まで迎えてくれた。そして「カヌースティにも行くんでしょう。素晴らしいコースですよ。」と、期待させる言葉を投げかけてくれ、長旅の後のラウンドの疲れもすっ飛んだ。カヌースティも海がすぐ近くまで迫っているシーサイドコースである。むずかしいことで知られているが、とくにそれを感じさせたのは、後半の16番(パー3=245ヤード)、17番(パー4=433ヤード)、18番(パー4=444ヤード)だ。幸運にもこの3ホールを1オーバーで上がって、トータル87というスコアは上出来だった。その夜はホテルで祝杯。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2021年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら
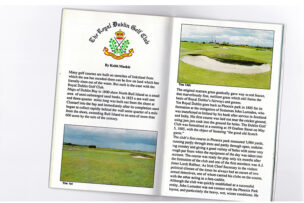
クラブの仲間とは、月に数回一緒にプレーするが、誰いうとなく「年はとりたくないものだ」とドライバーを打った後につぶやく。
お互いに今のクラブで出会った頃は、背骨もシャキッと伸びていたし、歩き方も早かった。飛距離も200ヤードをはるかに超えていた。
それに比べると今は肩が丸くなり、腰も少し曲がり始め、膝の伸びない歩幅で、歩く時間も遅くなっている。こうした体型を見ると、あと何年ゴルフがやれるのか、誰もが心配し始める。
しかし、70歳過ぎてもゴルフをしている人は、月に2、3回は6時間近いコースをラウンドするし、週に何回かは練習場で、100発近いボールを打っているはずだ。
こうした人たちは、ゴルフをしない人たちに比べれば、はるかに健康生活を送っていると思って間違いない。
この環境からすれば、飛距離が落ちたといって、落ち込んだり、あるいはスコアが3、4ストローク悪くなったと、暗い顔をしたりするのは、せっかくのゴルフ人生を短くしてしまうかもしれない。
距離が落ちてがっくりする気持ちはわかるが、健康である限り、将来へ向けて、もう一度、若々しいスウィングを身につけて、ゴルフ人生の再出発へ、目を向けてもいいのではないか。
出っ尻、世界を制す
その第一としてチェックしたいのがアドレスの姿勢だ。70歳を過ぎたあたりから、構え方に変化が見え始める。本人は気がつかないのだが、わずかに曲げた両膝に力がなく、両肩も少し猫背の格好になっているのがそれだ。
レッスンの名手と言われた小松原三夫プロは、冗談交じりに「出っ尻、世界を制す」と、来日した来日した折のジャック・ニクラスのアドレスの姿勢を見てこう評した。
下半身がどっしりし、背筋がまっすぐに伸びて、安定した姿をまのあたりにしての感想である。
では、どうしたらニクラスのようなどっしり型のアドレスを作れるか。小松原プロは「両足を開いて、地面に置いた重い石を持ち上げるときの姿勢」と具体的に示す。
確かにずっしりと重いものを両手で持ち上げる時は、両肩にハリが見られ、お尻も後ろへ突き出た形になる。それに両膝もわずかに曲がった状態だ。この形を構えに採り入れたら、上半身と下半身のバランスが絶妙になり、早いスウィングの動きにも十分耐えられる。どう見ても、若者のような構え方にしか見えなくなる。
自然な動きで振り下ろす
2番目の注意点はダウンスウィングのスタートだ。遠くまで飛ばしたいボールが目の前にあるだけに、クラブを持つ両腕に力が入る。
とくに飛距離が落ち始めたグランドシニアにとって、ここでの切り返しの動きが問題になる。少しでも遠くへ飛ばそうとして、両手、両腕はもちろん、両肩にまで必要以上の力が入ってしまうのだ。
その結果、コックが早く解けるキャスティングの動きが出たり、両肩の早い開きになったり、体重が右足に残ったままになったりというミスが目につくようになる。
実際問題、ダウンスウィングのスタートでは、これまでも①コックを溜めたまま②グリップエンドをボールに向けて③両肩両腕で作る三角形を変えないで‥‥など、いろいろ試みたが、結果としては、ある時はうまくできても、それを定着させるという点では、あまり期待できなかった。
だが、あるときベン・ホーガンの「モダンゴルフ」(ベースボールマガジン社刊=水谷隼訳)を読んでいて、この肩の動きについて、はっと気づかされる箇所があった。
その内容とは次の一文だ。
「両腰の回転がダウンスウィングを始動する。この腰の運動が自動的に両腕と両手とを腰の高さあたりの位置まで引き下ろす」
目からウロコが落ちるとは、このことだろうか。つまりダウンスウィングのスタートは、何も考えなくても、腰をアドレスの位置に戻すだけで、両腕、両手がボールを打つ位置(ほぼ右腰の高さ)まで引き戻されてくるというのだ。
この言葉でダウンスウィングのスタートが非常に楽になった。必要以上の力を入れたがるグランドシニアたちにとっても、大きな意味を持つ言葉に違いない。
アドレスに戻る練習
もう一つの問題点は、インパクトでの伸びあがりだ。これも飛ばそうと思って、力んだときに起こる間違った動きである。
インパクトで体が伸びると、ヒッティングポイントに上下のずれが生じやすい。ドライバーからショートアイアンまで、ボールの頭を叩くトップが目立つようになる。
このポイントも矯正に苦労するところだが、アメリカの有名なティーチング・プロ、クリス・コモ氏の矯正法が、米ゴルフマガジン誌(2013年4月号)に載っていたので引用させていただく。
クラブを持たずに、お尻が壁に軽く触れる位置で前傾し、アドレスの姿勢をとり、さらに腰を回してベルトのバックルを目標に向けたインパクトの姿勢に移る。この時点でも、左のお尻が壁についたままにしておく。やってみればわかるが、前傾姿勢がそのまま残る。これがコモ氏の要約である。
お尻を壁に触れさせていることで、インパクトでも前傾姿勢が保たれるというドリルだ。誰にでもできる簡単な方法である。
「インパクトはアドレスの形に戻るイメージ」とはよく技術書に出てくる言葉だが、この方法だとやすやすと手に入れることができそうな気がしてくる。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら
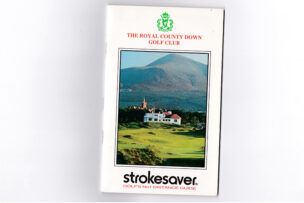
20年ほど前、夏になるとスコットランドのセントアンドリュースを中心にゴルフの旅を楽しんでいた。
そんなある日、R&Aの要人をオールドコースのクラブハウスに訪ねた。クラブハウスのバルコニーに備え付けられていた望遠鏡を覗いていたら、その人が「時々、その望遠鏡で、プレーヤーの動きを見ています。日本から来られた方も目に入ります。みなさんお上手ですよ」とにこやかに話してくれたが、「でも、時々日本のゴルファーは、我々のゴルフとは違うゴルフをしているという話も聞きますよ」と語りかけてきた。振り返ると彼は穏やかな眼をこちらへ向けながら、電話のベルの音でデスクへ歩を進めているところであった。
後で、この言葉が気になっていたので、現地で親しくなったプロにそっと聞いてみた。
それによると「当時、日本の皆さんの中には、フェアウェーにあるボールをピックアップして、置き直す人がいるという声があったのです。それが彼の耳にも入っていたのではないですか」という返事が戻ってきた。
日本人とスコットランド人の違い
ゴルフでは昔から〝ウィンタールール〟というローカルルールがあった。寒さで地面が凍りついていたり、長雨が続いたり、あるいは、乾燥して、芝が弱ったりしている時には、6インチかワンクラブレングスのプレースが許され、それがクラブハウスに張り出されていた。
また昭和30年代から40年代にかけては、ゴルフブームの影響で新設のコースが増え、オープン後1年くらいまでは、芝の保護のために、ワンクラブレングスのプレースというルールを採用していたところがほとんどだった。
そしてその後も、芝の保護を名目にして、このローカルルールの出番は少なからずあった。寒冷の冬、夏の猛暑、梅雨時の長雨など、さらにアップダウンの多い地形などの芝への影響については、コース管理者がいつも心を砕いていた。ウィンタールールの発動回数が増えるのも当然であった。
そしていつの間にかインプレーのボールを拾い上げることに、ある種の慣れを感じてしまった人たちがいたのも確かだ。
こうした背景があって、球を拾い上げて置き直すというルール違反に対して、それほど重大なことではないという潜在意識が、あるいは日本のゴルファーの間に広まっていったと考えられる。
ではどうしてスコットランドの人たちから、このルール違反に「違うゴルフをしている」とまで酷評されてしまうのか。
それはスコットランドでゴルフが始まった頃から、スコットランド人には、どうしても守らなければならない不文律があったからだ。そしてこの不文律は、今も彼らのプレーの中に生き続けているのである。
その不文律とは「ボールはあるがまま打て」(Play the ball as it lies)という言葉である。
この言葉は、ゴルフ規則としてスコットランドで最初に制定された13条のルール(1754年)が作られる前から、プレーヤーの間で絶対に犯してはならない掟として存在していたのだ。
「北方のスパルタ人」
ゴルフの歴史研究で名高い摂津茂和さんは、そのへんの事情を「1964ゴルフ年鑑」(ベースボールマガジン社)で次のように解説している。少し長いが引用させていただくことにする。
「この規定はいかにも峻厳過酷に思われるが、自然を対象とし相手よりもむしろ自然と戦うことを本質的な目標とするゴルフで、もし自由にボールに手をふれることを許せば、もはやその意義がなくなるわけである。それとともに、自然の困難と闘って、克己の精神を養うことが、当時北方のスパルタ人と言われたスコットランド人の目的であったといわれるが、このためボールが、たとえいかに困難な状態になっても、なんらの例外処置もみとめずに、あくまで打つか、さもなければいさぎよくそのホールを放棄(筆者註=当時はマッチプレーのみ)しなければならなかったのである」
ティーから打たれたボールは、ホールアウトするまで絶対に手を触れてはならないという背景には、勇猛果敢なスコットランド人の国民性があったと摂津さんは分析している。
その人たちが日本人のボールをピックアップするゴルフを受け容れられないというのは、当然といっていいかもしれない。
ボールを拾い上げている日本人を見れば、違うゴルフをしていると思われても仕方がなかったのである。
摂津茂和さんは自著「ゴルフ名言集」(鶴書房)で
「ゲーム精神が旺盛であれば、ゴルフ規則は不要である」
と、アメリカゴルフ協会初代副会長チャールズ・マクドナルドの言葉を採り上げている。
その中で、アメリカでもゴルフが行われていた初期には「ボールはあるがまま打て」というゴルフの伝統精神が身につかず、各ゴルフクラブは、ローカルルールでボールのプレースを許す条項を作ったりしていた時代があったといっている。
スコットランドでゴルフを習得したマクドナルドは、自ら範を示すためにいかなる場合も、伝統精神であるボールには一切手を触れず、あるがまま打って、終生これを実行したと同書で伝えている。
どんな事情があれ、ゴルフの根幹にある「あるがまま」の大原則を頭に入れて、いさぎよいゴルフを心掛けてプレーしたいと思う。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年9月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら
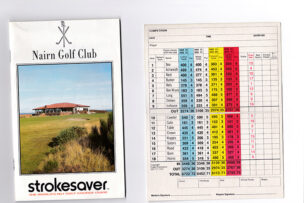
クラブの仲間とは、月に数回一緒にプレーするが、誰いうとなく「年はとりたくないものだ」とドライバーを打った後につぶやく。
お互いに今のクラブで出会った頃は、背骨もシャキッと伸びていたし、歩き方も早かった。飛距離も200ヤードをはるかに超えていた。
それに比べると今は肩が丸くなり、腰も少し曲がり始め、膝の伸びない歩幅で、歩く時間も遅くなっている。こうした体型を見ると、あと何年ゴルフがやれるのか、誰もが心配し始める。
しかし、70歳過ぎてもゴルフをしている人は、月に2、3回は6時間近いコースをラウンドするし、週に何回かは練習場で、100発近いボールを打っているはずだ。
こうした人たちは、ゴルフをしない人たちに比べれば、はるかに健康生活を送っていると思って間違いない。
この環境からすれば、飛距離が落ちたといって、落ち込んだり、あるいはスコアが3、4ストローク悪くなったと、暗い顔をしたりするのは、せっかくのゴルフ人生を短くしてしまうかもしれない。
距離が落ちてがっくりする気持ちはわかるが、健康である限り、将来へ向けて、もう一度、若々しいスウィングを身につけて、ゴルフ人生の再出発へ、目を向けてもいいのではないか。
出っ尻、世界を制す
その第一としてチェックしたいのがアドレスの姿勢だ。70歳を過ぎたあたりから、構え方に変化が見え始める。本人は気がつかないのだが、わずかに曲げた両膝に力がなく、両肩も少し猫背の格好になっているのがそれだ。
レッスンの名手と言われた小松原三夫プロは、冗談交じりに「出っ尻、世界を制す」と、来日した折のジャック・ニクラスのアドレスの姿勢を見てこう評した。
下半身がどっしりし、背筋がまっすぐに伸びて、安定した姿をまのあたりにしての感想である。
では、どうしたらニクラスのようなどっしり型のアドレスを作れるか。小松原プロは「両足を開いて、地面に置いた重い石を持ち上げるときの姿勢」と具体的に示す。
確かにずっしりと重いものを両手で持ち上げる時は、両肩にハリが見られ、お尻も後ろへ突き出た形になる。それに両膝もわずかに曲がった状態だ。この形を構えに採り入れたら、上半身と下半身のバランスが絶妙になり、早いスウィングの動きにも十分耐えられる。どう見ても、若者のような構え方にしか見えなくなる。
自然な動きで振り下ろす
2番目の注意点はダウンスウィングのスタートだ。遠くまで飛ばしたいボールが目の前にあるだけに、クラブを持つ両腕に力が入る。
とくに飛距離が落ち始めたグランドシニアにとって、ここでの切り返しの動きが問題になる。少しでも遠くへ飛ばそうとして、両手、両腕はもちろん、両肩にまで必要以上の力が入ってしまうのだ。
その結果、コックが早く解けるキャスティングの動きが出たり、両肩の早い開きになったり、体重が右足に残ったままになったりというミスが目につくようになる。
実際問題、ダウンスウィングのスタートでは、これまでも1)コックを溜めたまま2)グリップエンドをボールに向けて3)両肩両腕で作る三角形を変えないで‥‥など、いろいろ試みたが、結果としては、ある時はうまくできても、それを定着させるという点では、あまり期待できなかった。
だが、あるときベン・ホーガンの「モダンゴルフ」(ベースボールマガジン社刊=水谷隼訳)を読んでいて、この肩の動きについて、はっと気づかされる箇所があった。
その内容とは次の一文だ。
「両腰の回転がダウンスウィングを始動する。この腰の運動が自動的に両腕と両手とを腰の高さあたりの位置まで引き下ろす」
目からウロコが落ちるとは、このことだろうか。つまりダウンスウィングのスタートは、何も考えなくても、腰をアドレスの位置に戻すだけで、両腕、両手がボールを打つ位置(ほぼ右腰の高さ)まで引き戻されてくるというのだ。
この言葉でダウンスウィングのスタートが非常に楽になった。必要以上の力を入れたがるグランドシニアたちにとっても、大きな意味を持つ言葉に違いない。
アドレスに戻る練習
もう一つの問題点は、インパクトでの伸びあがりだ。これも飛ばそうと思って、力んだときに起こる間違った動きである。
インパクトで体が伸びると、ヒッティングポイントに上下のずれが生じやすい。ドライバーからショートアイアンまで、ボールの頭を叩くトップが目立つようになる。
このポイントも矯正に苦労するところだが、アメリカの有名なティーチング・プロ、クリス・コモ氏の矯正法が、米ゴルフマガジン誌(2013年4月号)に載っていたので引用させていただく。
クラブを持たずに、お尻が壁に軽く触れる位置で前傾し、アドレスの姿勢をとり、さらに腰を回してベルトのバックルを目標に向けたインパクトの姿勢に移る。この時点でも、左のお尻が壁についたままにしておく。やってみればわかるが、前傾姿勢がそのまま残る。
これがコモ氏の要約である。
お尻を壁に触れさせていることで、インパクトでも前傾姿勢が保たれるというドリルだ。誰にでもできる簡単な方法である。
「インパクトはアドレスの形に戻るイメージ」とはよく技術書に出てくる言葉だが、この方法だとやすやすと手に入れることができそうな気がしてくる。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら
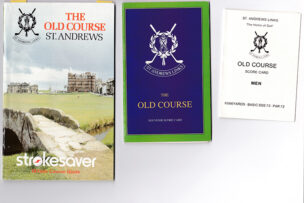
今年は新型コロナウイルス禍のために、内外のツアー競技をTVで見ることはできなかった。去年の今頃は、アメリカツアーでの選手の優勝争いはもちろん、スウィングの技術にも目を光らせる日が続いていた。
その中で特に目を引いたのが、トッププロたちのショットに入る前のあるルーティンだった。
素振りをする人、構える前に小刻みにヘッドを揺らす人、あるいは全く何もしないですぐ構えに入って、そのままショットする人など、まさに多種多様であった。
ただその中で綺麗なフォームで知られるジャステン・トーマスや強打のダスティン・ジョンソン、さらにタイガー・ウッズなどが、これまでプロの間では、ほとんどお目にかかれなかったルーティンが印象に残っている。
それはアドレスしたら、実際にボールを打つ時と同じようにトップまでバックスウィングをしていき、そこからダウンスウィングを始めて、両手が右膝の高さに達したところで止める、という動きである。
実際のショットのために、両手の通り道を確認するかのような動作に見えた。前述のようにこの動きはこれまでプロの間では、あまり目にすることはなかった。むしろトップから振り下ろす際の軌道確認は、ビギナーに多く見られる動きであったように思う。
今も昔も難問中の難問
では、アメリカツアーでもスターといわれるプロ達が、なぜビギナーと似たルーティンを採り入れているのか。
まず単純に、世界のトップランキングを争うようなプロでも、ダウンスウィングの軌道をしっかりと確かめるためではないかと考えた。言い換えれば、〝世界のプロ〟にとっても、このダウンスウィングのスタートが、一番間違いを起こしやすい箇所と思っていて、慎重になっているからではないかと感じ取ったのである。
一介のアマチュアゴルファーに過ぎなかった私も、長い間、プレーをしてきて、ダウンスウィングのスタートの部分では、いろいろなアドバイスを聞いたり読んだりして、一生懸命練習をしてきた。だが、あまりにも問題点が多く、今でもすっきりと振り切れていることはなく、迷いの多いポイントと感じている。
私の手元に「ゴルフ問答読本」(日本ゴルフドム社刊 草葉丘人著 昭和13年7月7月10日発行)がある。その中に第一線プロの技術座談会が載っていて、当時のプロ達がどんなイメージでダウンスウィングのスタートを始めていたかを語っている。ちょっと長いが引用してみることにした。
司会者が「ダウンスウィングを始める前の要領は?」という質問に対して、六人のプロが次のように答えている。
石角武夫プロ バックスウィングで捻った左肩を原位置に返す運動を起こすことです。
柏木健一プロ 絶対に手から下ろさない。トップでは左親指でクラブを支えた気持ちのまま左肩、および腰から引き下ろす。
宮本留吉プロ 右踵をまず最初に上げ、同時に左踵を下ろし、グリップを振り下ろすのです。
村木 彰プロ 右肩が前へ出るのを抑え、左足に重心を移す。体を動かさないでスウィングします。
中村兼吉プロ しっかりと左踵のヒールダウンから始めます。
瀬戸島達雄プロ 左肩をトップの位置に置いたまま、腰の捻りから始める。これでヒールダウンを始めれば、クラブが遅れてきます。
太平洋戦争前の話だが、この座談会では、六人が六人とも、ダウンスウィングを始めるときの要領については、それぞれが違う考えを持っていたことがわかる。そしてこうした話は現代でも、よく聞く言葉で、この点に関しては、昔も今もあまり変わってはいない。
腰の回転で始動
私もダウンスウィングのときは、前記六人のプロの秘法はもちろん、他にも「グリップエンドをボールに向けて」とか「まず左足へ体重を移す」など、あらゆる方法でテストしてきた。だが、「これだ!」と確信できる方法には、出会うことなく過ごしてきた。
難しさに負けたわけではないが、まあ、生涯の課題にしておくことにしようと考えていた。そんなとき、ベン・ホーガン著の「モダンゴルフ」(ベースボールマガジン社刊=水谷準訳)を読んでいて、はっと気がつく文章に出会った。
今までこの本は5回も6回も熟読していたはずなのに、読み過ごすというミスがあったのだ。その箇所とはこうだ。
「両腰の回転がダウンスウィングを始動する。この腰の運動が自動的に両腕と両手とを腰の高さあたりの位置まで引き下ろす」
これはダウンスウィングのスタートのイラストにつけられた説明文である。
ベン・ホーガンによれば「腰を正しく回転させてダウンスウィングをスタートさせることがダウンスウィングそのものなのだ」といっている。つまりトップから両手(両腕)を振り戻すのがスタートではなく、腰を巻き戻す動きをした瞬間がダウンスウィングの始まりだというのである。
さらにこの腰の回転で体重が右足から左足へ移動し、両腕の通り抜けもスムーズにし、目標に向かって力を絞り出させる、そしてこれが強力なヒッティングの位置につかせる、などダウンスウィングの重要な動きを自動的にやってくれるということにも触れている。
冒頭に挙げたジャステン・トーマス、ダスティン・ジョンソン、タイガー・ウッズなどが見せているショット前のルーティンも、解けたような気が気がした。今はベン・ホーガンのいう腰の回転が彼らの頭の中にあるからだと思えてならない。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年5月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

ボールを打たずに2ヶ月半が過ぎた。新型コロナウイルスの感染を抑える〝3密〟を忠実に守ったのと、この感染症の恐ろしさも理由の一つだ。
アメリカツアーも日本のツアーも中止になった。いつもならTVに見入っているのに、毎日の過ごし方が大きく変わってしまった。退屈しのぎに古いアメリカのゴルフ雑誌を読んでいたとき、ライダーカップの戦績に目が止まった。
ライダーカップが、イギリス対アメリカの対抗戦で始まったのは、1927年のアメリカ大会(マサチューセッツ州ウォーセスターCC)からで、1年おきの開催だ。第1回大会から両陣営の熱戦で盛り上がった。選手が18番グリーンに上がってくるたびに、大きな歓声が沸き起こる。
そのライダーカップは、新型コロナウイルスの感染が収まれば、今年は9月25日からアメリカのウィスリングストレイツCC(ウィスコンシン州)で行われる。実現すれば世界のゴルフ界再興へ、大きな弾みになるに違いない。 (実際には2021年に延期された)
アメリカの勝利から始まった対戦は、44回大会まで交互に2勝2敗で進み、その後のライダーカップ戦に大きな期待を残してのスタートとなった。
しかし、続く1935年大会から1955年(1935、1941、1943、1945年の大会は中止)まで、米チームは7連勝と勝ち進んだ。次の1957年はイギリスに敗れたものの、その後の1959年からもアメリカの連勝が始まり、1983年まで13連勝。あまりのことにイギリス陣営は、1973年から新しくアイルランドを加えたが、アメリカの勢いを止めることはできなかった。
勝てないイギリスの弱点
なぜイギリスは、アメリカに勝てなくなってしまったのか。
1966年、米ゴルフ雑誌にイギリスがライダーカップに勝てない原因として、アメリカツアープロ出身の評論家ビクター・イーストが、それは両チームのスウィング技術の差にあるとして、その記事を掲載している。興味深いポイントなので、比較している内容の一部をご紹介しよう。
バックスウィングスタート
(米)両腕と体を一体にして、クラブフェースをスクエアにキープしながらテークバック。
(英)両前腕を右へ回しながらオープンフェースでスタート。
ダウンスウィング
(米)スクエアフェースのまま、ボールへ振り下ろす。目標へ低く長く、自然の動きで振り抜く。
(英)両腕を捻り戻して、スクエアなフェースにしてインパクト。
インパクト
(米)両手首を返さず、両腕を伸ばしたまま高いフィニッシュへ。
(英)インパクトでは、手首を返して、左手の上に右手が重なる動きで打つ。低いフィニッシュ。
これが米・英のスウィング技術の比較のほんの一部である。
この時点でアメリカの手首を制御し、ボディターンとスウィング軌道を重視した打ち方に対して、オープンフェースのバックスウィングから、ダウンスウィングでは再びスクエアに戻すリスト中心の打法という、英国型の打ち方の差が浮かび上がる。
やはり「遠く、正確に」という永遠の目標に近づくという点では、アメリカが一歩も二歩も先行している感じが否めない。
こうした分析の結果で「この差がライダーカップに現れた」とV・イーストは発表したのである。
進化を続けるアメリカ打法
またアメリカのプロゴルフ協会は、1972年にレッスンの教科書として「METHODS OF TEACHING」を発表。その中でスウィングをモダンタイプとクラシックタイプの二つに分け、進化前と進化後のスウィング分析を行っている。指導者たちに技術の進化を理解させ、レッスンに際して正しい方向性を指示したものとみられる。ここでは新旧57項目について対比させているが、その幾つかを取り上げてみよう。
バックスウィング
(新)極端に少ない両脚の動き。
(旧)両脚はテークバックとともに右へ回して、回転を助ける。
トップ オブ スウィング
(新)シャフトが飛球線と平行。
(旧)シャフトが目標の右に向いて、飛球線と交差する。
ダウンスウィング
(新)両肩をトップの位置に残し、下半身を左へ平行に移行。
(旧)体重移動よりも両腰をほぼその場で回転。
この対比を見ると1966年のビクター・イーストの研究発表よりも、さらに進化した内容が読み取れる。
例えばバックスウィングの新しい方法では「両脚の動きを少なく」とあるが、これなどは進化した現在の「下半身を止めて上体を捻ることによって、コイルの強さをアップさせる」という基本につながる動きといえる。
このことはまたトップで両手が高く上がりすぎ、ミート率に問題を残すロングスウィングから、より正確さを求めるショートスウィングへ道を開くポイントになったとも考えられる。
ライダーカップは米国対欧州連合になった1979年から前回の2018年まで、欧州12勝、アメリカ8勝という結果を残している。さすがに多国籍の前には、アメリカも苦戦かと見える。
だが、近年ではゴルフもグローバル時代を迎え、イギリスを始め欧州の選手たちも米ツアーに参加。アメリカの新技術に追いつけ、追い越せと、技を磨く機会が多くなった結果とも考えられる。技術革新への道は年々激しくなる一方だが、日本も遅れてはならない。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

カラミティ・ジェーンは古い人なら知っているはずだが、ヒッコリーシャフトのパターである。私がゴルフ記者になりたての頃、師と仰ぐ水谷準さん(故人=推理作家、ベン・ホーガン著「モダン・ゴルフ」の訳者)もこのパターに魅せられた一人だった。
カラミティ・ジェーンとは、戦前のアメリカ西部劇のヒロイン。その容姿もさることながら、抜く手も見せず、一発で悪漢をやつけるガン捌きに、身も心も痺れた日本のファンは多かったという。
水谷さんも「カラミティ・ジェーン」とバックフェースに銘が入ったパターを使っていた。そして、水谷さんは普及版だったかもしれないが、このパターをいつも大切に扱った。その頃はパターにヘッドカバーをつける人は少なかったが、水谷さんは自分で
編んだ毛糸のカバーをつけて、バッグに入れていたほどだった。シャフトのヒッコリーも、木目がピカピカと光るほど磨きあげていた。
そして、このパターはアメリカのゴルフ史上、真っ先に語られる人物といわれる、ボビー・ジョーンズがこよなく愛したパターであったことも、水谷さんから教えてもらった。だが、時代が変わるにつれて、そのパターにもお目にかかれなくなったし、記憶としても忘れかけていた。
ところが最近、アメリカの古いゴルフ雑誌(1993年米ゴルフマガジン)に目を通していたら、いつか水谷さんが持っていたのと同じカラミティ・ジェーンとともに、ボビー・ジョーンズのパッティング写真が目に入った。
このとき、最近、カラミティ・ジェーンが話題にのぼっていないし、どうなってしまったのだろうという気持と、あの球聖といわれたボビー・ジョーンズと、どのようにこのパターが結びついたのか。俄然、興味が湧いた。
B・ジョーンズの人生を変えた1発の試打
カラミティ・ジェーンとボビー・ジョーンズとの仲を取り持ったのは、アトランタにあったジョーンズの自宅に近いゴルフ場で、レッスンプロをしていたジム・メイドンであった。
ジョーンズは1923年の全米オープンを前にした月曜日、近くのナッソーCCで、ジムとスチュワートのメイドン兄弟、それと同クラブのメンバーの4人で、9ホールをプレーしていた。
そしてラウンドの後、その頃ジョーンズがパッティングについて、大変な苦境に立たされているという話がでた。それを聞いたジム・メイドンは、その頃すでにフェースの裏に〝カラミティ・ジェーン〟と彫り込まれていた自分のパターを差し出し「こういうのを持っているけど、ちょっと振ってみるかい」といった。
ジョーンズは近くの練習グリーンに行くと、手にしていたボールを放り投げ、いつものように狭いスタンスで、上体をやや深く傾けながら、9メートル先のホールへストロークした。ボールはグリーン上を滑るように転がって、カップに消えた。
ジョーンズは嬉しそうにカップからボールを拾い上げると、
「こんなパターがあったらいいな」
とパターのヘッドを撫でながらつぶやいた。その言葉を聞いたメイドンは、
「君のバッグに入れておくよ」
と、笑顔を浮かべながらいった。
これがボビー・ジョーンズとカラミティ・ジェーンのペア誕生秘話である。
新パターが支えたメジャー制覇
ジョーンズはカラミティ・ジェーンを手に入れてから、その1週間後に、なんと念願の全米オープンに優勝したのである。この快挙を27年後、前記のアメリカのゴルフ雑誌は「ジョーンズとカラミティ・ジェーンの固い信頼関係は、彼が引退するまで引き裂かれることはなかった」と報じている。あたかも1923年の初優勝から、1930年に引退するまで、ボビー・ジョーンズが打ち立てた数々の栄冠は、ジョーンズとカラミティ・ジェーンとの合作であったような書き方をしている。
確かに1923年を境に、引退するまでのジョーンズの活躍には目をみはるものがある。例えばメジャーだけでもその優勝回数は、全米オープン4回、全米アマ5回、全英オープン3回、全英アマ1回に及んでいる。8年間にメジャーを13回も制覇したことになる。
「憐れなほど下手なパットをする」といわれた21歳のボビー・ジョーンズが、レイ・ミルズから、トラビスのモデルへと渡り歩き、カラミティ・ジェーンにたどりついた途端に、まるで人が変わったようにアメリカゴルフ界の頂点に上り詰めた。そして1930年には前人未到のグランドスラムまで成し遂げている。やはりカラミティ・ジェーンが、彼に何らかの力を与えたのではないかと思えてならない。
最後に、ボビー・ジョーンズが愛用したカラミティ・ジェーンとはどんなパターだったのか。
1923年にジム・メイドンから受け継いだカラミティ・ジェーンのヘッドは、L型でややオフセットネックのタイプである。そしてシャフトは前述のようにヒッコリー。グリップは革製でやや長めというのが特徴。
ところがジョーンズは1925年終わり頃にフェースを熱心に磨きすぎて、スウィートエリアをぼやかしてしまい、アメリカのデザイナー、ビクター・イーストに頼んで、全くそのままの複製品を作らせ、2代目カラミティ・ジェーンにつなげた。記録によると、この生まれ変わったカラミティ・ジェーンでの勝利は10回を数えたといわれている。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年3月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

ボールを打たずに2ヶ月半が過ぎた。新型コロナウイルスの感染を抑える3密を忠実に守ったのと、この感染症の恐ろしさも理由の一つだ。
アメリカツアーも日本のツアーも中止になった。いつもならTVに見入っているのに、毎日の過ごし方が大きく変わってしまった。退屈しのぎに古いアメリカのゴルフ雑誌を読んでいたとき、ライダーカップの戦績に目が止まった。
ライダーカップが、イギリス対アメリカの対抗戦で始まったのは、1927年のアメリカ大会(マサチューセッツ州ウォーセスターCC)からで、1年おきの開催だ。第1回大会から両陣営の熱戦で盛り上がった。選手が18番グリーンに上がってくるたびに、大きな歓声が沸き起こる。
そのライダーカップは、新型コロナウイルスの感染が収まれば、今年は9月25日からアメリカのウィスリングストレイツCC(ウィスコンシン州)で行われる。実現すれば世界のゴルフ界再興へ、大きな弾みになるに違いない。
アメリカの勝利から始まった対戦は、4回大会まで交互に2勝2敗で進み、その後のライダーカップ戦に大きな期待を残してのスタートとなった。
しかし、続く1935年大会から1955年(1935、1941、1943、1945年の大会は中止)まで、米チームは7連勝と勝ち進んだ。次の1957年はイギリスに敗れたものの、その後の1959年からもアメリカの連勝が始まり、1983年まで13連勝。あまりのことにイギリス陣営は、1973年から新しくアイルランドを加えたが、アメリカの勢いを止めることはできなかった。
勝てないイギリスの弱点
なぜイギリスは、アメリカに勝てなくなってしまったのか。
1966年、米ゴルフ雑誌にイギリスがライダーカップに勝てない原因として、アメリカツアープロ出身の評論家ビクター・イーストが、それは両チームのスウィング技術の差にあるとして、その記事を掲載している。興味深いポイントなので、比較している内容の一部をご紹介しよう。
<h3>バックスウィングスタート</h3>
<ul>
<li>(米)両腕と体を一体にして、クラブフェースをスクエアにキープしながらテークバック。</li>
<li>(英)両前腕を右へ回しながらオープンフェースでスタート。</li>
</ul>
<h3>ダウンスウィング</h3>
<ul>
<li>(米)スクエアフェースのまま、ボールへ振り下ろす。目標へ低く長く、自然の動きで振り抜く。</li>
<li>(英)両腕を捻り戻して、スクエアなフェースにしてインパクト。</li>
</ul>
<h3>インパクト</h3>
<ul>
<li>(米)両手首を返さず、両腕を伸ばしたまま高いフィニッシュへ。</li>
<li>(英)インパクトでは、手首を返して、左手の上に右手が重なる動きで打つ。低いフィニッシュ。</li>
</ul>
これが米・英のスウィング技術の比較のほんの一部である。
この時点でアメリカの手首を制御し、ボディターンとスウィング軌道を重視した打ち方に対して、オープンフェースのバックスウィングから、ダウンスウィングでは再びスクエアに戻すリスト中心の打法という、英国型の打ち方の差が浮かび上がる。
やはり「遠く、正確に」という永遠の目標に近づくという点では、アメリカが一歩も二歩も先行している感じが否めない。
こうした分析の結果で「この差がライダーカップに現れた」とV・イーストは発表したのである。
進化を続けるアメリカ打法
またアメリカのプロゴルフ協会は、1972年にレッスンの教科書として「METHODS OF TEACHING」を発表。その中でスウィングをモダンタイプとクラシックタイプの二つに分け、進化前と進化後のスウィング分析を行っている。
指導者たちに技術の進化を理解させ、レッスンに際して正しい方向性を指示したものとみられる。ここでは新旧57項目について対比させているが、その幾つかを取り上げてみよう。
<h3>バックスウィング</h3>
<ul>
<li>(新)極端に少ない両脚の動き。</li>
<li>(旧)両脚はテークバックとともに右へ回して、回転を助ける。</li>
</ul>
<h3>トップ オブ スウィング</h3>
<ul>
<li>(新)シャフトが飛球線と平行。</li>
<li>(旧)シャフトが目標の右に向いて、飛球線と交差する。</li>
</ul>
<h3>ダウンスウィング</h3>
<ul>
<li>(新)両肩をトップの位置に残し、下半身を左へ平行に移行。</li>
<li>(旧)体重移動よりも両腰をほぼその場で回転。</li>
</ul>
この対比を見ると1966年のビクター・イーストの研究発表よりも、さらに進化した内容が読み取れる。
例えばバックスウィングの新しい方法では「両脚の動きを少なく」とあるが、これなどは進化した現在の「下半身を止めて上体を捻ることによって、コイルの強さをアップさせる」という基本につながる動きといえる。
このことはまたトップで両手が高く上がりすぎ、ミート率に問題を残すロングスウィングから、より正確さを求めるショートスウィングへ道を開くポイントになったとも考えられる。
ライダーカップは米国対欧州連合になった1979年から前回の2018年まで、欧州12勝、アメリカ8勝という結果を残している。さすがに多国籍の前には、アメリカも苦戦かと見える。
だが、近年ではゴルフもグローバル時代を迎え、イギリスを始め欧州の選手たちも米ツアーに参加。アメリカの新技術に追いつけ、追い越せと、技を磨く機会が多くなった結果とも考えられる。技術革新への道は年々激しくなる一方だが、日本も遅れてはならない。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年7月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

「デーブ・ヒルのフォームは素晴らしく綺麗だが、あっちこっちでカドを立て、よく喧嘩するのでも有名である。つい最近も同伴したヒルはチ・チ・ロドリゲスと大喧嘩をした。(中略)同伴したヒルは『うるさい。人のプレーを邪魔するな』と食ってかかった。相手の言い分が正しくとも、そうあからさまに言われるとチ・チとしても面白くない。プレーが終わっても、しこりが残り二人は犬猿の仲になった」。
これは金田武明さん(故人)が書いた「近代ゴルフの心と技術」(昭和47年/産報刊)の中に出てくる話である。
消えた野球放送の名コンビ
日本でもかつてプロ野球の放送で長い間、名コンビを続けてきたアナウンサーと解説者の仲がまずくなったという噂が流れたことがあった。仮にN放送局Sさんと解説者Kさんとしておこう。
Sさんは本場スコットランドの厳格なアマチュア選手のような趣がある人だった。ゴルフの練習を始めてから1年くらい経ったとき、Sさんと泊りがけで水戸のあるゴルフ場へ出かけた。
彼は車中はもちろん、ホテルでも技術やルール、マナーの話を熱心に質問してきた。
そして最後に「やがてわが局もゴルフを放送する日が必ずやってくる。その日のために、ゴルフ発祥の地であるイギリス人の心を少しでも身につけておきたい。」といった。
一方Kさんには、Sさんとは反対にゴルフについて、よからぬ評判があった。
ある日、顔見知りだった読売ジャイアンツの牧野茂コーチ(故人)と新幹線で一緒になった。
品川に着いたあたりからKさんの話題になった。「Kさんは古いゴルファーで、エチケットやルールについては知り尽くしているのに、申告するスコアはいつも7以上にはならないし、マークしたボールの位置も、打つときには30センチも前になっちゃうんですよ」
こんな具合で話が弾み、終わったのは牧野さんが下車する名古屋駅の近くだった。
牧野さんは「でもKさんは、憎めない人だったですね。得意な話術で、一緒に回っている人をケムに巻いちゃうんです。別所さん(毅彦=元読売ジャイアンツ投手)なんか、そんなKさんとチョコレートを賭けていましたものね」と、笑顔を残して席を立っていった。
SさんとKさんとの間は、ゴルフのプレーぶりを見る限り水と油の関係だったが、しばらくして、二人の息の合った野球放送は、多くの人に惜しまれつつ終わりを告げた。後には「ゴルフが二人の仲を裂いた」という風評が残った。
「我々日本人はどちらかというと喧嘩下手である。例えば上下関係の絆が強く、会議では上役の意見が尊重される。部下は言うべきことを言わずにじっと我慢する。その代わり一度不満が爆発すると、徹底的な喧嘩になり、しこりが残る。(中略)刀を抜いたらどちらかが死ぬという武士の生き方では困る」。前記、金田武明さんの言葉である。
そしてさらに彼は冒頭のデーブ・ヒルとチ・チ・ロドリゲスのような後々まで残る喧嘩もあるが、欧米にはつかみ合い寸前になりながら、すぐケロリと親友関係に戻るさっぱりした喧嘩もあることを教えている。
「1971年の全米オープン(メリオン)で試合の最中『ニクラスみたいなスロープレーは見たことがない』とパーマーが毒づいた。それでもしこりは残さず、その後ナショナルチーム・チャンピオンシップ(ローレルバレー)では二人仲良くペアを組み、見事に優勝している」
と喧嘩の後、元の親友に戻った様子を金田さんは述べている。
プロ野球界両雄の喧嘩
「日本人は喧嘩下手」と金田さんは厳しいが、本当にそうなのか。
塩ジイが新入社員で、ゴルフの編集に従事していた頃のオフに、読売ジャイアンツの川上哲治さんと千葉茂さん、それに会社の役員の4人で千葉カントリー倶楽部の野田コースに出かけた。
プレーが終わってロッカーに入った時、奥の方から川上さんと千葉さんが部屋中響き渡る声で言い合っているのが聞こえた。特に川上さんの声が怒りを含んでいて大きかった。その頃川上さんがジャイアンツのヘッドコーチで、千葉さんが二軍の監督という関係だったと思う。
二人は風呂にも入らず川上さんがオースチン、千葉さんがヒルマンと、それぞれの愛車に乗ってクラブを後にした。私は千葉さんの車に乗せてもらって、日光街道を東京方面に向かった。
千住大橋の袂へ来た時、大勢の警察官が並び、一斉取り締まりであることがわかった。このとき千葉さんの顔色が変わった。免許証を小物入れの中の鍵と一緒にトランクに放り込んだままになって、取り出せなくなっていたのだ。
警官は免許証の提示を求めた。千葉さんはもじもじしながら事情を説明した。そこへ先行していた川上さんが心配してやってきた。千葉さんの免許証が鍵のかかったトランクの中にあるのを知っていたからである。
そうこうしているうちに、帽子に金筋を巻いた、この日の指揮官がやってきた。
「やあどうも、ここで川上さんと千葉さんに会えるなんて…」とニコニコしながら千葉さんに、車をここに置いて帰るようにと指示した。千葉さんは社の車に乗りかえて帰るということで放免になった。
そして二人はいつもの「川さん」「茂やん」の顔で別れた。1時間前にロッカーで激しく言い合ったことなどなかったかのように。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2020年1月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

2005年、ベイヒル・クラブ&ロッジのアーノルド・パーマーのロッカーには、ウッド4本、アイアン10本、使い古したパターが入ったバッグが置かれていた。
76歳を迎えていたパーマーは、すでにツアーを退いていたが、その頃使っていた彼のゴルフバッグの中身が、同年の米ゴルフダイジェスト誌に紹介されている。
それによるとウッドはドライバー、3番ウッド、5番ウッド、7番ウッドの4本。アイアンが2番〜9番までで8本。それにウエッジがPWとSWの2本にパターという内容である。
また同誌によると「私はパターを含めて1万本のクラブを自宅とベイヒルの別荘に置いてある」といっている。おそらく彼のプロ生活の中で使ったクラブ、あるいはテストしたクラブに違いないが、何れにしても、前記15本のクラブは、進化する1万本の中からさらに精選されたエキスみたいな代物だったのではないか。
保存された1万本の数もすごいが、76歳にしての彼の飛距離(下記)にも驚かされる。
<ul>
<li>1W(10°)250ヤード</li>
<li>3W(16°)220ヤード</li>
<li>5W(18°)210ヤード</li>
<li>7W(20°)195ヤード</li>
<li>2I(18°)195ヤード</li>
<li>3I(21°)185ヤード</li>
<li>4I(24°)175ヤード</li>
<li>5I(27°)165ヤード</li>
<li>6I(30°)155ヤード</li>
<li>7I(34°)145ヤード</li>
<li>8I(38°)135ヤード</li>
<li>9I(42°)125ヤード</li>
<li>PW(46°)110ヤード</li>
<li>SW(56°)95ヤード</li>
</ul>
(米ゴルフダイジェスト誌)
という資料がそれだ。
5W、7Wまで入れたパーマーのセット
2005年以前、パーマーがどんなセットを組んでいたかは、資料がないのでなんともいえないが、推測すれば前記番手の中から、5番、7番ウッドが消えて、4番ウッドと1番アイアンが入っていたのではないかと思われる。
なぜなら小さい頃から父親に「力一杯打て!」といわれて育ってきたパーマーの性格にもよるが、パーマーがプロになりたての1950年代から1960年代にかけては、5番ウッド以下のウッドクラブがほとんど世に出ていなかったことも理由の一つである。
その後、5番ウッドは、クリークと呼ばれ、ドライバー、スプーン、バッフィというセットから外れ、7番ウッドとともにハイブリッド風に扱われていた時代があった。
パーマーはアイアンセットでも当時、メーカーのスタン・トンプソン、マクレガー・ミュアフィールド、テーラー・テクニシャンがユーテリティアイアンとして、売り出していた1番アイアンも当然バッグに入れていたと考えられる。
ところが76歳とはいえ、ハードヒットを常に標榜し続けたパーマーが、5番ウッドだけではなく、7番ウッドまでもバッグに忍ばせていたとは、最初は信じられない思いだった。
パーマーはその理由を「5番、7番ウッドは1、2番アイアンよりも打ちやすく、ボールも高く上がる」と説明する。前記のようにパーマーのバッグにはパターを入れて15本のクラブが入っていたが、コースに出るときには、この言葉から状況によって5番、7番ウッドと2番アイアンを使い分けていたのであろう。
顔つきも温和になった76歳のパーマーは、ゴルフのショットにも柔らかさが加わったと、このキャディバッグの中身が物語っている。
5番、7番ウッドを仲間入りさせたこのパーマーのセットは、塩ジイと同じ古いゴルファーが、今でもフェアウェイウッドをバッグから消しきれないでいる心理に、一脈通じるものがあったような気がしてならない。
現在の70歳代、80歳代のゴルファーは、プロもアマも3ウッド(D、3W、4W)+8アイアン(2I~9I)+2ウエッジ(PW、SW)時代から始め、その後、2I、3Iの代わりに5W、7Wを入れたセットで長い間プレーを続けてきた。この流れは、年齢を重ねると同時に2I、3Iよりも5W、7Wに打ち易さ、高弾道の利点が認められたからである。
ユーテリティの進出
新しいクラブセットの波は、2005年が過ぎたあたりから徐々に始まっていた。それはフェアウェイウッドの数が少なくなり、代わってユーテリティの出現とウエッジの増加である。
それを2018年から2019年半ばにかけて、米ゴルフ誌(ゴルフダイジェスト、同ゴルフマガジン)に載ったプロのバッグの中身から調べてみた。
2005年以前は、前に述べたようにウッド4本、または5本。アイアンが2番から9番、ウエッジがPW、SWというのが主流だった。だが、それから15年が経たない間に、バッグの中身はかなりの変わりようを見せた。
2005年がすぎたあたりから、アメリカの女子プロや飛距離に劣る男子プロなどの間で、ユーテリティといわれる新しいクラブが使われ始めた。
例えば女子プロのポーラー・クリーマーがユーテリティの3、4番をバッグに入れ、男子のジョナサン・ケイはユーテリティの3番、シーン・オヘアとK・G・ジョイも同じ3番をバッグに入れていたと資料に記されている。
そして現状は、前記、米ゴルフ2誌に載っている、16名のツアープロのうち9名のプロが、ユーテリティを1、2本、ウエッジを3本入れているのが普通になった。
塩ジイのバッグの中身は2005年のアーノルド・パーマーの中味に近い。ユーテリティは1本しか入っていない。プロがいうボールの上がりやすさ、打ちやすさを考えれば、もう少しセット内容を検討してもいいのではないか。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年11月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

飛距離が落ちたと自覚してから6年が過ぎた。その間、飛ばなくなるのは仕方がないにしても、その幅を全盛時の30ヤード減程度に収めたいと思っていた。そのために手を替え、品を替えて飛距離回復に挑戦してきた。
だがここへきて、この方針を変更せざるをえなくなったのではないかと気がついた。
それというのも、数週間前、所属コースでラウンドしていたとき、ドライバーの飛距離が最盛期と比較して、50ヤード近く飛ばなくなっていることを知らされたからである。
30年間、メンバーとして同じコースでプレーしてきたので、若いときと今の飛距離とは、簡単に比べることができたのである。この差をはっきりと自分の目で確かめて、飛距離減退という天命には、勝てないものと痛感させられたのだ。同時にこれまでのラウンドでは、前記のように飛距離を落とすまいとする努力とともに、心のどこかにエージシュートで回りたいという欲求も一緒についてまわっていた。
いま冷静に考えると、これこそ「二兎を追う者は一兎をも得ず」ではないかと思った。つまり飛距離も落としたくない、エージシュートも回を重ねたいというのは、両立しないということにも、気がついたのである。飛ばしのことばかり考えてプレーすると、パワースウィングのみに気が散って、どうしても攻め方が雑になってしまうからである。
そして、結論は飛距離ダウンが避けられないのであれば、そのテーマへの挑戦はやめて、スコアメイクに重点を置くゴルフに転換することだと決めたのである。そうすれば、これからはエージシュートを目指して、ぶれない気持ちでラウンドすることができる。
飛距離減退と新計画
そこで飛ばしのゴルフからスコアメイク重視への具体案として、いままでのパーオン2パットの戦法から、ボギーオン+2パットへ変えることを思いついたのだ。
ボギーオンならよほど長い距離のホールでもない限り、グリーンを狙う3打目の距離は、ショートアイアンかウエッジで十分間に合うはずだ。
例えば400ヤードのパー4ホールを前にしたとき、2オン計画では、ドライバーとスプーンの百%ナイスショットを前提にして攻めるが、3オン2パットのボギー戦術なら、200ヤードのドライバーの後、残りの200ヤードを2回のショットに分けて狙っていくことになる。
すると誰でもミスの少ないクラブを2本、あるいは2本とも得意なクラブを使おうという気持ちになる。
塩ジイの場合は150ヤードの4番ハイブリッドと、残りの50ヤードを58度のウエッジで攻めていく戦法が浮かんでくる。
2本のロングショットでグリーンに乗せるのも豪快で気持ちがいいが、3回に分けて緻密に攻めていくのも、決して後味の悪いものではない。
もう一つのボギーオン戦法
最近よくレイアップという言葉を耳にする。状況によって目標を狙わずに、一度ほかのポイントに打っておいて、次のショットで真の目標に打っていくという戦法である。アメリカでは昔からよく使われていた言葉らしいが、日本では「刻んで打つ」といわれていたショットで、レイアップと表現されるようになったのは、10年くらい前からである。
塩ジイがこれから本腰を入れてやろうとしているボギーオン+2パット作戦は、レイアップ戦術とほとんど同じ内容である。
例えば320ヤードの短いパー4をプレーするとしよう。ティーショットは力んで180ヤード飛んだが、右のラフ。ピンまでの残りの距離は140ヤードだ。周りをバンカーが取り囲んでいるグリーンを考えると、3オン+2パット戦法の安全策しかないと考える。
そこで2打に分けて使うクラブだが、この場合は飛距離70ヤードのアプローチウエッジを2回使うアイディアを選ぶ。
ボールがラフにあっても、第2打でできるだけグリーンに近づけたいという気持ちは誰にでもある。だが、ラフの中にあるボールをピンまでの距離に合わせて、ロフトの少ない7番とか6番アイアンで攻めていくのは危険この上ない。ラフに食われてヘッドが抜けずに、チョロか、ダックフックで、大きく左へ逸らしてしまうのがオチである。
ここではやはり、2打をアプローチウエッジで70ヤードほど確実に前方のフェアウェーに脱出させることにする。そして、次の70ヤードを一度使って手応えを感じているアプローチウエッジでアタックしようとする戦法だ。この短いパー4でのレイアップ計画もボギーオン作戦の一部と見てよい。
新戦法と練習法
ボギーオン作戦を始めると、最後にピンを狙うショットでは、できるだけホールの近くに寄ってくれることを期待する。パー4の3打目がグリーンに着地後、ホールの近くまで転がってくれれば、パーオン作戦ではバーディに相当するパーが手に入るからだ。
そんなわけで塩ジイはいま、ピンを狙う最後のショットのために58度のウエッジで特訓中である。このクラブで4つの目標を打ち分ける練習に頑張っている。30ヤードのアプローチショットから始めて、40ヤード、50ヤード、60ヤード、と10ヤード刻みに距離を伸ばしていく方法だ。
この練習はボギーオン+2パット作戦が続く限り、続けなければならないと思っている。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)201年月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

「ストロークプレーは、全てのゴルファーにとって、さながら頭上に釣り下がるダモクレスの剣の下でプレーするようなものである」
これは作家の摂津茂和さんが「ゴルフ名言集」(1972年刊=鶴書房刊)に採り上げたバーナード・ダーウィンの言葉である。
ダモクレスの剣とは、ギリシャ神話に出てくる話で、現在のシチリア島を治めていたデオニシウス2世(紀元前430~367年)とその家来であるダモクレスが絡んだ逸話によるものである。
デオニシウス2世はある宴会で、彼の権力とその栄光を羨むダモクレスを呼び、王座に彼を座らせた。彼はそのとき、頭上に細い毛髪のような紐で吊るされた剣を発見する。
「王者はいつも幸福というわけではなく、常に危険と隣り合わせている」ということを、暗に家来のダモクレスにさとしたという古事にもとづくものである。
イギリスで最高のゴルフ評論家バーナード・ダーウィンが、なぜストロークプレーにこの言葉を使ったのかというと、1ホールごとに勝敗を決めていくマッチプレーと違って、ストロークプレーでは1ホールで二桁以上も打つことがあって、こうなるともう取り返しがつかなくなるというところから、ダモクレスの剣にたとえたのであろうと、摂津さんは説明している。
ゴルフが面白くなくなる
前説が長くなってしまったが、ゴルフも老齢の域に達してくると、1ラウンドに何回もダモクレスの剣が頭上に落ちてくる。
そのためにスコアカードには、8とか9といったスコアが何個も書き込まれるようになる。
最近の米ゴルフダイジェスト誌に、マリナ・アレックスさん(LPGAツアープロ)が「ダメージコントロール」と題して、一文を載せている。その書き出しにも「一つの曲って飛ぶショット、1回のショートパットのミス、そしてあるホールでの大たたきなどが、時としてそのラウンドを台無しにしてしまう」と書いている。
今の日本でのゴルフといえば、ほとんどがストロークプレーによる競技だ。もちろん塩ジイも所属クラブの競技会を敬遠するようになってから、マッチプレーのラウンドをしたことがない。それだけに、1ホールで二桁に近いスコアになる確率も高くなるわけだ。
さらに、高年齢層のゴルファーにとっては、運動能力や集中力の衰退により、一層、ワンホールでの大たたきの回数が多くなるのも当然である。
ゴルファーにも個人差があるが、さすがに80歳近くなると、ゴルフ場に姿を見せなくなる人が目立って多くなる。その理由は、疲れて18ホールを回れなくなったなどの健康面の問題。あるいは、「ボールも飛ばないし、自分でも考えられないようなスコアを叩く。ゴルフが面白くなくなった」といったのも多く聞く。
足腰が弱って1ラウンドを回れなくなったというのは、お気の毒というしかないが、問題は後者の「ゴルフが面白くなくなった」というケースである。
シニアゴルファーにとって、飛距離が落ちるのは仕方ないとして、スコアが悪くなるというだけで、長い間親しんだゴルフをやめてしまうのはいかにも惜しい気がする。
こんな話を聞くと、マリナ・アレックスさんが唱えるダメージ・コントロールこそ、70歳過ぎのゴルファーにとって、必須の研究課題のように思えてくる。もしここで高年齢ゴルファーが遭遇する多くの難ショットに、ダメージコントロールが働いて、二桁に近いストロークを少しでも減らすことができれば、ゴルフに興味を繋ぎとめておくことができるかもしれないからだ。
ミスショット回避術
塩ジイは長い間ゴルフを続けてきたことで、なんとなくショットが悪くなったときには「こうすれば、このミスショットを修正できる」というコツをいくつか身につけている。塩ジイなりのダメージコントロールである。
今でもウッドやアイアンで、時々出るのがダックフック(通称チーピン)だが、これが出たときには、塩ジイ自身の方法で修正することがある。
具体的には前のホールでティーショットを左のOB地帯へ打ち込んでしまったときである。
ここで塩ジイはティーショットの前に、右肩をトップの位置にキープしたまま、両手をストンと落とすダウンスウィングを2、3度やってみる。それからボールに向かってアドレスに入るようにしている。
この一瞬右肩を止めて、両手を体の右サイドへ落下させる動きで、塩ジイの欠点であるダウンスウィングでの右肩の早い開きと、力の入りすぎた振り降ろしが矯正され、ダックフックの危険を回避できるようになるのである。
あるいはアイアンショットでも、トップ病に襲われたときは、構えたときの背骨を地面に対して垂直にし、左足荷重になるようにチェックする。これでボールの頭を叩く軌道から、ボールの先の芝を削り取るダウンブローへの軌道に修正することができる。
そんなことが分かっていれば、いつもそのように打てばいいではないかと思われるかもしれないが、老齢でアマチュアゴルファーの悲しさ、危険なホールや、ここが勝負といった場面になると、つい悪い癖が出てしまうのだ。
だがここへきて、有難いことにM・アレックスさんのいうダメージコントロールのお蔭で、これからもダモクレスの剣の下でのゴルフが続けられそうである。

「ダウンスウィングのスタートは、両腕をドロップさせる動きから始める。だがその時、頭と両肩はトップのままだ」
この言葉を初めて目にしたのは、今から12年前の米ゴルフマガジン誌だった。アメリカの著名なレッスンプロ、ショーン・ハンフリーズ氏が「再現可能なスウィングの作り方」と題した特集である。
塩ジイは、この教えを拙著「ゴルフ死ぬまで上達するヒント」(2014年=ゴルフダイジェスト社発行)で「切り返しの方法として注目すべきレッスン」と紹介した。
なぜ注目したのかといえば、当時塩ジイは早すぎる切り返しと、ダウンスウィングのスタートとともにコックが解けてしまう欠点に悩まされ、その矯正に苦労していたからである。
有難いことに、このハンフリーズ氏のレッスンのお陰で、二つの欠点がかなり改善できた。2年後には倶楽部のグランドシニア選手権で、思いもかけず76、77のエージシュートで優勝することができた。77歳という参加者中最高齢であり、塩ジイにとっては、同倶楽部での3回目の栄誉だった。
再現性が高い両腕ドロップ
両腕のドロップと両肩の開きを抑えて、ダウンスウィングをスタートする練習は、今でもちょくちょく採り上げている。というのも、せっかちな性格と旧制中学から大学の2年まで、陸上競技の投てきを専門にやってきたので、若い時からダウンスウィングになると、どうしても必要以上の力に頼ってしまう。それが時々顔を出してしまうのである。
そんなこともあって、両腕ドロップのハンフリーズ理論には、これまでも数え切れないほどお世話になっている。
そして有難いことに、この方法は練習場でのナイスショットが、実際のラウンドでも再現できるという利点があった。
ゴルフの場合、練習場でいくらナイスショットが出ても、本番では期待に反して裏切られることが多い。「練習場ではよかったのになぜ?」と頭を抱えてしまうケースは誰にでもあるはず。
それなのに、ハンフリーズ氏の両腕ドロップと、両肩の開きを抑える打ち方は、12年前の雑誌のタイトルに偽りなく、再現性が非常に高いのである。
なぜ再現性に優れているのか。
塩ジイはハンフリーズ理論が、非常にシンプルな動きだからと思っている。一口にいえば、トップに達した両手をコックしたまま、バックスウィングの軌道へストンと落とすだけという感じである。
もちろんここでは、速く、強く振り下ろそうとする必要は全くない。ただ、両手をそのまま単純に軌道へ落としてやるだけで、筋肉がすぐ応じてくれるわけである。
有力プロも推奨
頭と両肩をトップのままにして、両手をドロップするのが、なぜダウンスウィングのスタートによい結果をもたらすのか。その辺を整理してみると①肩の早い開きを抑えて、インサイドからのヘッド軌道を確保、②コックのキープが、ヘッドの加速を生む技術につながる、③力む必要がないので、頭を静止した状態に保ちやすくなるなどが考えられる。
ハンフリーズ氏は、切り返しの要点として、両腕のドロップ、頭、両肩キープのほかに、体重移動の重要さを挙げている。だが、幸いなことにウェイトシフトについては、これまでの練習で、ほぼ身につけていたので、実際にはあまり気にすることがなかった。これなども塩ジイにとっては、ハンフリーズ理論を再現しやすくした一つなのかもしれない。
冒頭で書いたように、塩ジイがハンフリーズ氏のドロップ論を読んだのは12年前の2007年だった。最近、塩ジイが米・英の雑誌をチェックした限りでは、その以前には、切り返しでの「両腕ドロップ」という言葉は発見できなかった。
この方法を推奨するツアープロやレッスンプロが、雑誌に載るようになったのはその後だった。その名手たちの言葉を米ゴルフマガジン誌から拾ってみよう。
スペインの名手で早くからアメリカツアーで活躍しているセルヒオ・ガルシアは、ハンフリーズ氏が雑誌に発表した3ヶ月後に「ドライバーについての打ち方にはいろいろあるが、私にとって役に立つのは両腕をトップからまっすぐにドロップさせることだ」と述べている。そしてこの両腕のドロップはパワーを得る貴重な〝間〟になっているともいっている。
次にスーパースターで目を引いたのは、アーニー・エルス(南アフリカ)だ。
彼は「ダウンスウィングのスタートでは、両腕を体から離れたところへドロップさせ、シャフトは、体の近くに落とすように(註・コックをしたままという意味)振り下ろす」と、細かく分析する。
米ツアーで、屈指のロングヒッターであり、世界ランクでも上位を占めるダスティン・ジョンソン、それにジャステン・ローズも「ダウンスウィングのスタートを両腕のドロップから始めよ」といっている。
ジョンソンは両手を右耳から遠く離して落とすことを推奨し、ローズは「自然のコックにまかせながら両腕をドロップさせる点に注意を払っている。クラブヘッドは自然にインサイドからボールに向かっていく」と両手ドロップのポイントを説明している。
もちろん、こうした名手やレッスンプロたちの記事は、年を追うごとに雑誌に載る回数が増えている。クラブの進歩は誰もが認めるところだが、ここへきての両手のドロップによる切り返しは、スウィング技術進化の象徴的ポイントといえるかもしれない。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年8月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら
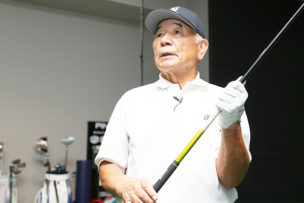
ある日、塩ジイは食事を終えて、クラブハウス内の洗面台の前に立っていた。そこへ顔見知りの歯科医の先生がやってきて、歯を磨き始めた。いつものように、ゴルフ場でも、食事の後は歯を磨く習慣になっているらしかった。
手を洗いながら、先生の歯を磨く音を聞いて、塩ジイとは違うなと感じた。こちらはどちらかというとゴシゴシという音がしているのに、先生のはシュッシュッといかにも軽やかな響きの良い音に聞こえた。
どうしたらあんな音が出るのか、帰宅してから早速実験してみた。いろいろやっているうちに、ペンを持つようにブラシを軽く握って、小刻みにそれを動かすのがコツだと気がついた。塩ジイみたいに、西洋料理でナイフを使うときのような握り方をしていると、どうしてもゴシゴシという音になってしまう。
その時から先生のような磨き方を心掛けようと思って始めたのだが、待てよ、このシュッという感じと、ゴシゴシという感覚の違いについては、ゴルフでもどこかの練習場で、プロからレッスンを受けたような気がした。
それはハワイでのゴルフ研修会のとき、アメリカのレッスンプロから、ショートアプローチの打ち方を習ったときだった。
若い頃だったので、レッスンプロの名前は忘れたが、1週間にわたる講習の中で、彼はグリップの強さについて、いつも目を光らせていた。とくにグリーン周りのアプローチでは、プロは幾度となく「もっと力を抜いて」と塩ジイのグリップを指差しながら注意を喚起した。
グリップに力が入っていると、ドスンと上からボールに叩きつけるような打ち方になり、ダフったりボールの頭を叩いたりするミスショットの確率が高くなるというのが理由だった。
それに対して、吸い付くような柔らかいグリップをしていると、クラブの振りもゆったりして、インパクトでも、ボールの前後5センチくらいの幅で、低く一定の速さでボールの下を滑って行く。これが距離と方向を正確にするということも彼は付け加えた。
その通りやってみると、柔らかい球筋で面白いほどピンに寄っていく。プロは「そうだろう」というように、塩ジイに片目をつむってニコッと笑った。
だが塩ジイは若かった。当時アメリカツアーで流行っていた低くて、よくスピンが効いたアプローチショットのほうに夢中になっていた。つまり粋がって、ボールの背中から、地面に急角度に打ちおろすチェックショットという打ち方に憧れていたのである。
そしてそれから以後も、ハワイで教わった、あの柔らかい握りのショットには見向きもせず、ショートアプローチといえば、ダウンブローで、スピンの効いたピッチショットが、塩ジイの主流になってきたのである。
1日千発の猛練習
80歳を迎える前、これからの年代は、ドライバーからアイアンまで飛距離が落ちていくから、ショートアプローチの優劣がスコアメイクの鍵を握ると思って、練習は短いアプローチが中心となった。もちろん打ち方はボールの先の芝を削りとるダウンブロー型だ。近くの練習場で1日3時間かけて、10ヤードくらいの距離を千発撃った。これを1週間続けた。
これは関西の杉原輝雄プロを取材したとき、ショートアプローチの練習で、グリーンにボールの山を築いているのを見たことによる。彼に「何発くらい打つとあのような山になるの」と聞いてみた。「千発だよ」とシャイな彼は小さな声で言った。80歳を迎えた塩ジイの千発練習も、杉原プロのボールの山が伏線にあった。
その後もアプローチの山積み練習を続けた。努力したせいか、深いラフ、ベアグラウンドなど特殊なライを除けば、グリーン周りからはほとんど1メートル以内には寄るようになった。
距離が落ちて、当分はそれなりのスコアをキープできそうだと、ホッとした気持ちになっていた。
マッチ擦り打法
ところが悲劇が起こった。
この短いショットに、突然のイップスが襲ったのである。練習や素振りではクラブヘッドがスムーズに振り下ろされるが、実戦になると、ボールが視界から消え、めちゃくちゃ早いクラブヘッド、手首を使ってすくい上げる打ち方になってしまう。結果はダフり、トップ、2度打ちだ。たまに上手く当たっても、当たりが強く、カップをはるかにオーバーしてしまう。
そのイップスはまだ治りきっていない。だが、少しずつまともな当たりが出るようになった。それというのも、昨年の暮あたりから採り入れたボールの前後10センチ幅を、浅い軌道で、インからインへ抜く練習が身につき始めたからではないかと思っている。
このボールを払うような打ち方にたどり着いたのは、アメリカのゴルフ雑誌で読んだアーニー・エルス(南ア)の「ショートアプローチのインパクトは、あたかも地面というマッチに、ウエッジというマッチの棒で火をつけるようなものだ」という解説だった。
マッチの棒に火をつけるときは、ドンと打ちつけるのではなく、まさしくシュッという音とともに薄く擦すらなければならない。
遠い昔、ハワイでプロから教わった打ち方が、いまアーニー・エルスの技術解説で蘇ったのである。
そして、このアーニー・エルスのマッチ擦り打法は、短いアプローチだけではなく、他のアイアンにも応用できるはず。老齢にふさわしく、豪打からソフト打法へ、そのきっかけをつかんだような気がしている。
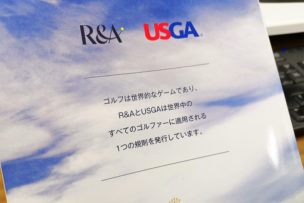
新しくゴルフの規則が変わって、早くも5ヶ月が過ぎようとしている。例年と違って、かなり大幅な改正なので、塩ジイがルール改正後に体験したこと、話に聞いたことなどから、ちょっとばかり気になった点をご紹介しよう。
ピンを抜く人、立てる人
「どう、今度のルール改正で、少しはプレーが早くなった?」
4月に入ったばかりの頃、古いキャディに聞いてみた。
「そうですね、これまでのラウンドで早かった人は、今度の改正でさらに早く、逆に遅かった人は、新ルールになっても時間短縮にはなっていませんね」
「なぜ?」
「ショートパットでピンを抜く人と、立てておいたほうがいいという人に分かれるからです」
という答えが返ってきた。
「例えば、これまでもOKパットでプレーをしていた人は、1ラウンド、ほとんどピンを抜かずに済ましています。こうした組は20~30分早くなっているのではないでしょうか。反対に短いパットでもOKなしでやってきた人たちは、ピンを抜きたい人、立てておきたい人いろいろです。抜いたり立てたりの時間が余計にかかってしまいます」
立てたピンに向けて打ってOKが出れば、ピンを抜く必要はないわけで、これを4人に当てはめれば、大幅な時間短縮は決して夢ではなくなる。
プライベートな競技などでは、マッチプレーでコンシードされるような短い距離は「OK」として、次のホールへ歩を進めるような「競技の条件」を加えたらどうか、と、つい思ってしまう。
基本はやはり遠球先打
進行を早める策として「ストロークプレーでは、安全が確保できるのであれば、球の位置に関係なく、準備ができたプレーヤーからプレーすることが奨励されます」(新しいゴルフ規則について=JGA GOLF Journal Vol.103)という一項は、新ルールが採用された1月1日から、ラウンド中にいつその状況がやってくるか、待ち望むような気持ちがあった。
というのも、我々の仲間うちでは、前々から「あいつ林の中で苦労しているから、進行上先に打って行こう」などと話し合って、ルール先取りでやってきていたからである。
つまり、新しくこの奨励策が出る前から、少しでもラウンドの時間を節約しようとして、すでに我々の間では実行済だったのである。それが晴れて日の目を見る日がやってきたのだ。
もちろんいつもの仲間同士でやるときは、安全のために、仲間の一人とか、あるいはキャディに「先に打つよ」と声をかけて打っていくのが自然に身についていた。
そんな4月のある日、仲間の一人が欠けて3人のところへ「K・Iと申します。どうぞよろしく」と初顔の人が入ってきた。
ところが順調に遠球先打のリズムでプレーを進めて行く我々の仲間とは関係なく、Iさんはボールのところへ行くと、辺りを見回すでもなく、真っ先に自分のボールを打ち始めたのである。
仲間の一人が「新ルールといってもあれは少しやりすぎではないのか」と言い出した。キャディも「ほかの人と打つのが一緒になって、ボールの行方を追うのも大変ですし、ちょっと危険なところもありますね」と言って眉をしかめた。
そのうち彼はパットでも自分の順番が来る前にそれをやり始めた。
一番長い距離を残した人が構えに入ろうとすると、Iさんは勝手に「お先に行きますよ」といって、さっさとボールを打ってしまう。
「集中して」いざ構えようとした遠球先打の人は、ここで仕切り直しだ。結果はその遠いパットをあっさりと3パットで天を仰ぐ。
いつもは楽しいゴルフが、この日はIさんに引っかき回された感じだった。みんなだんまりで、終始、 Iさんのショットが終わるのを待つ1日で、変則の遠球先打のゴルフが終わったのである。
前出の「新しいゴルフ規則について」では、規則が大きく変わった一方で「プレーヤーの責任を明確にし、プレーヤーの正直さ、誠実さを信じることを明記している」とも述べている。他の同伴競技者への影響という点から見れば、Iさんの行為はルール改正の真意とは大きくかけ離れている。
「遠球先打」を基本に、時に応じて「準備OKで先打」を採用するのが、新しいルールの精神ではないだろうか。
2度打ちでも罰なし
今年になって、まだ2度打ちを1回もやっていないことに、つい最近気がついた。
80歳の頃からショートアプローチやグリーンサイドのバンカーで、2度打ちが目立つようになった。大抵はダフった後、飛んでいくボールをヘッドが追いかけて、もう1度コツンとボールに触れてしまうのだ。ミスショットの中でも最低の後味の悪さである。
原因は手首を使ってボールをすくい上げるインパクトにある、というところまで突き止めた。だが実戦ではなかなか治りきるまでには至らなかった。短いショートアプローチの前に立つと〈2度打ちをするのではないか〉という不安な気持ちになり、手がすくんでいたためのようだ。
それが新ルール施行の今年から、2度打ちのことなど忘れてしまったかのように、スムーズなストロークができるようになった
なぜ、5年かけても治らなかった2度打ちが跡形もなく消えたのか。その答えは「例えば、偶然に2度打ちをしても罰はありません。そのストロークを1回と数えるだけです」(前出・新しいゴルフ規則について)という新ルールのおかげと思っている。肩の力が抜けたに違いない。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年6月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

「スタンスをとってしまえば、すべてが決定したのだ。なすべきことはただ一つ、ボールを打つの一途あるのみ」と言ったのはイギリスの心理学者レスリー・スコンである。
摂津茂和さんの「ゴルフ名言集」(鶴書房)の中に出てくる言葉だ。著者の解説によれば「スタンスを取った時には、すでに方針は決定されているのだから、あとは遅疑逡巡することなく、ボールを打つことに精神を集中すればよいのだ」ということになる。
また、アメリカ女子ツアーのレジェンド、スウェーデンのアニカ・ソレンスタムのコーチとして知られているピア・ニールソン女史も同じようなことをいっている。
「ボールの後方で目標を確認し、スウィングのチェックをしてから構えに入るのが一般的な方法だが、アドレスしたらスウィングのことは忘れて、ただボールを打つだけです」という話を東京での講演会で聞いた。
なぜ、こんな話を持ち出したかというと、近頃、塩ジイは実戦のティーグラウンドでも、フェアウェーでも、ボールを打つことよりも、スウィングのチェックのほうに、重点を置いて構えているような気がしてならないからだ。
ここ数年、塩ジイはダウンスウィングのスタートで、両手をドロップさせると説く、アメリカの有名なレッスンプロの言葉に従って練習を続けてきた。
難しい動きだが、ある程度の結果が出たので「今度こそは、ナイスショットにつながるのではないか」と大きな期待を抱いてコースに出ていた。
ところがである。この両手ドロップは、なんとも期待に背いて、いつも無残な結果に終わってしまう。ドライバーを始め、ウッドからアイアンまで、ダフる回数が目立ち始めたのだ。
なぜだろうと振り返ってみた結果、「構えたらボールを打つだけ」という言葉に反して、構えてもなお「両手をどのように振り下ろすか」とか「いつ体重を移動させるか」などの技術的なポイントに、力点を置きすぎていることに気がついた。
アドレス後は雑念を払う
「アドレスしたらボールを打つことに集中」という言葉は、ゴルフのスウィングが、頭で考えてコントロールできるほど簡単なものではない。「下手な考え、休むに似たり」ということにならないように気をつけろと言っているようにも聞こえる。
年間グランドスラムを達成したことで有名なボビー・ジョーンズも、スウィングの難しさを次のようにいっている。
<blockquote>
ゴルフがひどく腹立たしいゲームである理由の一つは、一度学んだことをいとも簡単に忘れてしまうことであり、われわれはすでに何度も気がついて矯正したはずの欠点と、いまだに戦い続けている自分を発見する。
しかしどんな矯正法にも永続的な効果があるとは思えず、スウィングの他の部分に気を取られた途端に、古い欠点が頭をもたげて、またしてもわれわれを悩ませる」
出典:<cite>ゴルフのすべて=ゴルフダイジェスト社・永井淳訳</cite>
</blockquote>
ボビー・ジョーンズにしてこの言葉である。われわれ一般のアマチュアが、構えてから前記のような技術のポイントにばかりとらわれていたら、身につきはじめた新しい技法などを生かすチャンスは全く絶望的である。
そればかりか、ジョーンズがいうように、すでに矯正されて良い方向に向かっているのに、古傷である力ずくのスウィングや手打ちなどを生き返らせてしまうことにもなりかねない。
以上のように考えてくると、塩ジイが選んだ新打法のラウンドで、貧打続出となったのも当然といえるかもしれない。
だが、実際問題、構えたらボールを打つことのみに集中しようとすると、これがなかなか難しい。
手本は若い女子プロたち
では、アドレスしたら、ただひたすらボールを打つことに専念するにはどうしたらよいか。まず頭に浮かんだのは、スポーツ雑誌社に勤めていたときに見たボクサーたちのシャドーボクシングである。
彼らがあの狭いリングの上で、軽快なステップを踏みながら、鋭く左右のストレートやジャブを繰り出す姿が印象的だった。
このときトレーナーにシャドーボクシングの効用について聞いてみた。彼は「ボクサーが相手の隙を見つけたとき、瞬時に手が出るように筋肉に教えているのです」と説明してくれた。
このようにシャドーボクシングが、無意識のうちに筋肉が反応して、パンチを出せるものであれば、素振りという〝シャドースウィング〟も「アドレス後には、ただボールを打つだけ」という心の環境作りに、もってこいの方法ではないかと考えたのである。
そこでシャドースウィングのお手本だが、塩ジイは女子プロ、それも〝黄金世代〟といわれる人たち若い人たちのスウィングだと思う。シンプルな軌道上を加速させたヘッドで振り抜くスウィング型のフォームがぴったり合うような気がするからだ。
女子ツアーを実地やTVで見る機会があれば、彼女らの素振りを参考にするのをお勧めする。
男子プロのスウィングにも学びたい人はたくさんいるが、シニアゴルファーの筋力からすれば、女子プロの飛びとフォームの柔らかさのほうに親しみが湧く。
プレーを遅らせないよう注意しながら、最初の素振りはハーフスウィングでゆっくりと振り、2回目はボールの先で「ビューンと音が出るようなスウィング」をして、なんとか雑念を払いのけるインパクトを目指したい。

塩ジイにとって、昨年からあるプロの打ち方に何か引っかかるものを感じている。
もうお気づきかもしれないが、韓国のチェ・ホソン選手のインパクトの後、右肩を下げながらもう一度くるっと回ってフィニッシュに至るあのスウィングだ。
塩ジイが初めてチェ・ホソン選手を知ったのは、2018年11月のカシオワールドオープンだった。TV観戦を決め込んでいたのだが、彼はこのビッグイベントで、ちょっと普段お目にかかれないフォームながら、堂々15アンダーの好スコアで優勝した。
続く日本シリーズJTカップでも、画面を通して彼のフォームを穴のあくほど見た。
どの大会でも彼の組には多くのギャラリーがついて回って、ショットごとに大きな歓声が上がっていた。同時に何か珍しいものでも見たような驚きの声も混じっていたように思えた。
塩ジイも最初のうちは、インパクト後に体を回しながら、あたかも歌舞伎役者が六法を踏むようなあの動きには、どんな意味があるのだろうかと思った。失礼ながらギャラリーへのサービスかとも考えた。
だが、待てよ、塩ジイにも、インパクト後に回転こそしなかったが、右足を半歩前へ出し、右肩を下げて、ボールを見送ったことがあった。彼のスウィングを頭に描いているうちに、幾たびかそれに近いフォームで打ったことを思い出した。
なぜそのようなフィニッシュになってしまうのか、よく考えてみると、そんな時に限って、インパクトの直前にフックの予感があり、フェースがかぶるのを防ぐために、咄嗟に右足を前へ出していたように思う。もしそのまま打ったら、俗にチーピンと言われる大フックを招いていたはずである。
だが、フィニッシュが不安定な割には、インパクトでボールのつぶれる感じが手に伝わり、軽いドローで飛距離もそこそこ出ていたように感じた。
そんな動きを頭に描いているうちに、もし、チェ・ホソン選手のようにボールを打ってすぐに、右肩を下げながら右足を半歩前に出し、その足を軸に1回転したら、彼と同じようなスウィングになるのではないだろうかと思った。
そして、結果はつかまり感の良いインパクトと程よいドローボールで距離も伸びているはず――と勝手にイメージを広げていた。
後でわかったのだが、彼の狙いは「年をとって(1973年生まれ。36歳)飛距離が落ちたのを考えてこの打ち方にした」と言っているそうだ。実際、インパクトでのつかまりの強さが36歳にして、今も282ヤードの平均飛距離を保つ要因になっているのではないか。
砲丸投げも回転投法
塩ジイは中学(旧制)、高校、大学(2年半ばまで)で、陸上競技の砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げなどをかじってきた。
中学時代を除けば、いずれも3流、4流選手で、これといった記録を残していない。ただ、大学2年までは、いわゆる部活で相当激しい練習をやってきた。
今も時々陸上競技をTVで見るのを楽しみにしている。その中で砲丸投げの選手のほとんどが、円盤投げのようにサークルの中で体を1回転させて投げているのに驚いた。
塩ジイのころは砲丸を右首に当て(右利きの場合)、背中を投げる方向に向け、右ひざを曲げ、右肩を下げた低い姿勢から、右足でステップして、直線的に腕を突き出して投げていたものだ。
それが今では前述のように、右足のステップに代えて、左足を軸に回転することから始動、その勢いを利用して、最後に前方へ突き出すやり方に変わったのだ。中には古い直線ステップ方式で投げている選手がいるが、傾向は回転の投げ方に移りつつあるという見方が強い。
砲丸投げの日本記録は18.85メートル(中村太地選手・ミズノ=2018年)だが、もちろん投げ方は回転投法だ。
投てき競技は日本人にとって不得手の種目といわれてきた。欧米人に比べて体力的に大きく劣っていたからである。今でもその傾向は残っているが、新技術を採り入れるという点では、日本人の器用さが有力な武器になる。
現在日本記録と世界記録の差は4メートル弱だが、回転投法による技術革新と欧米人に近づきつつある体力アップで、ここ数年で世界との差は大きく縮まってくるのではないかと期待している。
未来打法への第1歩か
塩ジイはチェ・ホソン選手の体の回転で飛ばすという打ち方が、回転投法へ進化を遂げた砲丸投げとかぶさってきてしまう。
塩ジイの頃は、砲丸投げの回転投法など考えもつかなかったと同じように、異常とさえ思える現在のチェ・ホソン選手の回転打法が「未来のゴルフスウィングへの入り口になるかもしれない」と、つい思ってしまうのである。
ほぼ半世紀前、オーストラリアの物理学者ミンディ・ブレーク博士は「未来のゴルフ」(日本語版/産報出版社=1952年)という著書で①強いフックグリップ②両つま先を飛球方向へ向けた構え③極端なアップライトスウィングなどの特徴を挙げていた。だがこの未来を透視した技術論は日の目をみることはなかった。
その点チェ・ホソン打法には、進化への伸びしろがたくさん残っているような気がする。
10年後、ダスティン・ジョンソンが新回転打法と称して、進化したチェ・ホソン打法を継承、45歳になっても、さらに飛距離を伸ばしている姿が重なって、どうしても頭から離れない。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界(GEW)2019年4月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら

ベン・ホーガンはプレー中、ほとんど口をきかず、多くのプロから煙たがられたという話を何かの本で読んだ。
だが、今でこそ、塩ジイは練習の効果を楽しむだけのゴルフになってしまったので、ベン・ホーガンのようにだんまりの人と一緒でも、それほど影響を受けることはなくなった。
だが、かつて、クラブの公式競技、関東や日本と名のつく競技会に顔を出していた頃は、同伴競技者から話しかけられる言葉や、聞こえよがしの独り言などには、大なり小なり影響を受けた。
どんな内容だったか、主だったものを整理してみると、だいたい次の3つのタイプに分けられる。
1.言い訳派
朝スタート前に「おはよう」の挨拶が終わるか終わらないうちに、「今日は寝不足でしてね」とか「ゆうべ飲みすぎて、今日は二日酔いなんで…」と話しかけてくる人たちだ。
塩ジイにも寝不足や二日酔いの経験は数え切れないほどある。一晩中、酒を飲んでいて、そのままコースへ出かけたこともあった。
こんな日は当然のことながら、集中力のかけらもないラウンドになる。「もう二度と、二日酔いのゴルフはやらない」と誓うのだが、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」で、また同じようなラウンドを性懲りもなく続けてきた。
そんなある時、「どんなに体調が悪くても、ゴルフをしようとして家を出たからには、何があろうと言い訳を口にするな」と、あるゴルフ場の支配人から言われたことがあった。
その支配人氏は「ゴルフで全力を挙げるのは、同伴競技者に対する礼儀。言い訳は卑怯」と厳しく語った。それからというもの、塩ジイは「言い訳をしない」を守ることに神経を使ってきた。
2.自己分析派
ドライバーからパットまで、一球一球、打ち終わってから、そのショットのどこがどうだったかを克明に説明し続ける人がいた。
「今のショットは頭を上げるのが少し早かったな」とか「体重が左へ乗らなかった」など、カートが動き出すと座ったまま手振り身振りで解説しはじめるのだ。スタートから最終ホールまで、こんな調子で自分のスウィングを熱心に語る。
最初のうちは「ま、だんだん調子が出てくるよ」などと、調子を合わせているのだが、5、6番ホールあたりまでくると、聞いているふりをするか、「今日は足を鍛えるか」とつぶやきながら、カートから降りて歩くと言う作戦をとったりした。
もし最後まで、彼の言葉を親身に聞いてあげていたら、自分のゴルフへの集中力は完全に失われていたに違いない。
このように自分のゴルフに浸りすぎて、一緒の組の人との正常な会話ができない人は、お世辞にも楽しい相手とは言えない。年をとるにつれて、残念ながら仲間がだんだん少なくなっていく。自分のゴルフだけしゃべり続けるのは、友人を失うという点で厳に慎まなければならないことだと今の塩ジイは思っている。
3.誉め殺し派
このタイプのプレーヤーは文字通り、同伴競技者のショットを褒めまくる人たちである。
人は誰でも褒められて悪い気はしないが、ちょっと芯を外したボールにも「ナイスショット!」という声がかかったりすると、なんとなく有難味が薄れてしまう。
昔、全盛時代の中村寅さん(寅吉プロ)から「おめえなんかの目からすれば、おれのショットはみんなナイスショットに見えっかもしれねえが、1Rで本当のナイスショットは3、4発しかねえんだよ」と聞かされたことがあった。
この話を聞いて、プロはもちろん、仲間のショットでも褒めるのは難しいものだと思うようになった。今は誰と回っていても本当にいいショットなのか、自分なりに見極めてから「グッドショット」と声をかけるようにしている。
言葉の心理戦
以上、プレーヤーとして敬遠されそうな人たちを挙げてきたが、実はプレー以外のおつきあいでは、話題も豊富で友人として、むしろ好ましいタイプに属する人が多い。今でもクラブハウスであったりすると、手を上げて寄ってきて、酒の席に加わったりする。
塩ジイはあまり好きな言葉ではないが、ゴルフには「言論戦」という言葉がある。親しい仲間同士が相手にプレッシャーを感じさせるような言葉を要所要所で何気なく口にするのがそれだ。
いわゆる「メタ・コミュニケーション」と言われる心理妨害作戦である。アメリカのスポーツ心理学者トーマス・タッコ教授は「誰かが何かを伝えるのに、直接に多くのコトバをもって言うのではなく、含みのある一挙一動の全体からしてそれとなく意のあるところをわからせるのである」(「スポーツサイキング」松田岩男・訳=講談社)とメタ・コミュニケーションについて説明している。
例えば池を前にしたティーショットで、Aが相手のBに向かって「昔はあの池によく入れたもんだがね」と何気なくつぶやく。するとBはなるべく池を見ないように平常心で打とうとしていたのに、Aの言葉が強い誘因となって、Bの目の前に池が大きく迫り、いやでもプレッシャーと戦わなければならなくなる。
BはAの言論戦にまんまとはめられたことになる。
エスプリの効いた健全な心理戦は捨てたものではないが、最近は言論戦への反応も鈍りがちだ。熱戦ゴルフから楽しむゴルフへの変わりようが、こんなところにも現れているのかもしれない。

悲劇は7年前に起きた。塩ジイが所属クラブのグランドシニア選手権で3度目の優勝を遂げた直後のことである。2週間にわたる36ホールズ競技で77、76という自分でもびっくりするような好スコアでの勝利だった。
信じられないような出来事に塩ジイは年甲斐もなく舞い上がってしまったのか、次への飛躍のためにある計画を思いついたのである。年老いて飛距離の落ちるのを見込んで、ショートゲームにいっそうの磨きをかけるのが骨子だった。
各クラブの飛距離が落ちてくると、どうしてもパーオンの確率が少なくなり、グリーンサイドからのアプローチに比重がかかるはずと読んでの発想である。
そこでどうしたかというと、近くの練習場の打ち放題の日に毎日千発ずつ7日間、ショートアプローチだけに限って打つという案だった。80歳(当時)に近い老ゴルファーにとっては、過酷ともとれるプランだったが、そのときはなんとなく「今やらなければ、時期を逸する」という追い込まれた心境にあったような気がする。
だが、良かれと思って採り入れた集中練習だが、意外にもこれがアダとなって、逆に大変な病気を抱え込んでしまったのだ。「同じ練習を単調に長時間繰り返すとイップスになりやすい」というアメリカ雑誌に載った警告の通りになってしまったのである。
最初の2、3年はピンに半分以上は寄っていたのだが、それから年を追うごとにアプローチの確率が悪くなっていった。5年後くらいからは成功率が10%以下だったと思う。
昔、まともなアプローチショットをしていた頃、「もしイップスになっても口外するな」という一文をアメリカのゴルフ雑誌で読んだことがあった。
実戦での成功率が10%くらいになったとき「イップスに違いない」と感じたが「オレはイップス」と認めてしまうと、本当の“病気”になって、回復に手間取るという記事を目にしており、絶対に口に出すまいと誓った。
柔らかい目で見る
イップスを意識してから、自分ではありとあらゆる打ち方を試したと思っている。例えば練習場でアプローチだけ千発打ったこともあった。そのうちの300発は右手だけで手首を固定してショットし、つぎに同様に手首を使わずに両手で300発を打った。そして、残りの400発は両目をつむって打ってみたりした。
厳しい課題の下で練習を重ねたのだが、練習に限っては、いつもうまく打てていた。このときもかなりの確率で芯を捉えて打つことができた。これで実戦でも上手くいくだろうと期待してコースに出たのだが、結果はいつものようにダフリ、トップ、それに2度打ちの3点盛りだった。
ここまでくると仲間も「なんで」とか「信じられない」という表情で塩ジイを見るようになった。そのたびにイップスであることを白状しようかと思ったが、なんとか耐え続けてきた。だが、歳のせいにしてはいけないが、とうとう根負けして80歳を過ぎてから、イップスであることを友人に告白した。
塩ジイは後悔した。その日からぐっと気持ちが楽になった。しかし気持ちは晴れてもコースでは依然として3点盛りのオンパレードだ。
イップスだといっていなかったら、今に見ていろ、こんな打ち方なんかすぐに治してやると意気込んだはずだが、それを口に出してからは、そんな気力なんかどこかへ吹き飛んでしまったように感じた。
ゴルフをしていても「早く失敗して楽になろう」とか「同伴競技者が見ていないうちに打ってしまおう」とか、姑息な手を用いるようになった。
このような状態が何ヶ月か続いた後、ふと我に返った。告白はしたが、もう一度イップス解消への挑戦をしてみようという気になった。たまたま古いアメリカの「ゴルフマガジン誌」に載っていたT・J・トマシ博士の「イップス撃退、7つの方法」という記事を読んだのがきっかけだった。
7つの項目の中で塩ジイの目にとまったのは、パッティングのイップスについての練習法であるが、その中の「ストローク中、顔をボールに向けたままにしない」というのに釘付けになった。
「パットしているときは、知らないうちに頭はわずかながらも動いている。ところが、イップスになると頭の自然な動きが押さえつけられてしまう。練習法としてはパッティングのスタンスをとったらわずかに顔を上げ、カップよりも遠くに視線を送る。
このときは睨むような目で見るのではなく、柔らかい目で見ること。これができたら、視線をカップに戻し、ジョーダン・スピースのようにボールを見ないでストロークする」
塩ジイの場合はパッティングというところをアプローチショットに置き変えればいいだけである。
昔、読売巨人軍の主戦投手H選手がスランプになったとき、順天堂大学の太田哲男教授(スポーツ心理学=故人)が「キャッチャーミットを睨みつけるような投球はやめて、薄眼を開けてやんわり見て投げなさい」と進言した。それでH選手のスランプが止んだ。今思うと凝視と柔らかい目という点ではよく似た話ではある。
スピースもボールを見て打っているというよりは、カップを見ながらストロークしている感じだ。腕前は天地の差だが、キャリアという点では塩ジイの方が勝っている。落下点だけを見て打てないはずがない。これでイップスが治れば、もう何もいうことはない。
<hr>
この記事は弊誌月刊ゴルフ用品界2017年12月号に掲載した記事をWeb用にアップしたものです。なお、記事内容は本誌掲載時のものであり、現況と異なる場合があります。
月刊ゴルフ用品界についてはこちら
 ゴルフ産業活性化メディア
ゴルフ産業活性化メディア 

